|
4.2.5 地域福祉交通計画の策定
需要動向分析を受けて、供給側としてどこにどの程度の地域福祉交通サービスを供給し、その財源をどのように確保するかを示す。公共交通を利用できない重度の歩行困難者等に個別に対応できるSTSについて検討する。
基本計画における対象者、対象地区の検討、計画手順と計画目標期間を踏まえ、需要動向分析と財源規模の両方を見定めた上で、以下の視点から具体的な地域福祉交通サービスの策定を行う。
・総合的な視点で地域福祉交通サービスの資金調達を検討する。
・全ての高齢者・障害者がドア・ツー・ドアのSTSを必要としているわけではなく、利用者の歩行能力あるいは身体状況等からみた公共交通利用可能性を一つの基準として、交通サービス別利用資格を検討する。
・利用者を歩行能力あるいは公共交通利用能力別に分類することは、公的資金の制約、利用者負担率の抑制を考慮した効率的なサービス提供のためにも必要である。
・地域福祉交通サービス関係者の役割分担について検討する。
・STS運営計画を中心とした具体的な供給サービスを検討する。
(1)検討手順
1)地域福祉交通計画
可能な資金調達方法を検討した上で、実施のための計画の検討を行う(図4-9)。
図4-9 地域福祉交通計画の策定メニュー
2)STSの運営計画
ドア・ツー・ドアのSTSについて、運営形態、運行計画、資金調達、事業収支計画の順で検討する。
(2)検討内容
1)地域福祉交通計画
a)資金調達
地域福祉交通サービスの資金調達を検討する。例えば表4-12のような財源がある。
表4-12 財源の種類と課題
| 財源 |
課題 |
| 利用者からの負担(利用料金) |
・利用料金のみで成り立っている福祉交通が少ない
・料金を高くすると、利用者が増えない |
| 国、都道府県、市区町村からの補助、助成金 |
・地域福祉交通サービスの運行に適用される補助、助成金は限られている |
| 自治体が既に行っている、高齢者・障害者の移動支援のための施策への予算配分を地域福祉交通計画全体での見直し |
・自治体の財源が逼迫している
・(あまり利用されていないものも含めて)既存のサービスを縮小して、別のサービスに振り替えるためには、既存サービス利用者が納得する説明が必要 |
|
b)実施のための検討
ア)交通サービス別利用資格の詳細検討
地域福祉交通サービス別利用資格の詳細検討を図4-10に具体的に示す。
検討基準は「案1高齢者・障害者の歩行能力を個別に認定」が最も望ましい。
参考:利用資格検討の際には、介護保険制度における要介護5の人に比べて要介護3、4の人に対するモビリティ保障が十分でないこと、要介護1、2の自立可能な人でも移動困難な人はいること等がヒアリング調査で明らかになっている。
地域福祉交通サービス利用資格の分類例
図4-10 地域福祉交通サービス利用資格の分類例
(拡大画面:40KB) |
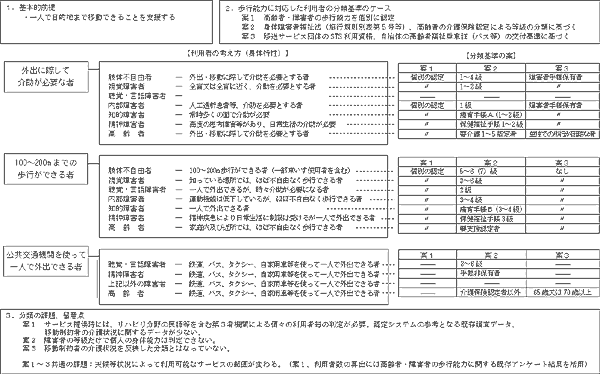 |
欧米ではSTS利用資格について、以下のような基準を設けている。
参考:欧米におけるSTSの利用資格
・HTハンディキャップ・サービス(コペンハーゲン)
(1)18歳以上であること。(18歳未満には別の制度がある)
(2)大コペンハーゲン都市圏居住者であること。
(3)既存の公共交通が利用できない状況であること。
(4)車いす使用もしくは何らかの障害者補助具を地方自治体から提供されていること。
表4-13 ハンディダートの利用資格(バンクーバー)
| 運動(移動)機能に関する障害(例:関節炎、下肢欠損、多重硬化症、これらに類するもの) |
−自宅から最寄のバス停まで歩行が困難である
−階段やスロープを使うのが困難
−バスの乗降が困難 |
| 神経に関する障害(例:脳性麻痺、精神障害、老化による認知障害等) |
−交通の利用案内、行き先案内等が理解できない場合 (外国語が理解できない場合は除く)
−混乱、錯乱により安全に公共交通が利用できない場合 |
| 知覚に関する障害(例:視覚障害) |
−視覚障害により公共交通の利用が困難である |
| 健康上の(医療に関する)障害(例:心臓疾患、呼吸器障害等) |
−既存のバスで移動する事が困難という診断書がある場合
−居住地(自宅、医療施設等)から最寄のバス停までの移動が困難という診断書がある場合 |
|
参考:案1認定システムの事例
・ADAのパラトランジット
利用資格について、所定の申請書で申し込み、診断書の作成、身体機能テストを受ける必要がある。
・ロンドンのアンビュランスサービス(PTS:非救急の患者輸送サービス)
利用できるのは、医師や専門家がその必要性を認めた場合である。サービスを利用するためには通院が必要であること、公共交通での通院が困難であることが条件となる。判断は医師が行う。
利用者には歩行が可能な人もおり、基本的には公共交通を利用すると考えられるが、あくまで医師の指示に基づくので、医師がPTSを利用するように指示すれば利用可能になる。この場合セダンタイプの乗用車を利用することが多い。
出典:「欧米主要国における高齢者・障害者の移動に関する調査」平成11年度報告書、交通エコロジー・モビリティ財団
「英国における障害者・高齢者を対象としたSTSセミナー」平成12年10月、STSセミナー実行委員会、日本財団
「欧米主要国における高齢者・障害者の移動円滑化に関する総合調査」平成13年度報告書、交通エコロジー・モビリティ財団
参考:介護保険制度の認定制度
一次判定と二次判定をおこなって、要支援から要介護1〜要介護5までの6段階の要介護度を決定している。
一次判定では、利用者は市町村の訪問調査員による調査を受け、85項目の調査結果をコンピューターソフトで判断する。
その後、市町村の介護認定審査会が一次判定をもとに、調査員のコメント、主治医の意見書を加味して要介護度の二次判定をおこない、最終的な要介護度が決定する(表4-14)。
表4-14 介護保険制度の認定区分
| 介護度区分 |
身体の状態(おおまかな目安) |
| 要支援 |
社会的支援を要する状態 |
日常生活の能力は基本的にあるが、入浴など一部介助が必要。 |
| 要介護1 |
部分的な介護を要する状態 |
立ち上がりや歩行が不安定。 排泄、入浴など一部介助が必要。 |
| 要介護2 |
軽度の介護を要する状態 |
立ち上がりや歩行などが自力では困難。 排泄、入浴などで一部または全体の介助が必要。 |
| 要介護3 |
中程度の介護を要する状態 |
立ち上がりや歩行などが自力ではできない。 排泄、入浴などで全体の介助が必要。 |
| 要介護4 |
重度の介護を要する状態 |
排泄、入浴、衣服の着脱など、日常生活に全面的介助が必要。 |
| 要介護5 |
最重度の介護を要する状態 |
意思の伝達が困難。 生活全般について全面的介助が必要。 |
|
出典:自治体ホームページによる
イ)関係者の役割分担
サービス提供者、行政機関等の調整を行う。地域福祉交通サービスの運行に必要な関係者の、現状の取り組み状況を下記に整理した。
・サービス供給者
NPO等ボランティア団体、社会福祉協議会
NPO等ボランティア団体、社会福祉協議会等の非営利団体は、移動困難な高齢者・障害者に対して、非営利の組織が会員制等により自宅から目的地まで等の送迎サービス(移送サービス)を提供している。
活動資金は会費、実費の利用料金、寄附、支援団体からの助成金等で構成され、市区町村が委託(委託費を拠出)して運営が存続している。
タクシー事業者
福祉輸送の分野への参入を開始した事業者が増加傾向にあり、自治体の委託を受けている事業者もある。一部、移送以外の在宅介護の分野にも進出している事業者もある。
(1)福祉タクシー
福祉タクシーとは、高齢者・障害者等の移動制約者の病院・施設等への通院等のニーズに対応したサービスとして、車いす使用者やストレッチャー使用者が乗降できるリフト等を備えた専用のタクシー車両による輸送サービス。道路運送法上は車いす使用者等に限定した8ナンバーの許可を取得しての運行を指す。
(2)介護タクシー(ケア付きタクシー)
要介護高齢者を対象に、ホームヘルパー資格を取得した介護ドライバーが主にセダン型タクシー車両を運転し、乗降介助サービスを提供するタクシー。
介護タクシーの単位認定については、平成14年度まで乗車・降車の介助行為につき身体介護の報酬(30分:210単位)が算定されて、利用者は2,100円のうち、1割のみ(210円)負担で利用できた。平成15年度以降、要介護1以上の人は「通院等のための乗車・降車の介助」を行った場合に1回100単位(1,000円)認定、利用者は乗降介助に対して1割(100円)負担することとなった。タクシーでの移動自体は介護保険の対象外となっている。
(3)施設送迎サービス
タクシー事業者や福祉関係の送迎に特化した事業者が、施設巡回バス、通所型施設への送迎サービス、デイサービスの移送等を担っている。福祉施設や病院への送迎を主とする乗合タクシー等もある。
バス事業者
ほとんどのバス路線は、黒字となるまでの利用者数がなく、何らかの公的補助を受けている場合が多い。交通不便地域における生活交通の確保のため、自治体がバス、タクシー事業者に乗合バスの運行を委託、又は依頼する事例も見られる。
・行政機関
国(国土交通省)
国土交通省の自動車交通局は構造改革特別区域法(平成14年、以下特区という)3条に基づく構造改革特別区域基本方針(平成15年1月)において「NPO等によるボランティア輸送としての有償運送可能化事業」が盛り込まれた。これは地方公共団体が、当該地域内での輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交通機関によっては移動制約者に係る十分な輸送サービスが確保できないと認めた場合、NPO等ボランティア輸送における有償運送の実施管理のための運営協議会を設け、内閣総理大臣に申請し、「構造改革特別区域計画」に認定を申請し、認定を受けるものである。
平成14年度には、札幌市において「スペシャルトランスポートサービス(STS)実証実験調査」を実施し、タクシーやNPO等ボランティア団体によるSTSシステム構築のため、共同配車センターの設置やサービス水準の確保等が必要との報告書をまとめた。
国(厚生労働省)
平成12年度創設の介護予防・生活支援(外出支援サービス等による自立した生活の支援)事業は、自治体への補助、福祉サービスの一部として実施されており、自治体ごとにその利用状況は異なる。平成12年4月に介護保険制度が実施され、平成15年4月からは支援費事業も発足した。
都道府県
東京都や神奈川県でも80年代から、STS車両への補助が取り組まれているが、政策的には今後の方向性について十分なビジョンを持ったものと言えない側面がある。その他の道府県:多くの自治体で乗合バス(特に過疎地域)への補助制度がある。
市区町村
都市部では、コミュニティバスの運行が広がり、地方部では、高齢化、民間バスの廃止代替、学校の統廃合等の社会的背景から、自治体が主体的に計画するバス路線が増えている。しかし、高齢者・障害者のモビリティ保障を交通計画及び都市計画、福祉部門との連携した視点からの計画が必要である。
ウ)供給サービスの検討
地域福祉交通計画の策定において、以下のような視点が必要である。
バスは需要に応じてフレキシブルな運行をするバス及びバス路線の再編等を含めた検討、車両の更新に伴うノンステップバスの導入を行う。一方、公共交通機関を利用できない重度の歩行困難者に対応するためには、福祉タクシーや移送サービス等の個別移動手段が必要であり、地域内でどの程度の需要があるかを推計することが重要である。これらを組み合わせて一連の移動手段と捉え、地域福祉交通という一つの枠組みの中で連携を図れるような供給サービスの計画策定が望まれる。
|