|
第2章 わが国における海洋管理のあり方
2−1 海洋管理とは何か
海洋管理は、21世紀におけるわが国の国家政策の最重要課題の一つとして取り扱っていかねばならない。この点は昨年度報告書でも述べたが、繰り返し強調しておきたい基本的考え方である。
領土すなわち国土については、国土利用計画が国家政策の最上位の一つとして位置付けられているのと同様に、沿岸域を含む「領海」ならびに「排他的経済水域」と「大陸棚(Continental Shelf)」についても、「国家政策の最重要課題の一つ」として取り扱うべきである。
したがって、海洋管理問題は、内閣総理大臣の施政方針演説に盛り込まれるべきレベルのものとして考えられねばならない。
海洋管理のそうした重要性は、わが国の経済・産業・社会のいずれの面においても海洋の果たすべき役割が極めて大きく重要だからである。それは、あらゆる資源、生産物のほとんどが海上輸送に依存しており、海洋は食糧資源の供給の場であり、国民のレクリエーションの場でもあることなどを考慮すれば、当然のことである。
他方、国際面からみても国連海洋法条約の定めるところにより、EEZおよび一定の条件下での大陸棚について主権的権利(sovereignty rights)と管轄権(jurisdiction)が及ぶが、同時に、義務としての環境管理もまた沿岸国の責任として課せられている。
こうした海洋管理の基本的考え方については、これが国家的政策課題であると同時に、国民一人一人も管理の一翼を担うものであり、政府と国民はともにco-managerであって、管理の権利と義務は海洋を利用する国民だれでもがその責任の一端を負うことを基本的考え方とする必要がある。たとえば、国・地方自治体が、産業界が、そして国民一人一人が海洋の環境管理についての主役である、ということが海洋管理の出発点である。
昨年度の報告書でも述べたが、海洋管理の対象海域は、第一に12海里(一部3海里)の『領海』で、面積は約43万平方キロメートルである。わが国の領土の面積は約38万平方キロメートルであるから、その1.13倍の面積である領海が領土と同一の国土として管理対象になる。「領土」および「領海」の上空部は「領空」となり、これらの空間は国の主権がそのまま適用される。
対象海域の第二はEEZで、その面積は領海部分を含めて約447万平方キロメートルと領土の約11.8倍におよび、しかもこの面積は世界で6番目の広さである。
対象海域の第三は、EEZの外側に国連海洋法条約の許す範囲で拡張が可能な「大陸棚」である( 昨年度報告書ならびに本報告書の第1章参照)。これらのEEZおよび大陸棚には、わが国の主権的権利と管轄権が及ぶ。 EEZの場合、領海の基線から200海里までの海洋空間、すなわち海面・海中・海底ならびに海底下のすべてが管理の対象範囲となる。したがって、EEZの範囲内にある生物資源、海底鉱物資源やエネルギーなどの非生物資源のすべて、現在利用されているものはもちろん将来利用されることになるものや、科学的調査活動を含むこれらの空間・領域の利用そのもの全てが管理の対象である。
ただし、船舶航行の自由や上空飛行の自由などが適用され、「公海」と同様の法的地位をも併せ持った性格を有する海域である。
大陸棚の場合は、EEZの場合と異なり海水部分は含まれず、海底および海底下のみが管理の対象となる。ただし、生物資源の中で海底に密着しているとみなされる底生生物、具体的には底魚(カレイ、ヒラメ等)や甲殻類(エビ、カニ等)などは管理の対象として認められている。
2−1−3 海洋管理および国土管理の一部としての沿岸域管理
上記のように、領土すなわち国土については「国土管理」、つまり国土利用計画が国家政策として取り組まれている。そして、国土の延長上に、水際線をまたいで海域部まで含む、いわゆる「沿岸域」とよばれる空間がある。河川等を通じた陸起源汚染の海域への流入防止や土砂の供給源という意味で“流域圏”の考え方を導入するのが望ましい海洋環境管理の場合、また、経済活動が展開される密度が濃く海域利用の競合問題が発生する場合、等々、「沿岸域管理」の重要性はきわめて高い。
しかし、沿岸域は陸域と海域のインターフェースの部分であり、独自の生態系を有しているため、それ自体で一つの管理政策を必要とする空間である。また、一般的に言って沿岸域の海側の範囲が領海の幅を超えることは考えにくい。
つまり、「沿岸域管理」は、「国土管理」の一部であると同時に「海洋管理」の一部をも構成するといえるが、これらとは個別の管理政策として取り組まれるべきものである。
また、管理主体の観点からは、沿岸域は国土と同様に、国と地方自治体の連携と役割分担が極めて重要であるのに対して、EEZならびに大陸棚は、国が管理すべき領域であることが大きな相違点として認識されねばならない。
したがって、本報告書ではこの沿岸域管理については必要な限りにおいて触れるにとどめ、基本的に海洋管理の対象空間を「EEZおよび大陸棚」とすることをご承知願いたい。
なお、本事業における海洋管理の対象を示した模式図を図2−1に示す。この図のうち、緑色の線より陸側の部分(地下・海底下も含む)が、わが国の主権がおよぶ領土・領海・領空であり、赤い線で区切られた領域(沿岸域に係る部分を除く)が、EEZおよび大陸棚として本事業の議論の対象となる。
| (拡大画像:356KB) |
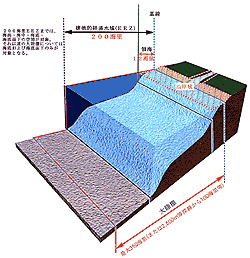 |
図2−1 排他的経済水域および大陸棚の範囲と本事業の検討対象
海洋管理のうえで重要な役割を果たすのが、わが国の領土であってEEZの起点を構成する遠隔離島の存在である。とりわけ、領有権問題を抱える北方四島、竹島、尖閣諸島、東シナ海と太平洋の境界に位置する南西諸島、太平洋のはるか沖合に点在する大東諸島、小笠原諸島・沖ノ鳥島・南鳥島の存在が大きい。
これらの遠隔離島は、基本的に行政区画としてはそれぞれ地方自治体のもとにあるので、前述の領土、領海ならびに沿岸域管理の関係がでてくるが、EEZならびに大陸棚の管理の上では、その周辺360度がEEZおよび大陸棚を構成するという特異な条件下にあるので、これら遠隔離島およびその周辺のEEZおよび大陸棚は、国が管理すべき性質のものである。
事実、沖ノ鳥島については、海岸法の改正により海岸の直轄管理制度が導入された。そして、わが国200海里水域の海洋管理ネットワークの構築においては、空間的なネットワークとその拠点形成という意味で、これらの遠隔離島の果たすべき役割は極めて大きい。
アメリカにおいては、米国海洋大気局(NOAA)の下部組織である海洋漁業局(NMFS)の太平洋諸島(PIR:Pacific Islands Region)支局をハワイのホノルルに新設することでEEZ管理、とりわけ水産資源と漁業活動の管理について即応体制を整えるに至った。従来は、本土西海岸にあるNMFSサウスウェスト支局の出先機関がホノルルに設置されていただけだが、2003年にEEZ管理の本格的取り組みのために組織を再編、これを支局に格上げしたものである。
このような海外の事例からも、遠隔離島の果たすべき役割が非常に大きいことが理解できよう。その点、わが国の遠隔離島の活用・振興は、取り組みが不十分であると言わざるを得ない。
海洋管理とは何か、その定義は様々あり単一の概念で説明することは困難である。しかし、その意味を理解する上で、昨年度報告書でも整理したように「管理」の英語表現が解釈を手助けしてくれる。
そこで、昨年度報告書で検討した海洋管理の概念を改めて整理すると次のようになる。このうち、新たに加えたもの、同列に格上げしたものはイタリック体で示す。
―control:security controlやpollution controlなどのフレーズで用いられ、強制力をもって行う管理。
―regulate:法律、基準、制度などを定めて規制を行う管理。
―law enforcement:法の実際の適用と執行を強調し、違反行為を取り締まることまでを含む管理。Control、Regulate、administrationにも通じる管理。
―policing:耳慣れない用語だが、administration and policingというように対で用いられることが多い。個別具体的“政策実行”あるいは“政策の適用”という意味での管理。
―stewardship:ocean stewardshipというフレーズで用いられる用語であって、執事としての役割ということから、海洋の管理は自然から付託されたものであることを意味し、そうした精神の下で行う管理。
―administration:法律、基準、制度はもちろんのこと、日常的な活動から非常時の活動まで幅広に行政実務を行う管理。実効的な意味での海洋管理という意味としては合理的な表現。
―governance:ocean governanceというフレーズでよく用いられる用語であって、administrationがその時点でのあるいはその政権の下での政策や法制度にもとづいて実務的に主権あるいは主権的権利や管轄権を行使していくイメージであるのに対し、governanceの方は国家的理念と思想の下に政策を積極的に策定し、必要に応じてそれを見直し、より良い管理に向けて主体的に取り組む(governする)姿勢が折り込まれた管理のイメージである。
―management:資源管理(resource management)、沿岸域管理(coastal zone management)あるいは環境管理(environment management)というフレーズで用いられるが、総合的取り組みを言い表す管理。
これらのいずれをも包括的に表現する用語として、やはりmanagementという用語が海洋管理に一番ふさわしいといえるが、他の表現の意味するところも海洋管理を考える上でさまざまな示唆を与えてくれる。
なお、海洋管理の理念として盛り込まれるべきコンセプトとして、昨年度報告書では以下の項目を掲げているが、ここではキーワードのみを改めて整理し再掲する。
―sustainable development
―common heritage of mankind
―sound and healthy environment
―wise use
―rational and responsible management
―scientific research promotion
―safety and disaster prevention
―international cooperation
―pre-cautionary approach
―co-existence
|