|
(2)海洋環境モニタリングネットワーク構想
平成9年11月に、当時の環境庁が組織した「海洋環境調査検討会」(座長:平野敏行トキワ松学園美術短期大学長〔当時〕)が、わが国における海洋環境の総合的な保全のために必要となる海洋環境モニタリングのあり方についてとりまとめた「海洋環境モニタリングネットワーク構想」を提言した。前項で触れた「海洋環境モニタリング指針」は、この提言内容をもとに策定されたものである。
当時、国内的・国際的に以下のような状況にあり、海洋環境モニタリングの必要性が叫ばれていたことが、同構想策定の背景にある。
平成6年12月:環境基本計画の閣議決定
平成8年7月:国連海洋法条約の発効
平成8年12月:経済構造の変革と創造のためのプログラムの閣議決定
(海洋環境に関する情報の整備)
平成9年1月:ナホトカ号油流出事故
同提言では、海洋環境モニタリングの基本的課題と保全上必要な個別の課題を整理しているが、特に基本的課題としてこれまでの水質基準に加え、EEZを対象とした環境保全の目標を明らかにし、この目標を達成するために必要な海洋環境モニタリングを実施すること」が掲げられている。
また、同提言には海洋環境モニタリングの対象水域について、日本近海を以下の3海域に区分し、それぞれにおいて重要な海域を選定するとした。
なお、同提言には、当時の関係省庁が実施する海洋環境モニタリングの調査対象をとりまとめた資料が掲載されており、参考として図1−17および図1−18に示す。
| (拡大画像:97KB) |
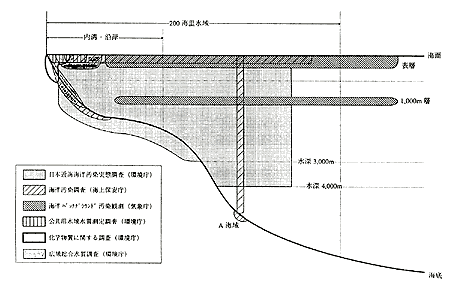 |
図1−17 主要な海洋環境モニタリング調査の鉛直的な範囲区分
出典:海洋環境モニタリング指針、環境省水質保全局、平成12年7月
| (拡大画像:487KB) |
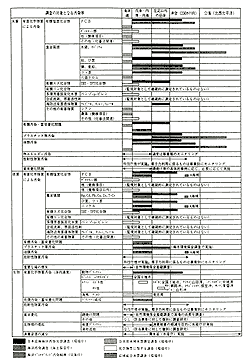 |
図1−18 主要な環境モニタリング調査の調査対象と海域
出典:同前
今回の調査では、内閣府や外務省、防衛庁などわが国のEEZ管理において重要な役割を担う省庁からの回答が得られなかったこともあり、十分な成果は得られなかったが、EEZ管理に係る関係省庁の施策を一定の範囲で把握できたことで一定の成果が得られたといえる。今後は、今回回答が得られなかった省庁に対して、本事業の意義を十分に説明しながら、引き続き協力を依頼して改めて情報の収集を図ることが重要である。
また、本報告書では、一部の省庁の情報が欠落していたために実現できなかったが、EEZ管理に係る施策別に、特定のケースを想定して(例えば、外国人漁船による違法操業、サハリンにおける石油・天然ガス開発にともなう冬季の油流出事故など)、準用される法令の確認や関係省庁の連絡体制や対応の手順の確認など、具体的なケーススタディを行い、わが国の海洋管理施策の現状と問題点をより詳細に把握することが必要であると考えられる。
特に防衛庁については、これまでわが国の海洋政策論議に参加することがほとんどなく、海洋開発分科会や海洋開発関係省庁連絡会議にも参画していないが、わが国のEEZ管理を実効性のあるものとするには同庁の参加・協力が不可欠である。したがって、今後も積極的に防衛庁へ協力を呼びかけ、まずは本事業のような海洋政策論議の場への参加を実現することが第一歩として重要である。
さらに、EEZ管理においては、国内だけではなく周辺国との協力や調整が不可欠であることから、外務省に対しても引き続き協力を呼びかけ、本事業に対する支援を得ることが重要である。
|