特定の病原体の有無を調べることもできるが、通常の検査にはより感度の高い指標菌として大腸菌を使う。大腸菌は通常、温血動物の腸に生息し、多量に排泄される。こうしたバクテリアが検出された水は、ふん便に汚染されていることを意味し、危険性が高い。
31. 通常、水中の大腸菌の数は水100ml中の個数で表される。以下は目安である。
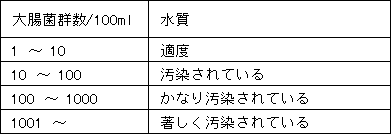
32. 水が塩素殺菌されている場合は、バクテリアよりも遊離塩素の含有量を調べるほうが簡単で適切である。配水所で0.2mg/l〜0.5mg/lの遊離塩素が検出されたら、バクテリアはほぼ確実に死滅し、ふん便などの有機物によって水がひどく汚染されていないことを意味する。
33. 水は当然、配水所だけでなく、家庭で飲んだり使用したり時も安全な必要がある。水が実際に使われるまで安全に保つためには、家庭の衛生や環境衛生対策が重要で、貯水槽やタンク車の水も定期的に検査する。
34. 飲用水が不足している場合は、飲用に適さない水や、塩分を含む水を洗い物に使う。
◆即時対応
◆ 最低限の水量さえも地元の水源から確保できない場合は、難民を移動させる。
◆ すべての水源において排泄物による汚染を防止する措置を速やかに実施する(詳細は第17章参照)。
◆ 水が不足している場合は、水源の汚染を防止し、公平さを保証する配水システムをつくる。
35. 長期的に使用される給水システムを開発している間、または難民を適当な用地に移動させるまでの間、短期的な緊急措置が必要な場合がある。現地で確保できる水量が難民の最低必要量に満たない場合は、トラックで水を運び込む手配をする。
36. それが不可能な場合は、速やかに難民を移動させる。ただし、入手できる水量で初期の最低必要量なら満たせる場合も少なくない。その場合は水質が当面の問題となる。
37. 難民が利用するのは地表水、場合によっては地下水(井戸や湧き水)である。通常は水質に関係なく、一番近くにある水が利用される。水源が何であれ、排泄物による汚染を防止する措置を速やかに実施する。
すぐにとるべき措置は、組織的な対策が最良の策となる可能性が高い。
38. 難民コミュニティのリーダーとコミュニティ全体の組織化を図り、既存の水源の可能性と危険性を難民に認識させる。また、水源を排泄物による汚染から守るという考えを広める。水源が流水の場合、上流に取水所を設ける。次に洗濯場所を決め、最下流に居住地がくるようにして、家畜にもそこで水を飲ませる(図2参照)。必要に応じて河岸を柵で仕切るとともに、は虫類など水中に危険がないか注意する。
39. 水源が井戸や湧き水の場合は、水源を柵で囲み、覆いをかけて管理する。
水源の汚染を防ぐため、難民が各自の容器で水を汲み上げるのを禁止する。