|
CHAPTER 4章 産業化する北洋鮭鱒漁
◆サケ商品の開発と市場開拓
カムチャッカ漁場からの漁獲高は年々増加し、ロシア領鮭鱒漁は大きく発展した。新潟の堤商会はサケ缶詰の製造を成功させ、商品の販路を海外市場に求めた。堤商会は本拠を新潟から函館へ移し、生産体制の整備と流通の拡充に力を注いでいった。一方、生産設備の大規模化・借区料の増加のため、中小規模の漁業家には漁区経営が困難な状況となりつつあった。サケの大量漁獲が価格の下落を生み、その打開には従来の流通と市場の再編・拡大が必要であった。業界では、企業合同による大資本化への動きが加速していった。
管轄漁場・漁場沿岸の大要・漁場地理の大要
|
市立函館博物館 昭和6(1931)年 旧堤商会が中心となって合併した日魯漁業は、昭和6年には合計133漁区を管轄する一大勢力になっていた。翌昭和7年には、個人漁業家の漁業権をも含めた露領漁業大合同が行われ、日魯はほとんどの漁区を入手することになる。
|
◆堤商会のサケ缶製造
明治43(1910)年、堤清六はサケの缶詰の製造を開始した。日本人による缶詰製造は、明治10(1877)年の北海道開拓使による缶詰試験所の開設に始まり、何度か試みられていた。しかし、製缶技術と経営方針の不足から事業の成功に至ることはなかった。堤は缶詰の原料として、大量の漁獲があったベニザケ・ギンザケだけを用い、イギリスを販売先として海外市場を開拓する方針を立てた。大正2(1913)年にはアメリカから最新の自動製缶缶詰機械を導入するとともに、機械の操作を指導する技師も雇い入れ、経営・技術の両面において本格的な缶詰生産事業を開始した。
鮭缶の製造工程
|
(拡大画面:26KB)
|
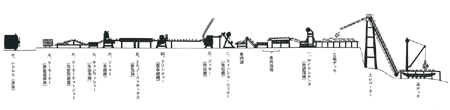 |
|
『日魯の現況』昭和12(1937)年 当館蔵 より転載(一部改変)
|
|