|
3)船舶航行管理システム
船舶の航行安全や危機管理の強化を目的として導入が進められているAISでは、旅客船や大型商船(300トン以上の外航船および500トン以上の内航船)に搭載が義務付けられているが、EEZを航行する小型船の安全確保のため、さらには、わが国のEEZ内で活動する外国人漁船や外国海洋調査船等の動向を把握するための船舶航行管理システムを構築する。
これを実現するためには、AIS陸上局の増設・機能強化を図るのに加え、AISの搭載義務を漁船やプレジャーボート等の小型船にも拡大することが必要となる。
(2)基幹システム
本稿で検討する海洋モニタリングネットワークでは、わが国周辺海域に海底ケーブルを張り巡らせ、これに海底ステーションや各種のブイシステム等を接続し、さらに、船舶や人工衛星、航空機、陸上局等を組み合わせたシステムを、基幹システムとして採用する。
なお、システムの諸元や機器のスペック等の詳細検討は別の機会に譲り、ここでは、システムの概略検討を行なう。
1)ネットワークシステムの参考事例
システムの中心となる海底ケーブルシステムについては、東京大学地震研究所や海洋科学技術センターが中心となって取り組んだ「VENUS」計画や、アメリカ西海岸のシアトル沖で整備が進む「NEPTUNE」計画などを参考にする。また、船舶やブイ、AUV等を組み合わせる複合システムとしての要素については、アメリカ東海岸のニュージャージー州沖で展開されている「LEO-15」などを参考にする。
(1)VENUS・ARENA
運用を停止した沖縄−グアム間の第二太平洋横断海底ケーブル(TPC-2)を再利用して、多目的地球観測システムを構築することを目的とした実験的なプロジェクトで、以下の開発が行われるとともに、これらの技術を利用して貴重なデータが収集された。
○観測機器の開発:広帯域地震計、ハイドロフォンアレイなどの開発
○水中接続技術の開発:水中着脱コネクタ、ROV等による接続技術などの開発
なお、現在はわが国のプレート境界域に海底ケーブルを張り巡らせて海洋・海底に関する総合的な研究を行う「ARENA」計画が進行中である。図3−1は、IEEE Oceanic Engineering Society Japan Chapterで検討された海底ケーブルの概念設計の結果であるが、このうち、釧路沖と室戸沖には既に海洋科学技術センターによりケーブルシステムが設置され、海底地震計やハイドロフォン、CTD、ADCP等による観測が行われている。
図3−1 ARENA計画における海底ケーブルの想定ルート
出典:科学観測用海底ケーブルネットワーク技術報告書、
IEEE ic Engineering Society Japan Chapter,2003年1月
(2)NEPTUNE
アメリカとカナダの共同プロジェクトとして推進されているNEPTUNEは、ワシントン大学、ウッズホール海洋研究所、NASA Jet Propulsion Laboratory(JPL)、モントレー湾水族館研究所(MBARI)、Institute for Pacific Ocean Science and Technology(IPOST)、Victoria大学等が参加しており、100億円規模のプロジェクトである。
このシステムは、北アメリカ太平洋沿岸のCascadia沈み込み帯(北アメリカプレートの下にJuan de FucaプレートとGordaプレートが沈み込んでいる)の海底に光海底ケーブルを張り巡らせ、地殻変動やその他海洋科学研究等に利用することを目的としており、ケーブルの総延長は3,000kmにおよぶ。同システムから得られるデータは、科学研究に活用されるほか、アウトリーチの一環として、インターネットを通じて学校や関係機関に配信され、新たな海洋研究、水産資源評価、海産哺乳類の研究などに活用することを想定している。NEPTUNEのシステムイメージを図3−2および図3−3に示す。
| (拡大画像:558KB) |
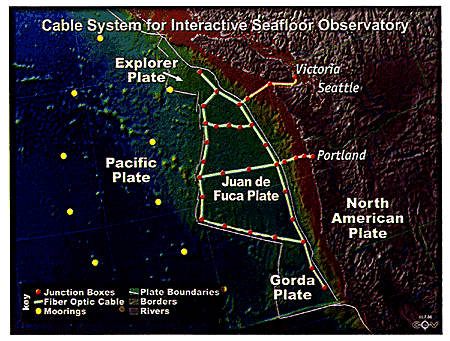 |
図3−2 NEPTUNEの全体構成
| (拡大画像:505KB) |
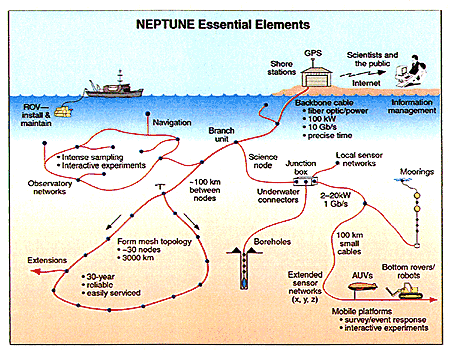 |
図3−3 NEPTUNEのシステムイメージ
出典:同前
|