|
1−3−9 海上保安庁
海上保安庁は、海上における国民の生命・財産を保護し、法律の違反を予防・捜査および鎮圧するために国土交通省の外局として設置されており、以下の4項目を戦略的な目標と定め、巡視船や航空機等によりわが国周辺海域の警備・監視活動等行っている。
(1)治安の維持
(2)海上交通の安全確保
(3)海難の救助
(4)海上防災・海洋環境の保全
各施策の詳細については、最新版の海上保安レポートを参照していただきたいが、ここでは、特に以下の項目についてその概要を紹介する。
(1)領海および周辺海域における警備・監視活動
1)密航・密輸対策
○中国・韓国・ロシアとの連携強化(覚書の締結、連絡窓口の設置)
○国際刑事課、国際組織犯罪対策基地の設置
2)領海警備等
○尖閣諸島を巡る対応(巡視船・航空機による哨戒、関係省庁との連携)
○外国海洋調査船に対する対応(巡視船・航空機による監視等)
3)外国人漁業の取締り
○外国漁船データベースの構築、捕捉用資機材の開発・整備
○水産庁等関係機関との連絡協議会等の開催による連携強化
4)その他の重点事項
○不審船・工作船対策
・海上保安法の改正
・防衛庁との共同対処マニュアル作成
・内閣官房・防衛庁・海上保安庁間での早期の不審船・工作船情報の共有化
・不審船・工作船取締りにおける運用面・法制面の検討
・巡視艇・航空機の不審船・工作船追跡能力の強化
○テロ対策
・国際テロ警備本部の設置等
(2)海洋測量・調査業務
海上保安庁では、本庁の測量船5隻(拓洋、昭洋、明洋、天洋、海洋)を中心に、各管区本部の測量船、巡視船、航空機等が連携して、わが国が管轄権を有する海域において、大陸棚調査や自然災害に備えた調査、海洋環境保全に係る調査等の海洋測量・調査を実施している。
1)大陸棚調査
1−2−8で紹介した大陸棚調査には、海上保安庁の測量船が従事しており、現在までに国土面積の約1.7倍にあたる約65万平方キロメートルの海域について、大陸棚延長の可能性があることが判明している。図1−10に大陸棚が延長できる可能性のある海域を示す。
今後は、国連の科学的・技術的ガイドラインの内容に基づいて、従来行ってきた概査に加えて以下の調査を実施することになっている。
○精密地殻構造判定調査
○精密海底地形調査等の精査
| (拡大画像:674KB) |
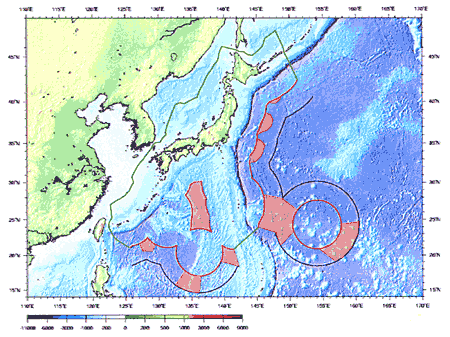 |
図1−10 新たにわが国の大陸棚とできる可能性がある海域(オレンジ色の部分)
出典:海上保安庁提供資料
2)自然災害に備えた調査
わが国はプレート境界域に位置することから、海底地震や海底火山活動などにより様々な自然災害が発生する恐れがあり、この発生予測発生時の状況把握のため以下の調査を行っている。
○海底地殻変動観測等の地震調査研究
○海底火山活動監視調査等の海底火山調査研究
3)海洋環境保全に係る調査
海洋環境を保全するため、測量船および巡視船に「船舶観測データ集積・伝送装置」を整備し、海流、水温等の観測データをリアルタイムで収集しているほか、人工衛星による漂流ブイの追跡観測および可視・赤外線画像解析ならびに内外の関係調査機関とのデータ交換を実施し、海洋速報、海流推測図等の形で広く一般に提供している。
○海洋汚染調査
海洋の汚染状況を把握する観点から、石油、PCB、重金属等の調査を実施しており、その対象海域は以下のとおりである。
・わが国周辺海域
・閉鎖性の高い海域(湾内等)
・海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律第10条第2項第4号により海洋投入処分が認められる海域(A海域)
○西太平洋海域共同調査(WESTPAC)
太平洋沿岸国19カ国が参加して1979年に開始されたWESTPACでは、同庁がモニタリング調査を行うとともに、責任国立海洋データセンター(RNODC)として、同調査から得られるデータの元的管理を、海洋情報部内に設置されている日本海洋データセンター(JODC)が行っている。
○黒潮変動観測
測量船、巡視船および航空機等による海流、水温等の定期的な観測および全国7ヶ所にある験潮所データにより、海流通報に必要なデータを収集している。
(1)海洋気象観測
海上の船舶にとって航行の安全と経済的な運行のためには、海洋気象情報は不可欠なものであり、気象庁においては、以下に示す方法で海洋気象データの収集に取り組んでいる。
1)海洋気象観測船等による観測の実施
わが国では、本庁および海洋気象台に配備される5隻(凌風丸、啓風丸、高風丸、長風丸、清風丸)の海洋気象観測船により、西太平洋および日本周辺海域における海洋観測と海上気象観測を行っているほか、商船や漁船などの協力を得て、気象・水温・海流などの観測データも収集して利用している。
特に、気象業務法第7条において、「船舶安全法第4条の規定により無線電信を施設することを要する船舶」は、WMO技術基準に沿った形で気象観測の実施および通報が義務付けられている。
なお、参考として図1−11に気象庁海洋海象観測船の主要な観測ラインを示す。
2)人工衛星による海洋観測の実施
気象衛星「ひまわり(5号)」や米国海洋大気庁(NOAA)の「ノア」の観測データをもとに、西太平洋の海面水温やオホーツク海の海氷分布を求めている。
ただし、「ひまわり」の代替衛星であった運輸多目的衛星「MTSAT」をつんだH2ロケットの打ち上げ失敗により、「ひまわり」は設計寿命を大きく越えた状態で運用を続けていた。現在は「ひまわり」のバックアップとして米国の静止気象衛星「GOES-9」を用いて観測を行っている。平成15年冬には、後継機である運輸多目的衛星新1号(MTSAT-1R)が打ち上げられる予定である。
また、海洋観測衛星「Jason-1」(アメリカとフランスの共同運用)による海面高度分布データから、黒潮や暖・冷水渦の位置や強さを算出している。
3)ブイ等による海洋観測の実施
海洋気象ブイロボット(漂流ブイ)による気圧、波浪、水温などの自動観測を行っているほか、関係省庁と連携して「ARGO計画」を推進しており、同庁はあるVフローとの投入やアルゴフロートから人工衛星(ARGOS)経由で送信されるデータをリアルタイムに収集・解析・提供を行う「全球海洋データ解析・提供システム」の運用等を担当している。
| (拡大画像:439KB) |
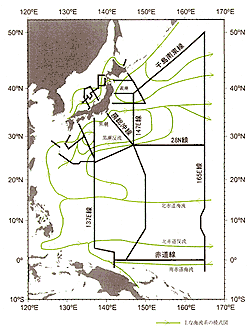 |
図1−11 海洋気象観測船による主要な観測ライン
出典:気象庁提供資料
4)その他の観測
上記のほか、海洋気象観測に関連する業務として以下の項日について取り組んでいる。
○沿岸防災観測
高潮や高波、地震による津波などによる災害を未然に防ぐため、全国77か所の検潮所などで潮位変化の監視等を行っている。また、船舶の安全航行や沿岸施設の安全管理、および海洋における事故防止のため、全国11ヶ所の沿岸波浪計により波高・周期の常時観測を行っている。
○オホーツク海沿岸における海氷観測の実施
防衛庁および海上保安庁の協力を得て航空機などにより海氷観測を行っている。
○南鳥島における観測
わが国最東端に位置する南鳥島において、地上気象、高層気象、津波、大気バックグラウンド汚染、オゾン観測等を実施している。
○北東アジア地域海洋観測システム(NEAR−GOOS)
わが国では、気象庁がNEAR−GOOS地域リアルタイムデータベースの管理を実施している。
(2)海の予報・警報
(1)の海洋気象観測データ等をもとに、海上の気象予報・警報、海面水温予報、海流予報、波浪予報・警報などを発表している。海上気象は、主に以下の2つのカテゴリーに分けて情報が提供されている。
(1)全般海上予報区
昭和55年より、国際水路機関(IHO)の提唱で国際海事機関(IMO)の決議により運用が開始された世界航行警報システム(NAVAREA航行警報)で、インマルサットEGCシステム8により情報を提供している。わが国は、11区域(北太平洋区域)の区画調整国となっている(業務は海上保安庁が担当)。
(2)地方海上予報区
日本近海を12の海域に区分し、それぞれの海域において地方海上予報・警報、情報を国際・日本語ナブテックス9により提供している。
(3)地震・津波の監視
わが国およびその周辺で地震が発生した場合、震源の位置やマグニチュードなどの各地の震度などの地震情報を気象庁が発表する。さらに、震源が海底にあり津波が発生するおそれがある場合には、津波予報(津波警報や津波注意報)を発表する。また、外国の地震による津波に関しては、ホノルルにある太平洋津波警報センター(PTWC)との連携により津波予報を行っている。気象庁が取り組んでいる海底地震・津波観測は、以下のとおりである。
○海底地震計(海底ケーブル式・自己浮上式)による海底地震観測の実施
○関係機関から送信される海底地震計データの処理
阪神・淡路大震災の教訓から制定された「地震防災対策特別措置法」により、海底地震の観測を行っている海洋科学技術センター・東京大学地震研究所・防災科学技術研究所等からデータの提供を受け、同庁が一括して処理している。
○南鳥島における遠地津波観測
○アメリカ・ロシアとの潮位データの交換による津波監視
8 Enhances Group Call:高機能グループ呼び出しによる自動放送(英語の自動印字方式)
9 世界的に統一された航行警報であるナブテックス(NAVTEX航行警報)は、各国が沿岸約300海里内において、航行の安全のために緊急に必要とする情報を自動印字方式により船舶に提供するもの。
|