|
1−3−6 農林水産省(水産庁)
(1)水産基本法の制定
従来の水産行政は、生産者重視の傾向が強いという批判があったが、消費者にも配慮した政策に転換するために、平成13年の通常国会で水産基本法が制定された。同法制定の背景として以下の点があげられている。
(1)新たな国際秩序の導入、定着
国連海洋法条約の下で自国の200海里水域の資源の持続的利用を基本に、漁業の発展を図っていくことが求められている。
(2)漁業生産の減少と自給率の低下
国内漁業生産を基本とした水産物の供給体制の構築が求められている。
(3)漁業者の減少と高齢化
国民に対する水産物の安定供給のため、意欲のある担い手の確保、育成とその経営発展を可能とする条件整備が求められている。
同法の概要は以下のとおりである。
1)基本理念
(1)水産物の安定供給の確保
○良質な水産物の合理的価格での安定供給
○国連海洋法条約の的確な実施を旨とした水産資源の適切な保存および管理と、水産動植物の増殖および養殖の推進
○水産資源の持続的利用と、国内漁業生産の増大を基本とする輸入の適切な組合せ
(2)水産業の健全な発展
○効率的かつ安定的な漁業経営の育成、漁業・水産加工業・水産流通業の連携および漁港、漁場その他の基盤整備による水産業の健全な発展
○生活環境の整備その他福祉の向上による漁村の振興
2)水産基本計画
施策の総合的かつ計画的な推進を図るため水産基本計画を策定する
3)水産物の安定供給の確保に関する施策
(1)排他的経済水域等における水産資源の適切な保存及び管理
(2)水産資源に関する調査及び研究
(3)水産動植物の増殖及び養殖の推進
(4)水産動植物の生育環境の保全及び改善
(5)排他的経済水域等以外の水域における漁場の維持及び開発
(6)水産物の輸出入に関する措置
(7)国際協力の推進
4)水産業の健全な発展に関する施策
(1)効率的かつ安定的な漁業経営の育成
(2)漁場の利用の合理化の促進
(3)人材の育成及び確保
(4)災害による損失の補てん等
(5)水産加工業及び水産流通業の健全な発展
(6)水産業の基盤の整備
(7)技術の開発及び普及
(8)女性の参画の促進
(9)高齢者の活動の促進
(10)漁村の総合的な振興
(11)都市と漁村の交流等
(12)多面的機能に関する施策の充実
なお、水産基本法の制定に伴い、以下の示す関係法の改正も行われている。
(1)漁業法
(2)海洋生物資源の保存及び管理に関する法律
○我が国周辺水域の資源回復の計画的・総合的な推進
・「漁獲努力量管理制度(TAE制度)」の創設
従来のTAC制度(漁獲量の総量管理)に加え、漁獲努力量(操業日数等の漁ろう作業量)の総量管理制度(※あかがれい、さわら、とらふぐ等を想定)を創設。
・TAC制度の暦年方式の見直し
一律に暦年方式になっている同制度について、資源の種類ごとにその漁業時期を考慮した方式に改める。
(3)漁船法
(4)漁港漁場整備法(旧漁港法)
(2)水産基本計画に基づく水産政策
前項の水産基本法に基づき平成14年3月に策定された水産基本計画は、以下の4つの柱で構成されている。
1)水産に関する施策の基本的な方針
2)水産物の自給率の目標
3)水産に関し総合的かつ計画的に講ずべき施策
4)水産に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
2)の「自給率の目標」では、漁業生産および水産物消費の面における課題が解決された場合に実現可能な漁業生産量および消費量の水準を、それぞれ「持続的生産目標」と「望ましい水産物消費の姿」として明示し、これらを踏まえ10年後の平成24年における「水産物の自給率目標」として設定している。
また、3)において水産物の安定供給の確保に関する施策として示された中で、EEZの管理にかかわりの深い事項を以下に示す。
○EEZにおける水産資源の適切な保存および管理
TACおよびTAEの設定・管理、外国人漁業・遊漁の管理、資源回復計画の推進と漁業経営への影響の緩和等
○EEZ以外の水域における水産資源の適切な保存および管理
国際漁業管理や便宜置籍漁船の廃絶のための貢献等
○水産資源に関する調査および研究
資源調査の拡充および制度の向上、国際資源調査への貢献等
○EEZ等以外の水域における漁場の維持および開発
わが国への漁獲割当の確保、入漁国への協力、水産資源の開発調査等
○国際協力の推進
開発途上国における水産業の振興に関する技術協力・資金協力、資源管理の分野における多国間協力等
なお、わが国の水産資源管理制度の根幹をなすTACおよびTAE制度については、水産庁ホームページ( http://www.jfa.go.jp/)に掲載されており、各方面においてもレビューされているので、本報告書での解説は割愛する。
(3)情報整備事業
TAC・TAE制度を的確に運用するためには、漁獲データにとどまらず広く海洋データを収集・管理することが不可欠であるが、わが国においては、水産庁の外郭団体である社団法人漁業情報サービスセンターが中心となり、漁獲データの管理、漁海況予報の発信等の情報整備を行っている。以下に、代表的な情報関連事業を示す。
1)漁況海況情報事業
調査船・漁船・商船・フェリー・航空機・人工衛星等による観測データや漁船の操業状況のデータを、漁業無線局・各県水産試験研究機関・水産研究所や各地の調査員を通じて収集し、これらのデータを処理・解析し、漁況海況情報・短期予測・長期予測結果の広報などを、迅速にFAXやインターネットなどで漁業者や関係機関に提供するシステムである。以下に、漁況海況情報事業の特徴を記す。
・収集された水温データは即日処理(表層・50・100・200の各層等温線図を作成)され、翌日には無線ファックス、インターネット等で配信される。
・漁船のシステム使用は無料。ただし、各都道府県が会員となり会費収入を得ている。
・水温以外のデータもあわせて収集し、データベース化している。
・TACおよびTAEの資源量推定に利用する漁獲データの集計とデータベース化も行っている。
| (拡大画像:507KB) |
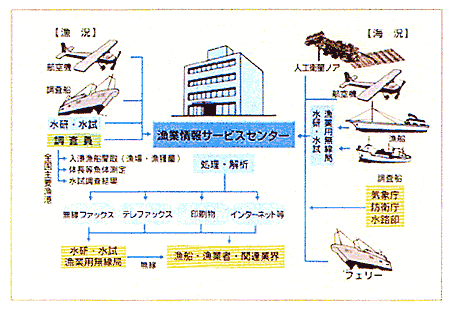 |
図1−5 漁況海況予報におけるデータの流れ
出典:漁業情報サービスセンターパンフレット
2)わが国周辺漁業資源調査情報処理システム
(FRESCO:Fishery Resource Conservation)
主要魚種の資源評価を迅速にかつ適正に行うための中核となるデータベースおよびデータ解析システムで、平成7年度に国が構築したシステムである。国・県の水産試験研究機関および漁業情報サービスセンターが参加して全国ネットワークシステムを構成しており、各自治体が「資源評価調査」で得られたデータを入力・転送し、漁業情報サービスセンターが運用管理している。当初のFRESCO1は、体長測定データや漁場分布調査結果などの生物情報が主体であったが、平成11年度運用が開始されたFRESCO2では、海洋観測データも含まれている。なお、水産資源の管理に資するデータ交換を目的に構築されたため、一般への公開はされていない。
| (拡大画像:86KB) |
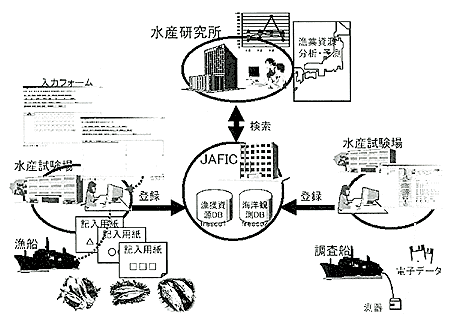 |
図1−6 FRESCOにおけるデータの流れ
出典:資源評価情報システム、雑誌FUJITSU2002−1月号
|