|
1−3−3 総務省
(1)海洋関連の技術開発
1)高度海上交通システムの実現のための研究開発
陸上分野に比較してIT化の進展が格段に遅れている海上分野において、海上通信に適した技術の研究開発を行うとともに、これらの技術の活用による海上通信の高度化方策について調査研究を実施している。具体的には、海上通信のデジタル化、陸上局のネットワーク化などが検討されている。
2)亜熱帯地球環境計画技術の研究開発
地球規模の気候変動に大きく寄与する地球循環機構や大気海洋相互作用のメカニズムを解明するために有効な電波を利用した地上設置型リモートセンシング技術の研究開発を行っている。この中で、海流ベクトル・波浪の2次元分布を観測する遠距離海洋レーダー(Long-range Ocean Radar)の開発が進められており、現在、石垣島と与那国島に設置した2台のレーダーと海上に設置した大型の海洋観測ブイ「COMPASS」を組み合わせて海流の観測を行っている。
また、この研究開発を行っている独立行政法人通信総合研究所沖縄亜熱帯計測技術センターでは、同研究から得られる海洋観測データのほか、気象観測データ、降雨データ等を自動的に収集・集積・配信する亜熱帯環境計測ネットワーク・データシステムを運用している。
| (拡大画像:181KB) |
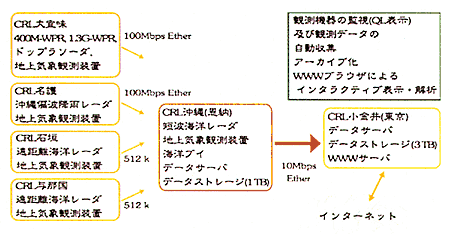 |
図1−4 亜熱帯環境計測ネットワーク・データシステムの概要
出典:通信総合研究所沖縄亜熱帯計測技術センターホームページ
3)高分解能三次元マイクロ波映像レーダーの研究
全天候で昼夜の区別なく地上を映像として把握する航空機搭載レーダーシステムを開発しているが、このレーダーシステムを用いた各種応用分野への実験観測を通して、技術の実証と応用のための処理技術等の開発を行っている。平成9年度から同レーダーの試験観測を開始し、国内の大学・研究機関等と共同で各種分野における応用を目指した観測および解析手法の開発を進めており、海洋への応用としては、波浪、海流、渦等の海洋現象のほか、油汚染や流氷等の環境把握への応用が図られている。
外務省については回答が得られなかったため、同省ホームページおよび関係資料などをもとにとりまとめた。
(1)漁業問題
外交活動を担当する外務省と漁業行政を担当する水産庁が協力して(水産物の輸出入に関しては経済産業省や財務省、衛生基準に関しては厚生労働省などとも協力)諸外国との漁業問題に取り組んでいる。
1)二国間の漁業問題
○主に当該国との二国間関係を担当する局課が担当する。一方、普遍性と一貫性に対する観点から、経済局漁業室や条約局等が協力を行っている。
2)多数国間の漁業問題
○漁業に関する国際機関や条約については、主に経済局漁業室が担当しつつ、二国間関係に対する観点から、主要関係国との二国間関係を担当する局課等が協力を行っている。
○漁業以外の問題を含め広範な問題を扱う国際機関や条約(例:WTO、国連海洋法条約、ワシントン条約)において漁業に関する議論がなされる場合には、主に当該国際機関等を担当する局課(例:国際機関第一課、海洋室、地球環境課)が担当しつつ、普遍性と一貫性に対する観点から経済局漁業室や条約局等が、二国間関係に対する観点から、主要関係国との二国間関係を担当する局課等がそれぞれ協力を行っている。
(2)海洋調査
国連海洋法条約では、沿岸国がEEZの管轄権として海洋科学調査を規制・許可・実施する権利を持つことが定められており、外国の調査船がEEZ内で海洋科学調査を行うには、沿岸国の同意が必要である。他方、他国または国際機関が平和的かつ全人類の利益のため海洋環境の科学的知識を増進させる目的で行う海洋科学調査について、沿岸国は同意を与える義務を負う。
同省のホームページに海洋調査に関する記述はないが、文部科学省の回答に関連する情報として以下の事項が含まれていた。
○外国がわが国のEEZ内における海洋調査を申請する場合、あるいはわが国の海洋調査船が他国のEEZ内で海洋調査を申請する場合については、外務省がその窓口となり、関係省庁への関連事項の問い合わせ、あるいは他国への申請を行う。
なお、防衛庁と同様、文部科学省のホームページ上で公開されている海洋開発分科会第2回海洋研究・基盤整備委員会の議事録には、EEZ内において行われる海洋調査に関する議論についての記録があり、おおむね以下のような内容であった。
○他国からの申請の場合、手続きに不備がなければ外務省が窓口となって受け付け、各省庁に問題の有無を問い合わせる。
○関係省庁から申請内容に関する不審な点(例えば、使用機材にボーリング機器、エアガンなどが記載されていた場合)について指摘があった場合、申請国に押し返す場合もある。
○他国のEEZにおけるわが国の海洋調査については、過去に116件の申請を行っている。(平成13年11月7日の会合開催時)
○海洋科学技術センターの場合、おおよそ2〜3年に一度の割合で拒否されるケースがあった。特に、中国とロシアは対応が厳しい。ロシアの場合、ロシアの研究者を招聘して同乗させていてもうまくいかない場合もある。一方で、アメリカ、オーストラリア、フランス等はあまり問題ない。
○科学者レベルで他国と覚書をとりかわしても、地方政府や中央政府、あるいは政党で見解が異なり、調査時に拒絶されるケースもある。海洋調査の場合、Give and Takeの側面が強い。
○国内法の未整備、あるいは他国の国内法との整合性の問題がある。(かつて、日ソ科学協力協定のもとで調査を行おうとした際、EEZの境界線を越える段階でわが国の海上自衛隊と海上保安庁に止められたケースがある。外務省に確認はとれたが、最終的に現場の任務として境界線を越えることが認められなかった。)
|