|
3.4 疲労寿命解析入門
従来からの船体構造設計における疲労寿命の評価は、「マイナー則に準じて”累積疲労被害度”を求める」アプローチで行われている。おおまかには、一定の応力変動を繰返した疲労試験より得られる変動応力Sと疲労寿命(限界繰返回数)Nの関係を表す”S−N線図”に基づいて、変動応力Sがn回繰返した時の累積疲労被害度(D.F.)をn/Nと定義し、異なった振幅の変動応力が作用した場合の累積疲労被害度は各変動応力による累積疲労被害度の和とみなすものである。即ち、D.F. =n1/N1+n2/N2+n3/N3+・・・
変動応力が一定である場合に、n i=N iすなわちD.F.=1.0の時点で疲労損傷が生じるのは当然であるが、異なった変動応力が組合わさった場合でもD.F.=1.0となった時に疲労損傷が生じると仮定する (修正マイナー則;図1参照)。 通常、単純小型で手軽な”溶接継手試験片”を用いた疲労試験によって得られた種々のS−N線図を援用した累積疲労被害度計算が一般的であるが、本来は評価の対象となる”構造体”と同一条件下にある実寸模型による疲労試験データが必要である。さらに注意すべきは、D.F.=1.0となった時点で構造物がどの様な”状態”になっているかは、疲労試験に於いてどの様な状態をもって”疲労損傷発生”と定義したかに依存する点である。言い換えると、疲労損傷の定義によって異なったS−N線図が得られる。不統一な「疲労損傷発生」の定義と不明確な「実構造との対応」は、精度限界と混乱の要因となっている。
図9 ”疲労損傷”の定義によって異なるS−N線図
現実の船体構造の疲労損傷事例においても、溶接部で発見された2〜3mm程度の”微細な亀裂”から部材を横断する様に数mにも達する”大きな亀裂”まで、「疲労損傷(亀裂)発生」と一括して称するものの発見時点に応じてサイズと状態は様々である。また、疲労損傷による被害の程度についても、数十mmの亀裂であっても隔壁板厚を貫通して油の漏洩を生じ社会的に重大な問題となる場合もあれば、見開き写真(5)のストラット基部における疲労亀裂事例の様に(悪例ではあるが)数mの亀裂に至っても発見時点まで特に問題を引き起こす事なく、補修されて終わる場合もある。
一方、先進的な「疲労亀裂伝播解析に基づく寿命の評価」アプローチでは、製造時点における潜在的で検知/完全除去が不可能な微細きず(初期亀裂)を想定し、その微細亀裂が応力の繰返しによって成長(伝播)して行く状態を刻々シミュレーションする。また、亀裂の最終的な状態(危険疲労亀裂寸法)を明確に定義し、その状態に達した時点を疲労寿命と定義するので、合理的である。最終的な危険疲労亀裂寸法は、その亀裂によって生じる強度上あるいは機能上の事象と明確に関連付ける事により、例えば以下の様に定義される。
・ 外板あるいは隔壁を貫通する事によって液体貨物が漏洩/海水が侵入する状態
・ 部材が破断する等、所定の強度を喪失する/隣接部材の連鎖的損傷を早期に招く状態
| (拡大画像:4KB) |
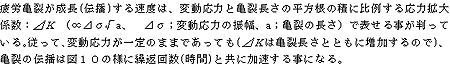 |
図10 疲労亀裂の成長(伝播)特性・・・一定振幅の変動応力が作用する場合
これに伴い、(船舶の様に)作用する変動応力の振幅が一定でなく変化する(ランダムに近い)場合だと、疲労亀裂伝播の様子は順序の影響を受ける事になる。例えば、極端ながらトータルとしては同じ作用回数/頻度分布となる変動応力の作用順序を図11の様に恣意的に変えた場合、疲労亀裂伝播の様子は図12の様になり、疲労亀裂が板厚を貫通する(亀裂深さが板厚に達する)までの繰返回数(時間)には約2倍の差が生じる事が判る。
同一パターンの変動応力が作用した場合の、従来型の修正マイナー則による累積疲労被害度の計算値を図13に示す。累積疲労被害度は、作用順序が異なっても繰返回数(経過時間)が同じとなる時点で一致する事、即ち作用順序(履歴)の影響を受けない事を示している。従来の疲労寿命の評価アプローチでは、上述した「不明確な疲労損傷状態の定義」と相侯って、ランダムに遭遇する変動応力順序(荷重履歴)に起因する疲労亀裂寸法の”ゆらぎ”を把握できないという問題点も指摘される。就航直後の1年間と経年後の廃船時期に近い1年間とを、同じリスク期間として捉えるアプローチであり、合理的で無い側面がある。
漸減型:変動振幅が漸減(Down)する繰返しパターン(変動の総繰返回数は同一)
漸増型:変動振幅が漸増(Up)する繰返しパターン(変動の総繰返回数は同一)
図11 トータルとしては同頻度分布ながら変動応力の作用順序が異なるパターンの事例
図12 変動応力の作用順序に依存する疲労亀裂伝播のゆらぎ(注:2D、2Uは低発生確率)
図13 変動応力の作用順序を変えた場合の従来型修正マイナー則による累積疲労被害度
以上で示した様に、先進的な「疲労亀裂伝播解析に基づく疲労寿命の評価」アプローチでは、”疲労亀裂寸法”という実現象と直接結びついた量を疲労損傷の尺度としている事から、従来型アプローチに比較して、以下の様なメリットを有する。
|