|
1. 研究の背景
荷主/船主/運航管理会杜では近年、特に「船舶の安全性」への要求気運が高まっている。船体構造の疲労(亀裂)損傷撲滅は関連する重要課題のひとつである。この様な社会的ニーズを受けて、船級協会には疲労強度の観点からの各種要求及び「○○年疲労設計」といったノーテーション導入の動きがありまた、船主/造船所間では新造船契約時に長寿命設計の仕様織り込みの動きも見られる。これに対し現実には、疲労損傷は就航後のごく初期には発生せず、また突発的な異常海象遭遇の結果というよりは個船毎の長期的な就航履歴/荷重遭遇累積に依存する現象なので、精密な予見には未だ技術的困難を伴う状況にある。且つ、板厚貫通にまで成長(伝播)した場合には漏油等をもたらす(海洋汚染and/or不稼働損等を招く)ので社会的/経済的影響は重大であるが、疲労損傷は一般的に局部的で微細なので検知にも困難があるのが実態である。
従来、船舶の構造疲労設計では統計的遭遇荷重予測及び累積疲労被害度を指標にするMiner(マイナー)則に準じた疲労寿命評価アプローチが採られてきた。実績ある類似構造との相対比較には便利であり安全性向上に一定の貢献を果たしてきたが、個々の船舶が特有の航路で遭遇する荷重の相違は考慮されない。また、本来連続的な事象を不連続的に表現する等、物理的な曖昧さがあり、新規構造の疲労寿命絶対値評価などに際しては適用限界が指摘されている。ランダムな荷重履歴を受けた既存構造の疲労損傷解析にあたっても説明がつかず矛盾をきたす場合も多々あり、また、一旦疲労亀裂が発見された段階での余寿命の評価(亀裂伝播推定:補修実施デッドライン特定)には向かないなど、問題点も多い。
| (拡大画像:165KB) |
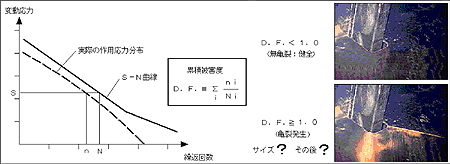 |
図1 累積疲労被害度(D.F.:ダメージファクター)による「クロ・シロ」評価イメージ
図2 疲労亀裂の連続的な成長(伝播)イメージ・・・実際の現象
一方、航空機・車両や原子力等の発電プラント産業では、個々の構造に関する不可避な「製造時微細きず(初期亀裂)」の存在前提(認知)及び「亀裂の成長(伝播)」に対応する「残存強度」評価の観点からの、「危険疲労亀裂寸法(補修要否判定基準)」の定義並びに、モニタリングと定期検査とによる実働荷重計測/亀裂検知体制とを組合せた、「構造疲労(寿命)制御・安全性管理スキーム」が指向されて久しい。
比較的に荷重履歴が単純で予見が相対的に容易と考えられるこれらの産業でも、事故の撲滅に至ってはおらず技術的に不完全であるのは昨今の事故例からも明らかであるが、実用的レベルには一応達している。そこで本研究では、船舶の疲労設計に先進的な「疲労亀裂伝播に基づく構造安全性管理」のアプローチを導入するにあたって、必須となる基盤技術を整備すると共に、保守点検と組合せた運用法のイメージアップを図り、安全性向上面で如何なる貢献が期待され得るのかについてのビジョンを示すものとした。
原子力発電所設備の検査・維持について
保安院、原発の安全確保へ新規制導入(日本経済新聞2002/09/25)
経済産業省原子力安全・保安院は24日、原子力発電所のトラブル隠しを防止する新しい制度を固めた。運転中の原発に小さな傷があっても安全上問題がなければ使い続けられる「維持基準」を設け、抜き打ち検査の実施など検査制度を改める。関連法を改正し2003年度にも実施に移す。
原子力安全・保安院は同日開いた原子力安全規制法制検討小委員会に、新制度の素案を提示した。これまで新品同様の品質を求めていた原発の部品に維持基準を新たに設けるほか、(1)抜き打ちで立ち入り検査をする(2)電力会社による自主的な点検を国が監査する――などの点検制度の改革を盛り込んだ。原発には高い安全性が必要で、運転中の原発に対しても新品の基準が求められてきた。しかし部品の多くは長期間使用しているとひび割れなどが生じやすい。原発がある米仏などには維持基準があり、ないのは日本だけだった。
| (拡大画像:292KB) |
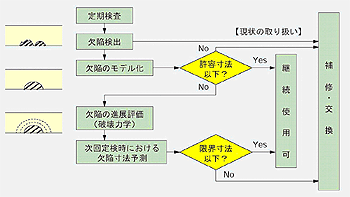 |
図3 原子力発電所設備の現行・改訂「保守・維持」アプローチ(電中研ニュース336)
1990年代に海洋汚染防止の見地から、タンカー構造の二重殻化が義務づけられたが、載貨重量20〜30万トン級の二重殻超大型タンカー(ダブルハルVLCC)は約10年以前に建造/運行が開始されたばかりであり、就航・経年実績が確認されるのはこれからである。一方、衝突・座礁事故などの極限状態に於ける船舶の安全性向上のみならず、経年構造部材の疲労損傷から漏油を引き起こす様な(敢えて例えれば)平常時にも発生し得る事故の防止も重要である。この考えに則り実施した本研究では、ダブルハルVLCCを具体的な対象として選定した上で、「疲労寿命」管理に関連する各種技術の全般的な高度化を図り、「ライフサイクルに亘る構造安全性の合理的な向上に寄与する事」を目的とした。
|