|
第4章 データベースの基本設計
4.1 検索項目の抽出・検討
データベースの基本設計を行うため、まず、最初にオンライン表示システムの基本的な方針及び機能について以下に提示する。
(1)システムの運用方法
オンライン表示システムの基本的な運用方針としては、以下を考えている。
| (1) |
システムは、インターネット上で公開する。 |
| (2) |
システムは、属性情報及び観測データのデータベースを持つものとし、収集した観測データは、JODC及びMIRCのデータベースに収録する。 |
| (3) |
日本海の環境変動に関する統計解析を行い、その結果より作成した図表をシステム上で公開する。 |
| (4) |
システムのユーザーとしては、研究者、行政機関などのある程度、専門的な分野に関わる人々を想定する。 |
(2)システムの機能
オンライン表示システムの機能としては、以下のような項目を考えている。
(1)観測情報の検索
日本海で行われた観測情報のうち、以下の項目について情報の検索を行えるようにする。その流れを図化したものを図4.1に示した。
1)観測プロジェクトの検索、インフォメーション
・観測プロジェクトのインフォメーションの表示
・実施期間からの観測プロジェクトの検索
・実施海域からの観測プロジェクトの検索
2)観測情報の検索
・プロジェクト別の観測情報の検索
・期間からの観測情報の検索
・観測実施機関からの観測情報の検索
・観測海域
・データ項目からの観測情報の検索
3)データ所在情報の表示
・観測情報の検索に伴うデータ所在情報の表示(所在情報)
(2)観測データの検索・抽出
本研究で収集した日本海の観測データについて、データの検索及び抽出を行えるようにする。また、観測データはインベントリー情報と関連付けを行い、観測情報の検索結果から参照できるようにする。
(3)日本海の環境変動のインフォメーション
収集したデータから統計解析を行い、ユーザーに海洋環境情報を提供できるような図化データ等を作成し、公開する。この内容の詳細は平成16年度の研究において決定する。
(3)検索項目
(2)に示したシステムの機能を踏まえて、データベースにおける検索項目を整理すると以下のとおりとなる。
(1)観測プロジェクトのインフォメーションに関する情報
1)プロジェクト名
2)実施期間
3)実施海域
(2)観測情報及び観測データ
1)航海期間又は観測期間
2)観測海域または観測位置
3)実施機関(実施国含む)
4)プロジェクト名
5)データ項目
| (拡大画面:174KB) |
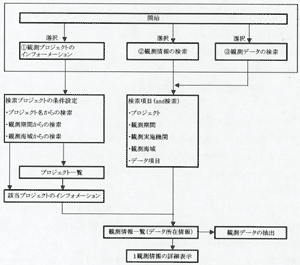 |
図4.1 日本海の海洋観測情報検索のイメージ
4.2 データベースの基本設計
本研究では次の3種類のデータベースを作成するものとする。
(1)観測プロジェクトのインフォメーションのデータベース
(2)観測インベントリー情報のデータベース
(3)観測データのデータベース
データベース構築にあたっての基本的な方針を以下に示す。
(1)データベースの収録項目について
第3章で抽出・付加した属性情報項目の中には、それほどデータベースに記載する必要がないと思われる項目も含まれているが、基本的には全項目についてデータベース化する。(1)(2)のデータに関してデータベース化する項目を表4.1にまとめた。
(1)の観測プロジェクトのインフォメーションに関しては、 表3.5に例示したように各項目に関しての情報をデータベース化する。一方、(2)の観測情報のインベントリー情報に関しては、 表3.1に示した属性情報に準拠してデータベース化する。表中に○印で示した項目は、検索キーとなる項目である。 また、観測データのデータベースについては、原則としてJODCのデータベースのフォーマット(FETI)に準じた項目を収録するものとする。
(2)観測位置情報について
観測インベントリーの情報のうち観測位置に関する情報としては、観測位置図の有無、係留・海底設置機器及び漂流システム等の観測(投入)位置などがある。また、この他に位置の概要を示す項目としては、「調査海域」「特定海域」「調査範囲(MSQによる)」などの項目がある。観測情報のデータベースにおいては、こうした位置情報は重要であるので、上記のいずれかの項目を複合的に用いてユーザーに調査範囲を絞り込むための情報を提供するような仕組みを作る必要があろう。
なお、観測研究プロジェクト及び官庁の定期観測などのように観測位置が決定されているもの、あるいは、CSRなどに測点図が記載されているものについては、できるだけ測点図のファイル化(画像ファイル等)を行い、データベースに付加していくものとする。
(3)データのコード化について
観測インベントリー情報のデータベースの作成にあたっては、JODCで既にコード化されている項目(船舶コード、機関コードなど)については、共通のコードを用いてコード化するものとする。この時、原データ(実際の船名、機関名など)も残すかどうか、あるいは、コード化されていない項目を新たにコード化するかどうかなどについては、来年度に詳細検討することとする。
(4)観測データベースの作成及びインベントリー情報との関連付けについて
本研究で収集された観測データ群から、日本海の海洋観測データを抽出して観測データベースを作成する。データベース化に際しては、船名、位置、観測期間などをキーとして、インベントリー情報と観測データとを関連付けられるように構築する。
| 表4.1 |
観測プロジェクト及びインベントリー情報のデータベースにおける収録予定項目一覧 |
| 項目 |
|
内容 |
検索項目 |
備考 |
| (1)観測プロジェクトのインフォメーション |
プロジェクト番号 |
整理番号 |
|
|
| プロジェクト名 |
|
○ |
|
| 略称 |
|
|
|
| 実施国 |
そのプロジェクトに関わる参加国 |
|
|
| 日本海の実施国(機関) |
日本海における観測実施国と観測機関 |
|
|
| 実施期間 |
プロジェクトの実施期間 |
○ |
|
| 実施内容 |
観測分野の概要 |
|
|
| プロジェクト概要 |
プロジェクトの背景 |
|
|
| データ所在情報 |
関連機関によりデータ所在が明確な時 |
|
|
| 観測海域 |
観測海域、または観測位置図 |
○ |
別途作成した観測測点図ファイル名 |
| (2)観測インベントリー情報 |
整理番号 |
データ照合番号 |
|
観測データファイルとの照合 |
| 照会番号 |
CSR情報のJODCにおける照会番号 |
|
|
| 船名 |
データを収集した船舶のフルネーム |
○ |
|
| 船種 |
データを収集した船舶の種類 |
|
|
| 航海番号 |
航海の固有番号、名称または略称 |
|
|
| 航海期間 |
出港日と入港日 |
○ |
|
| 出港地 |
出港した港の名称 |
|
|
| 帰港地 |
帰港した港の名称 |
|
|
| 担当機関 |
航海の観測計画を作成した調査機関の名称 |
○ |
|
| 観測責任者 |
航海中観測を担当した者(観測班長)の名前と所属機関 |
|
|
| 調査海域 |
航海中にデータを収集した海洋または海域の名称 |
○ |
左記の情報を統合し、観測海域の情報を提供 |
| 特定海域 |
調査が或る海域の特定区域に集中した場合、その区域のローカルな海域名、海底地名、または地理座標 |
○ |
|
| 調査範囲 |
MSQの海域番号図による |
○ |
|
| 交換制限 |
データ交換に制限がある(Yes)か、否(No)か条件付き(In Part)かを示す |
|
|
| プロジェクト名称 |
航海が共同プロジェクト(または調査、計画)の一部であるならばその名称 |
○ |
|
| 調整機関名 |
上記プロジェクトの調整機関名 |
|
|
| 航海の目的と簡単な報告内容 |
収集されたデータを有効利用に供するための、航海の日的と性格についての情報 |
|
|
| データタイプ |
データリストのコード(表3.2参照) |
○ |
|
| データ数 |
収集されたデータの量、または推定量 |
|
数量の情報提供 |
| 情報源 |
インベントリー情報の情報源 |
|
観測情報の収集先または報告書名 |
| 測点図の有無 |
情報源における測点図の有無 |
|
|
| 観測位置 |
係留、海底設置機器および漂流システム等の観測(投入)地点の経緯度 |
○ |
|
| データ所在情報 |
データ保管機関またはデータ所有者(機関)の情報 |
|
|
| 観測国 |
観測機関が所属する国名 |
|
|
|
| 観測測点図のファイル |
プロジェクト別、定線観測などの位置情報 |
|
別途作成した観測測点図ファイル名 |
|
| 注: |
○印は、データベースから情報検索を行う際のキー項目を示す。 |
|