|
5)燃料こし器(フェーエルフィルタ)
燃料こし器は燃料に含まれている水分やごみなどを取り除くもので、ガソリンエンジンでは2・142図示すようにガラス製のカップとその中に目の細かい金網又はプラスチック製の網、ろ紙、フェルト等のろ材を入れたものと、2・143図に示すようにろ紙とケースを一体にしたカートリッジ式のものがあり、一般にカートリッジ式のものが多く使われている。
ディーゼルエンジンの機付き燃料こし器としては燃料ポンプの前に設けられており、燃料ポンプのプランジャや、噴射弁などの寿命に大きな影響を及ぼす重要な装置であり、機関によっていろいろなものが用いられており、一般的に、メッシュの細かなノッチワイヤ式やろ紙式が使用されている。又小形機関には、フエルト式やビニールスポンジ式のものが用いられており、大形では複式として運転中でも片方ずつ、こし器の掃除が出来る構造としている。
(1)ろ紙、フエルト、スポンジ式こし器
こし器内部に使用しているエレメントの材質により各種のものがあり、ろ紙式はろ紙を折り曲げて筒状にして濾過面積を大きくしている。目の粗さはろ紙式が10ミクロン又小形機関に多く使用されるフエルト式やビニールスポンジ式は40ミクロン程度である。一般にエレメントのみ交換できるようになっているが、最近は図2・143図に示すようなカートリッジタイプのものも多く使用されている。
| (拡大画面:52KB) |
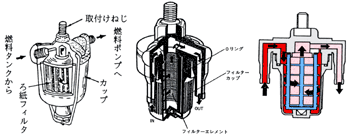 |
2・142図 フューエルフィルタ
| (拡大画面:67KB) |
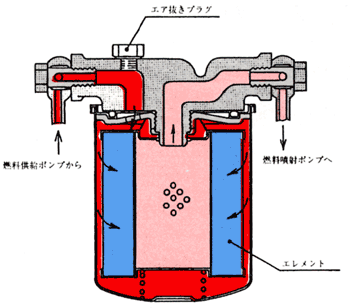 |
2・143図 カートリッジ式こし器
| (拡大画面:84KB) |
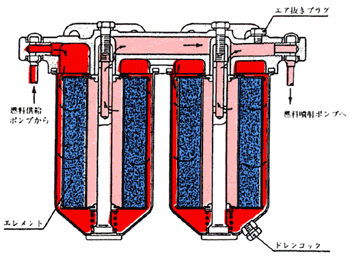 |
2・144図 ろ紙式こし器
2・145図 ろ紙の形状
(2)ノッチワイヤ式こし器
2・146図に示すような構造の40〜50ミクロン程度のこし器で、目詰まりした時にはエレメントを取り出し洗い油に浸した後圧縮空気を吹き付けて清掃する。中大形機関では複式となっており、ブローオフなどもあり、運転中でも片側ずつ清掃できるようになっている。
2・146図 ノッチワイヤ式こし器
6)キャブレータ(気化器)
キャブレータは燃料を微粒化して空気と混合させて気化しやすい状態にすると共に、エンジンの運転状態に応じて適切な混合気を作るもので2・147図にキャブレータの一例を示す。
| (拡大画面:77KB) |
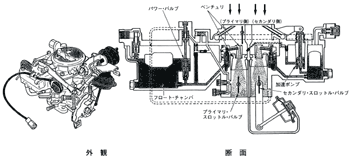 |
2・147図 キャブレータ
キャブレータの原理は「霧吹き」の原理を応用している。霧吹きは2・148図に示すように送風管から空気を吹き込むと、先端の細く絞られた部分で空気の流れが速くなり、この部分の圧力が低下して負圧状態になる。水の表面は大気圧で押されているので吸い上げ管の先端が負圧になると水は吸い上げられて、送風管から吹き出す空気と激しくあたって霧になり噴出する。キャブレータには2・149図に示すようなベンチュリ(細く絞ってある部分)及びノズルが組み込まれており、エンジンの吸入負圧によって吸い込まれた空気は、通路に設けられたベンチュリ部で空気の流れが速くなり、これによって発生する負圧によって、ベンチュリ部に設けられたノズルから表面を大気圧で押されているガソリンが吸い出され、空気と混ざり合って霧状となり、エンジンに吸い込まれる。
2・148図
2・149図
キャブレータの主な役割をまとめると次の通りである。
(1)燃料の微粒化
ガソリンを出来るだけ粒の細かい霧状にし、空気と均質な混合気を作る。
(2)適切な混合比の混合気を作る。
エンジンの状態に適応した濃度の混合気を作る。
(3)出力に応じた量の混合気を作る。
燃焼室へ供給する混合気の量を増減し、エンジン出力を制御する。
以上3つの役割をスロットル操作とエンジンの吸気作用(吸入負圧)で自動的に行っている。
(混合比について)
ガソリンが完全燃焼するための理論的な空気とガソリンの質量比を理論混合比(空燃比)といい、理論混合比は約15(空気):1(ガソリン)であるが、実際のエンジンでは運転状態によりいろいろな混合比が要求される。なお、不完全燃焼でも混合比が8:1から20:1の範囲なら、電気点火で燃焼させることが出来る。最近では、燃焼室内に強力なガス流動を発生させて燃焼期間の短縮を行い、24:1のような希薄域でも安定した燃焼を行わせる方法がある。
エンジンの出力は測定してみると2・150図に示すようにスロットルバルブ開度に関係なく、混合比が12〜13:1の時に最も大きな出力を得ることが出来る。この混合比を出力混合比という。また同様に燃料消費率が最も少ないときの混合比は16〜18:1くらいで、これを経済混合比という。エンジンの回転速度が変わっても、これらの混合比は殆ど変化していないので実際のエンジン運転状態における混合比は次のような範囲になる。
| ・始動時(冷機時) |
2〜3:1(チョーク使用) |
| ・始動時(暖機時) |
7〜8:1 |
| ・アイドリング(トローリング) |
8〜10:1 |
| ・低速運転 |
10〜12:1 |
| ・中速運転(通常航走運転) |
15〜17:1(経済混合比) |
| ・高速・高負荷運転 |
12〜13:1(出力混合比) |
2・150図 混合比と出力・燃費の関係
キャブレータの主要部はベンチュリ、ノズル、フロート室、チョークバルブ、スロットルバルブなどで構成されており、また、キャブレータの種類は非常に多く、形状は複雑である。本体は亜鉛合金又はアルミ合金のダイキャスト製である。ここではキャブレータをフロート系統、スロー系統、メーン系統、パワー系統、加速系統及び始動系統に分けて説明する。
(1)フロート系統
フロート系統はフューエルポンプから送られてきた燃料を蓄え、燃料がノズルから吸い出しやすく、しかも過不足なく適量を供給できるように、常に油面を一定の高さに保つためのもので、2・151図のようにフロート、フロートチャンバ、ニードルバルブ、エアベントチューブなどで構成されている。
2・151図 フロート系統
2・152図 ニードルバルブ
フロートは耐油性ゴムの発泡体又はナイロン成型のものが用いられている。
ニードルバルブは2・152図のようにバルブ、バルブシート、プッシュピンなどで構成されており、バルブとプッシュピンの間にはフロートが振動した場合でもバルブとシートの密着を確保し、オーバフローを防止するためにスプリングが挿入してある。
エアベントチューブはフロートチャンバ内の圧力とチョークバルブ上方の圧力を等しくするために双方を細い管で結び、エアクリーナが詰まったときなどに混合気が濃くなるのを防ぐ働きをしている。
燃料の油面の高さが変化すると、ベンチュリを流れる空気の速さが同じでもメーンノズルなどから吸い出される燃料の量が変わるので、混合比が変化し、エンジンの負荷に応じた適切な混合気が作られなくなるため油面の高さの安定が必要である。
|