|
第2章 エンジン及び船外機の構造・機能と整備
1. 分解整備について
1.1 整備工事の準備
分解整備の殆どは故障修理であるが、その他に船舶安全法に基づく中間検査、定期検査、臨時検査、或いはメーカの保証ドック、操業前の点検整備等がある。
検査対象船以外でも、メーカの取扱説明書等に基づき、点検時間になった機関は、点検整備を実施することが、船舶の安全航行に重要な事である。
整備を実施するに際しては、依頼する側も、依頼される側も、双方で「ピストン抜きをする」とか、「シリンダライナを交換する」など具体的に工事仕様書を作成して、事前に周知徹底することが大切である。口頭のみの約束では往々にして誤解が生じてトラブルのもとになる。又、部品の手配も事前に出来るので、工事を計画通り進めることが出来る。
工事仕様書には、次のようなことを記載する。なお、機関の整備来歴があれば交換部品などの予測が出来るので記載するよう徹底すべきである。
(1)注文主、連絡先、
(2)船名、機関形式(メーカ名、回転数、シリンダ径等)
(3)工事期間(着手日、完成予定日)
(4)工事内容(整備範囲並びに予測される交換部品など)
(5)検査の種類(JG中検、定検等)
1.2 分解時の注意
エンジンの分解にあたっては、細心の注意を払い入念に行わなければならない。分解の仕方が悪ければ部品を破損させたり、紛失させたりして組立が出来なくなり、作業が計画通り進まず、時間の空費となる。
分解前に、機関の整備マニュアル、取扱説明書を読んでおき、適正な工具を使用し、正しい手順と適切な方法により分解すると共に、分解した部品は整理整頓しておく細心の注意が必要である。
又分解した部品は、汚れの状況、カーボンの付着状況を、写真又はノートに記録しておく。特に分解中に破損個所や不具合箇所を発見した場合は、その都度客先と打ち合わせを行い、整備方針をはっきりさせ、後日トラブルが起きないよう注意せねばならない。
なお、分解に際しては、下記のような注意が必要である。
(1)メーカの整備マニュアル、取扱説明書に従って適正な工具を使用して分解する。
(2)相手部品とのなじみが重要な部品には、合わせ番号を付けて、組み合わせが変わらないようにする。
(3)向きの判らなくなるような部品には、分解の際組立方向が判るような記号、合いマークを付けるとともに、組立時に迷わないようノートなどに記録しておく。
(4)摺動部分等に合いマークを付ける時は、マーカなどを使用し、けがき針等傷の付くものは使用しない。
(5)ボルト類は同じ径でも、長さの違うものが多くあり、組立の際探すのに時間を要すので、出来る限り分解した後のネジ穴にねじ込んでおくか、ノートに長さと使用箇所を記入しておく。
(6)電気配線を外す時には、接続されている端子番号や符号を線に付けておく。
(7)破損部品や、不具合部品はすぐ廃棄しないで、原因調査がすむまで保存しておく。
(8)オイルシールや、研磨面には傷を付けないよう注意して分解する。
(9)はめ合いが固くて抜けない時には、無理に叩かず適正な工具を使用して分解する。
(10)分解した部品は、部分毎に分類整理しておく。
(11)ボルトやナットは、太さ、長さ別又は使用部分別に分類し仕分け箱に入れて保管する。
1.3 分解整備工具
分解に必要な標準工具は、通常エンジン出荷時メーカより供給されるが、専用工具などは整備業者で準備するのが一般的である。下記に整備でよく使用される工具と使用上の注意事項を記す。
1)一般工具
(1)スパナ
ボルトやナットを締め付けたり、ゆるめたりするもので種類としては、両口スパナ、片口スパナ、片目片口スパナなどがある。スパナのサイズは口径と呼ばれる寸法で表し、ボルト頭部の二面幅を示している。
(使用上の注意)
・ボルトの頭やナットに正しく合うものを使用する。
・締めるときも、緩めるときも身体に引き寄せる方向に力をかける。
・柄の部分を長くして使ったり、ハンマ等で柄を叩いて使ってはいけない。
2・1図 スパナの種類
2・2図 スパナのサイズ
| (拡大画面:13KB) |
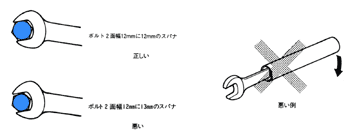 |
2・3図 スパナの使い方
| (拡大画面:12KB) |
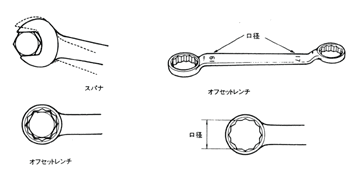 |
2・4図 メガネレンチ
(3)ソケットレンチ(ボックスレンチ)
窪んだ場所のボルトやナットを締めたり緩めたりするときに使用する。また、ラチェットハンドルと組み合わせてスピードのある作業が出来る。
サイズは口径で表し、種類としては、下記のように分けられる。
・口径部の角の数により6角12角
・口径部の長さにより普通型、ディープ型
・差込角のサイズによって、6.35mm(1/4)9.5mm(3/8)12.7mm(1/2)19.0mm(3/4)25.4mm(1/1)
2・5図 ソケットレンチ
| (拡大画面:12KB) |
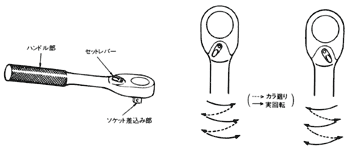 |
2・6図 ラチェットハンドル
(2)スピンナハンドル
ソケット差込部の取り付け穴が2・7図のようになっておりレバーの角度によってボルトやナットを強く締めたり速く締めたりすることが出来る。
2・7図 スピンナハンドル
(3)スライディングハンドル
ハンドルが軸方向に滑るため、ハンドル腕の長さを変えることが出来、回転力を加減することが出来る。
2・8図 スライディングハンドル
(4)スピーダハンドル
手早い作業をするときに使うクランク状のハンドル。
2・9図 スピーダハンドル
| (拡大画面:8KB) |
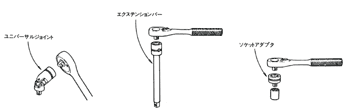 |
2・10図 ソケットレンチ用補助具
(5)T形レンチ
ソケットとT形のハンドルが一体となったもので、手早い作業が出来る。
2・11図 T形レンチ
(6)T形フレックスレンチ
T形レンチのソケットの首の部分にユニバーサルジョイントが組み込まれているもので、斜め方向からでも作業が手早く出来る。
2・12図 T形フレックスレンチ
(7)モンキレンチ(アジャストレンチ)
口径が変えられるスパナ状のレンチで、変わった寸法のボルト、ナットに対して使われる。顎の部分がスライドするのでガタが多少あり、規格化されたボルト、ナットには使用しないこと。
使用するときは、調整ネジで口径をきっちり合わせ、隙間のない状態で使用する。
なお、使う向きがあるので注意する。
2・13図 モンキレンチ
|