(13)長崎
| 会場: |
長崎県総合福祉センター |
| 日時: |
平成13年6月23日(土)午前10時〜17時 |
| 来場者: |
68人 |
| 相談ボランティア: |
2名 |
| 受入機関: |
4団体 |
| 概要: |
長崎で不登校といえば、テレビ長崎の「夜間高校」が大変有名である。今は廃校になった市校(長崎市立高等学校定時制)での不登校生の様子をドキュメンタリービデオに取った当時のディレクターが山本氏・教頭だったのが溝部氏・PTA会長で不登校の親だったのが田中氏であった。この超有名なお三方にお集まりいただき、相談ボランティア2人を加えたシンポジウムは熱気に溢れ参加者も多く、相談会もその熱気をそのまま引き継いだような形で終了時刻の5時を過ぎてもまだ相談が続いていた程だった。 |
[1]「不登校生の進路と社会参加」シンポジウム
| 期日: |
平成13年6月23日(土) |
| 会場: |
長崎県総合福祉センター |
| パネラー: |
テレビ長崎 製作部長 山本 正興 氏 |
| |
元長崎市立長崎高校 PTA会長 田中 悠二郎 氏 |
| |
元長崎市立長崎高校 教頭 溝部 政英 氏 |
| |
相談ボランティア 松枝 希美 氏 |
| |
相談ボランティア 隈元 祐輔 氏 |
| 司会: |
社団法人 日本青少年育成協会 専務理事 近藤 正隆 |
討議内容:
溝部:現在は県教育センターで、いじめ・不登校・LD児などの相談にのっている。親子ホットラインという電話相談も行っている。当時は市校を不登校生の居場所にするつもりで対応していた。市校は定時制のみの高校だったので生徒が自分を受け入れ、信じられる人が必ずいることを目指した。互いの存在を認められる人がいる。そういう人を見つけ出すことが大切だと思う。
田中:自分も高校中退、子供ができてから市校に行った。高校を卒業したのは34歳のときだった。自分の子は3人とも不登校。PTA会長の子が学校に行かないということで、かなり辛かった。子供を待つのが一番辛かったが、今では本人がアルバイトで授業料まで出せるように成長してくれた。
山本:テレビ取材を通して「不登校の人に自信を持ってほしい」と伝えたかった。不登校の人は素晴しい能力を持った子が多い。人の気持ちが分かる子が多い。他人の悩む気持ちが理解できる人は、この現代には貴重な存在だと思う。当時自己評価の低い子がいて叱った。その子は素直にお礼が言える子だった。力づけられて就職も決まった。悩める人には能力がある。親は子を信頼してほしい。
松枝:家庭環境が複雑で、父を知らない。母親とも中学生になってからやっと一緒に暮らせるようになった。物でなく、母親の愛情がほしかった。母と生活できるようになって、自分を大切にするようになった。中3頃立ち直り、短大を出て、現在専門学校で昼は事務、夜は講師をしている。
隈元:自分に限界を感じて自分の殻に閉じこもった。自分を持っている人に憧れ、何もない自分に失望し不登校になった、父は3才の時に死亡している。家にひきこもると時間を持て余し、やがて「今のままではいけない」と思って16歳でアルバイトを始めたが、又ひきこもった。人と付き合うのがうまくなかった。職場で泣いてしまった。すると先輩が五木寛之の「生きるヒント」をくれた。宗教的な考え方だったが、「唯我独尊」が気に入り、全5巻を読んだ。それ以来本を読むようになり、今も本屋さんでアルバイトをしている。自分を受け入れることができたことで自信がついた。人と比べることは意味がないので、「自分は自分」という考えで生きていきたい。悩んでいる人の相談にのることで、もう一度自分を見つめ直したい。
松枝:今悩んでいる人には「自分のことが好きですか」と問い、他人と比べるのではなく、自分を見直し好きなことに打ち込んでほしい。
隈元:今日一日を有意義に生きてほしい。親も自分自身を大切にしてほしい。そうすれば他人も我が子も大切にし、認められるようになる。
溝部:認めるけれども譲れないこともある。たとえば単位をとらなければ昇級ができないし、卒業もできない。これは本人の努力しかない。
田中:当時仕事の世話をした生徒もいたが、長続きしない子が多かった。その点も努力しかない。親も我が子を他人と同じように客観的に人間として認めるようにしたい。

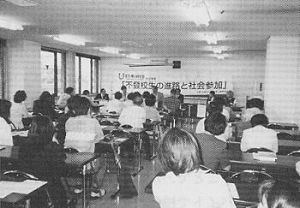
[3]相談会
あまり広い会場でない上に大勢の相談者が来たので、整理券を発行し外で待ってもらうような形になった。福岡から北九州支部の相談員5名と広谷チーフアドバイザー、相談ボランティアの二人が大活躍で、5時を過ぎても頑張って相談にのってくれた。素晴しい催しだった。
溝部先生から市校がない今、県立佐世保高校と県立成滝高校が定時制通信制高校として不登校を受け入れており、入試でも学科試験は課していないという情報が、紹介されたことも付け加えておく。