2.24 A2;§3.3.5.3.1 1フレーム後の通常運用
2.24.1 提案する明確化の文言
分間が経過し終えた時に、最初の送信が割り当てを終えられており、通常の運用が開始されるべきである。
2.24.2 明確化の根拠
A2;§3.3.5.1.1 「VHFデータ回線(VDL)の監視」についての明確化の根拠を参照すること。
2.24.3 修正の日付: 2001年10月
2.24.4 所見
なし
2.25 A2;§3.3.5.3.2 オフセットをゼロに設定する
2.25.1 提案する明確化の文言
1フレーム後に全ての割り当てが既に行われてしまっている時は、オフセットが最後の送信の中でゼロに設定され、それ以上の割り当ては行われないことを表示すべきである。
2.25.2 明確化の根拠
当該節は、見出しが述べていることを説明していない。明確化が必要である。現在の記事は、§3.3.5.3.4にある情報と同じである。
2.25.3 修正の日付: 2001年10月
2.25.4 所見
なし
2.26 A2;§3.3.5.3.4 この送信にオフセットを追加する
2.26.1 提案する明確化の文言
最初のフレーム段階における送信は、全て、ITDMAアクセス体系を使用すべきである。この構造には、現在の送信から、送信が発生することになっている次のスロットまでのオフセットを含んでいる。この送信は、また、保持フラグ(keep flag)も設定するので、受信局は占有されているスロットをもうーつ別のフレームに割り当てることになる。
2.26.2 明確化の根拠
A2;§3.3.5.1.1「VHFデータ回線(VDL)の監視」についての明確化の根拠を参照すること。
2.26.3 修正の日付: 2001年10月
2.26.4 所見
なし
2.27 A2;§3.3.6 指定運用
2.27.1 提案する明確化の文言
移動局が転換域の外に居り転換域に入ろうとしていない場合は、自律的な局は、基地局を経由して、通報16「指定モードの命令」により、担当機関が定めている特定の送信計画に従って運用するように命令されることができる。船舶に搭載されている等級A移動局は、指定モードで運用している時は、その全ての位置通報の送信について、通報1に代えて、通報2の「位置報告」を使用すべきである。船舶に搭載されている等級B移動局及びSAR航空機局は、指定モードで運用している時は、その指定モードフラグを指定モードで運用している局に設定すべきである。指定モードは、当該局の位置報告の送信にのみ影響を及ぼすべきであり、それ以外の局の動きは、何も影響を受けるべきではない。船舶に搭載されている等級A移動局以外の移動局については、この位置報告の送信は、単に、通報16によって指示された通りに行なわれるべきであり、当該局は、針路及び速度を変更しても報告率は変更すべきではない。船舶に搭載されている等級A移動体用AIS局については、自律モードが通報16によって指示されている報告率よりも高い報告率を必要としている場合を除き、同じ規則が適用されるべきである。自律モードが通報16によって指示されている報告率よりも高い報告率を必要としている場合は、船舶に搭載されている等級A移動体用AIS局は、自律モードを使用すべきである。スロットオフセットが与えられる場合は、そのスロットオフセットは、受信した指定事項の送信に関連しているべきである。各指定は、時間において限定されており、必要に応じて、担当機関により発動し直されることになる。最後に受信した指定は、前の指定に引き続いているまたは前の指定の上書きになっているべきである。2種類のレベルの指定が可能である。
2.27.2 明確化の根拠
1)基地局と中継局との機能性の区別。組み合わされた基地/中継局が通報16を送信している場合は、基地局の機能性により行っているものである。
2)必要な指定モードの一般的な明確化。
2.27.3 修正の日付: 2001年10月
2.27.4 所見
この明確化の一部は、船舶に搭載される等級A移動体用AIS局についての設計と試験とに、既に、取り込まれている。この明確化に対して今後変更を行う場合は、何れも、将来に遺る問題を作り出さないように配慮すべきである。
2.28 A2;§3.3.6.2.2 指定モードにおける運用
2.28.1 提案する明確化の文言
指定された各スロットは、指定スロットのタイムアウトに設定されているタイムアウト値を持った、SOTDMAのCommStateを使用すべきである。指定のスロットタイムアウトは、3と7との間になっているべきである。各々のフレームについて、当該スロットタイムアウトは減分されるべきである。
2.28.2 明確化の根拠
編纂上の理由
2.28.3 修正の日付: 2001年10月
2.28.4 所見
なし
2-29 A2;§3.3.6.2.3 自律的で連続的なモードヘの復帰
2.29.1 提案する明確化の文言
新しい指定を受信しない限り、当該指定は、スロットタイムアウトがゼロに達した時に、終了されるべきである。この段階で、当該局は、自律的で連続的なモードへ復帰すべきである。
当該局は、ゼロのスロットタイムアウトを持っている指定スロットを検知したら、直ちに、自律的で連続的なモードヘの復帰を開始すべきである。このスロットは、ネットワークへ加入し直すために使用されるべきである。局は、現在のスロットのNT内ある候補スロットの中から使用できるスロットを無作為に選択し、これをNSSとすべきである。局は、その後で、当該指定スロットを、ITDMAスロットとして代用し、これを、新しいNSSまでの相対オフセットを送信するために使用すべきである。この点から先は、過程は、ネットワークヘの加入段階(
第3.3.5.2項を見ること)と全く同じになるべきである。
2.29.2 明確化の根拠
編纂上の理由(指定モードの明確化に伴う変更)
2.29.3 修正の日付: 2001年10月
2.29.4 所見
なし
2.30 A2;§3.3.7 通報の構造
2.30.1 提案する明確化の文言
アクセス体系の一部である通報は、データパケットのデータ部分の内部において、図15が示している構造を持っているべきである。
図15
各々の通報は、最上段から最下段へかけて列挙されているパラメーターフィールドを持っている表を用いて記述されている。各々のパラメーターフィールドは、最初に最有効ビットで定義されている。副フィールド(例えば通信状態など)を含んでいるパラメーターフィールドは、各々の副フィールド内において最大有効ビットを最初に置き、最上段から最下段へかけて列挙されている副フィールドを持っている別の表で定義されている。
文字ストリングは、最大有効ビットを最初に置き、左から右へかけて呈示されている。使用されていない文字は、全て、@記号で表わされており、ストリングの最後に置かれているべきである。
データは、VHFデータ回線上へ出力される時は、ISO/IEC 3309:1993に従って、各々の通報に付随している表の最上段から最下段へかけて、8ビットのバイトでグループ化されるべきである。各々のバイトは、最小有効ビットを最初にして出力されるべきである。この出力過程にある間に、デ−タは、ビット添加物(第3.2.2項)及びNRZI符号(第2.7項)により形が決定されるべきである。
最後のバイトにある使用されていないビットはゼロに設定され、バイトの境界が保護されるべきである。
通報テーブル(message table)の一般的な例は、次のようになる。
| パラメーター |
記号 |
ビット教 |
解説 |
| P1 |
T |
6 |
パラメーター1 |
| P2 |
D |
1 |
パラメーター2 |
| P3 |
I |
1 |
パラメーター3 |
| P4 |
M |
27 |
パラメーター4 |
| P5 |
N |
2 |
パラメーター5 |
| 使用されていない |
0 |
3 |
使用されていないビット |
第3.3.7項で述べてあるように、データをロジックで表現すると、次のようになる。
| ビットの順序 |
M・・・・L・・ |
M・・・・・・・ |
・・・・・・・・ |
・・・・・・・・ |
・・LML000 |
| 記号 |
TTTTTTDI |
MMMMMMMM |
MMMMMMMM |
MMMMMMMM |
MMMNN000 |
| バイトの順序 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
VHFデータ回線への出力順序(例では、添加ビットは無視されている)は、次のようになる。
| ビットの順序 |
・・L・・・・M |
・・・・・・・M |
・・・・・・・・ |
・・・・・・・・ |
000LML・・ |
| 記号 |
IDTTTTTT |
MMMMMMMM |
MMMMMMMM |
MMMMMMMM |
000NNMMM |
| バイトの順序 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
2.30.2 明確化の根拠
M.1371-1への参照先を訂正
2.30.3 修正の日付: 2001年10月
2.30.4 所見
なし
2.31
A2;§3.3.7.2.2 SOTDMAの通信状態
2.31.1 提案する明確化の文言
この通信状態は、以下の機能を持っている。
1)SOTDMAの概念の中の、スロット割り当てアルゴリズムによって使用される情報を含んでいる。
2)同期状態を示す。
SOTDMAの通信状態は、表10で示されている構造を持っている。
表10
| パラメーター |
ビット数 |
解説 |
| 同期状態 |
2 |
0 UTC直接(第3.1.1.1項参照)
1 UTC間接(第3.1.1.2項参照)
2 局は、基地局に同期を取っている(基地直接)(第3.1.1.3項参照)。
3 局は、受信した局の数が最も多いことに基づいて他局に、または、基地局へ直接同期を取っている他の移動局に、同期を取っている(第3.1.1.3項及び第3.1.1.4項参照)。 |
| スロットタイムアウト |
3 |
新しいスロットが選択されるまで、残っているフレームを特定する。
0 これが、当該スロットにおける最後の送信であったことを意味する。
1-7 各々、1から7までのフレームが、スロットが変わるまで、残されていることを意味する。 |
| 副通報 |
14 |
副通報は、表11で示してあるように、スロットタイムアウトの現在の値により異なる。 |
SOTDMAの通信状態は、関連の送信が発生するチャンネルのスロットに対してのみ適用されるべきである。
2.31.2 明確化の根拠
局が、UTCを持っていない(持っている場合は、状態が「UTC間接」になっているものと思われる)他の移動局が既に基地局へ間接的に同期を取っているかどうか、を判断する方法が明瞭ではない。これは、1レベルを超える同期を招くことになると考えられるが、このことは禁止されている。CommStateのみが、「基地局へ同期を取っている」と表示する。 従って、CommStateを明確にする必要があった。基地局間接はSyncState値3を受信する。どの局も、このSyncStateを、更に同期に利用することは許されていない。次の表は、いろんな同期モードの優先順位とCommStateの中にあるSyncStateの内容とを図解しているものである。
根拠についての図解
| 自局の同期モード |
優先順位 |
図解 |
自局の同期状態
(CommSsateの中における) |
他局によって間接同期源に使用される可能性 |
| UTC直接 |
1 |
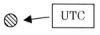 |
0 |
あり |
| UTC間接 |
2 |
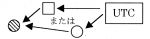 |
1 |
なし |
| 基地局直接 |
3 |

合図局として認定されている基地局 |
2 |
あり |
| 基地局間接 |
4 |
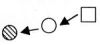
合図局として認定されている基地局 |
3 |
なし |
| 合図局としての移動局 |
5 |

合図局として認定されている移動局 |
4 |
なし |
2.31.3 修正の日付: 2001年10月
2.31.4 所見
この明確化は、移動局が影響を受けるという限りにおいて、船舶に搭載される等級A移動体用AIS局についての設計と試験とに、既に、取り込まれている。この明確化に対して今後変更を行う場合は、何れも、将来に遺る問題を作り出さないように配慮すべきである。