ゴキブリの話
東京商船大学元教授 橋本進(はしもとすすむ)
四国の片田舎で育った昭和ひとけた生まれの私には、家の中で「ゴキブリ」を見たという記憶はない。大戦末期の昭和二十年に商船学校に入っても「シラミ」に悩まされた記憶は強烈だがゴキブリに悩まされたという覚えはない。だからゴキブリは練習船に乗船して初めてお目にかかった昆虫であった。
さて、日本語大辞典(講談社・カラー版)によると
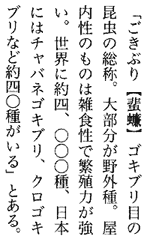
このゴキブリについては、『虫の博物誌』(梅谷献二、築地書館)に詳細であるが、これを参考にしながら話を進めよう。
ゴキブリという名のいわれは<ゴキカブリ(御器かぶり)>がもとになったもので、御器は「合器」が転じたもので、ふた付きの食器−とくに椀−のことをいい、それをかじる虫というところから「御器かぶり」の名が生まれた。
これが「ゴキブリ」となったのは明治時代のことで、ある昆虫学者が「ゴキカブリ」を「ゴキブリ」と「誤記」したのがそのまま伝わったというのが真相のようである。
このゴキブリの化石は古生代の石炭期の地層から発見されている。もちろん、哺乳類はおろか恐竜さえもいなかった三億年も前の時代で、それからあまり姿を変えることなく種族としての生命を長らえている、つまりゴキブリは三億年もの歴史をもつ昆虫−害虫−なのである。
このゴキブリが人類と深い関わり合いをもつようになったのは、人類が住居を建設して以降のことであるが、前述した「御器かぶり」の名から見て、日本での害虫歴もかなり古いように思われるが、ごく近年まではそれほど目立たなかった。昔から日本にいたのは「御器かぶり」の正体と目されるヤマトゴキブリだけで、チャバネゴキブリやクロゴキブリなどは江戸時代以降に外国から侵入してきた帰化昆虫と考えられている。
ゴキブリの仲間はもともと南方系の昆虫で、系統的にはスズムシやキリギリスと親類筋に当たる。ところが好きな虫にスズムシやキリギリスの名をあげる人でも、嫌いな虫となると圧倒的に多いのがゴキブリである。とにかくゴキブリの脂ぎったうすいからだ、長いひげ、毛だらけの長い足……、それらすべてが醜悪で嫌悪感をかきたてるのである。しかしゴキブリのこの醜悪なからだも、故なくしてそうなったのではない。
ゴキブリはもともと野外の生活者で、いまでも多くの種類は朽ち木の皮の下や落葉の下で生活しているから、物のすき間にもぐり込むのに適したうすいからだ、湿った場所で水をはじく皮膚、夜の行動のための長いひげ、武器のないゴキブリに必要な速い逃げ足など、いずれも野外での生活に不可欠の形態であり習性なのである。
ゴキブリと人類の関わりは人類が住居を建設してからだと述べたが、正確には人類が住居の一隅に「台所」をもつようになってからである。この雑食性の昆虫にとって、台所は生涯の食料が保障され、生活上不可欠の水も常時あり、しかも暖かい場所ときている。さらに台所には強力な生存競争の相手も天敵もいない天国であった。ゴキブリはこのような環境で生活しているうちに、現在のような野外では考えられない一大勢力を築き上げるに至ったのである。
ただしその裏には、船の存在があったことも忘れてはならない。
さきに、「チャバネゴキブリやクロゴキブリなどは江戸時代以降に外国から侵入してきた帰化昆虫」と述べたが、この時期はまさに外国船が多数渡来し始めた時期と一致する。一五四三年ポルトガル船が種子島に、関ヶ原合戦のあった一六〇〇年にはオランダ船デ・リーフデ号が九州・臼杵湾に漂着し、日本も大航海時代の洗礼を受け始めた時代だったのである。