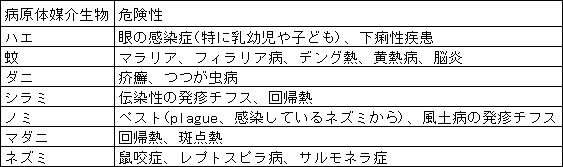廃水処理
64. 水洗式トイレから下水道に汚水が流出してしまったような場合には処理が必要だ。処理道具は市販されているが、ふつうは値段が高く複雑で、取り扱いや維持が難しい。
65. しかし廃水処理技術には様々な種類がある。最適な技術を選ぶのには衛生工学の専門家と相談する。
◆有害生物と病原体媒介生物の駆除
◆ 虫やネズミ類(rodents)は、病気を媒介・まん延させ、食糧を腐らせてしまうこともある。
◆ 当面の適策は、物理的な仕切りを設けることである。
◆ 病原体媒介生物が繁殖したり、好む場所をなくす予防措置が、最良の長期的解決策となる。
◆ 化学的処置はすべて専門家の監督下で行ない、害虫の抵抗力については地元の情報が必要になる。
◆ 化学薬品による防除はなるべく避ける。
一般的な考慮事項
66. 難民緊急事態は、病気を媒介する虫やネズミ類(病原体媒介生物、vectors)を繁殖させやすい典型的な環境である。こうした虫やネズミ類は大量の食糧を荒らす場合がある。
67. ハエは人間の排泄物や食物がある場所に、蚊は水たまりに、ネズミ(rats)は食物、ゴミ、物陰のある所に繁殖する傾向がある。人口過密と個人の不衛生な状態によって、シラミ、ノミ、ダニ、マダニその他の節足動物が健康に害を与える場合もある。表2に、一般的な病原体媒介生物と関連する病気を示した。
68. 緊急事態では、ハエ、蚊、ネズミ類をすぐに減らすのは難しいから、当面は物理的な仕切りの設置が最良の策であろう。長期的には、根本的な予防策が虫やネズミ類の防除に最も効果的であり、個人の衛生状態、排水設備、ゴミ処理、食糧の貯蔵、取り扱い方法などを改善し、病原体媒介生物が好む環境を排除する。具体的な方法としては、水たまりをなくし、ゴミを定期的に収集し、トイレに油を流し、石けんと手や体を洗うための十分な水の支給などがある。石けんは、1人あたり毎月250グラム支給するのが望ましい。計画は定期的に見直し、他の公衆衛生対策に組み込む。
69. 問題点は難民と話し合い、病原体媒介生物を駆除する重要性について教える。難民になじみのない対策を取る場合は、入念に説明する。
表2 健康に与える危険が大きい病原体媒介生物