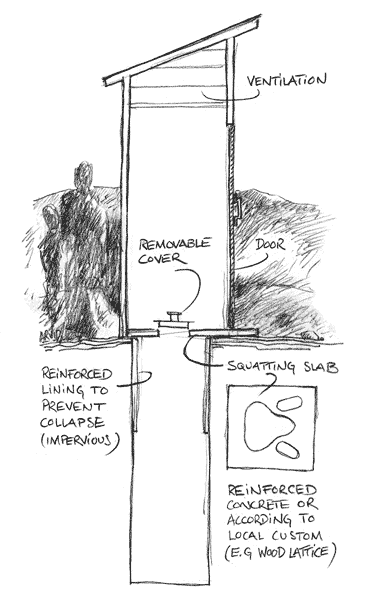4つの基本部分、すなわち便槽、土台、しゃがみ板(コンクリートまたは板)、上屋からなる。
41. 1世帯だけで使用すれば、ピット式トイレは通常清潔に維持される。いくつかまとめて設置し共同トイレにもできる。
42. ピット式トイレは、人口密度が低〜中程度(1ヘクタールあたり約300人まで)の場合に最適だが、この2倍の人口密度の場所でも十分に利用されている。1世帯あたり1個のピット式トイレを設置する場所だけでなく、便槽が一杯になった時に新しい便槽を掘るスペースも必要になる。ピット式トイレを共同トイレにする場合は、この点が重要な考慮事項になる。
43. 便槽が四分の三まで一杯になったら土をかぶせ、上屋と床板を新しい便槽に移す。途中何回か灰をまくと排泄物の分解が早まり、やがてその場所を再利用できるようになる。
44. 便槽は直径約1メートル、深さは2メートル以上にする。槽の縁を地面から約15センチ盛り上げ、地表を流れる雨水を避けるために土台の周りに溝を掘る。槽の壁は必ず地下1メートルまで補強し崩れないようにする。
45. これらの基本型には、悪臭・害虫問題があるが、通気改良型(VIP = ventilated improved pit)のように簡単な改良を施したり(図2a参照)、油を加えてフタをすれば大幅に抑制できる。
ピット式トイレを設置する場合は、できるだけ通気改良型にする。
46. VIPトイレの通気孔は、直径15センチ、高さ約2.5メートル以上とし、黒ペンキを塗って日の当たる側に設置し、最大限に悪臭や虫害を防除できるようにする。通気孔の外側を黒く塗ると通気速度がわずかに上昇する。無風状態ではこれが非常に重要になる。通気孔には、虫よけ用の金網を取り付ける(ハエ捕りにもなる)。空気の流れを遮断してしまうので、通気孔にフタはしないこと。
図 2a
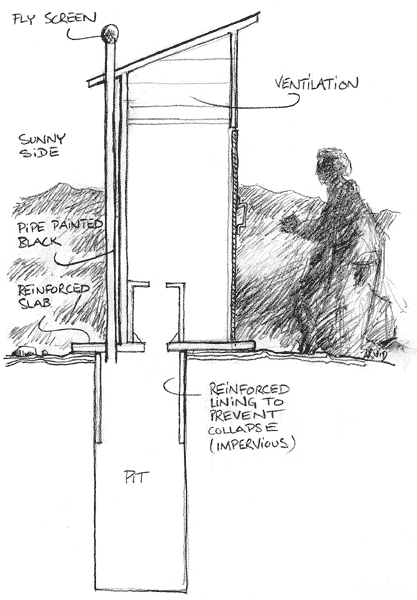
図 2b