人を大切にした看護
宮崎県立宮崎病院
吉本美智代
近年治療や医療機羅、医療制度などが著しく変化、疾病構造も生活習慣病等の一生病気と付きあっていかなければならない慢性疾患が増加してきている。癌も慢性疾患の一つとして位置づけられるようになり、診断から死に至る長いプロセスを人それぞれに経過していかれる中で私達医療者は深く関わっていかなければならない。これまで治療や処置等の技術には知識の習得に力が注がれてきたが、個人の価値観や気持ちなどの抽象的なものに対する理解は二の次にされてきた。しかし、多様化する医療の中で患者が自己決定していくためには医療者が価値観や気持ちを引き出す技術と支えていくサポート力が必要になってきた。今回、緩和ケアについてトータルして学ぶ機会に恵まれ、専門的知識と技術について当初の目標以上の多くの成果を得た。講義と病院実習の双方から振り返り、今後の自分自身及び自己の施設にどのように活用していくかを考えてみたい。
緩和ケアの理解
1990年のWHO発行の「癌の痛みからの解放とパリアティブケア」では、「緩和ケアとは、治癒を目指した治療が有効でなくなった患者に対する積極的な全人的ケア(トータルケア)である。痛みやその他の症状のコントロール、精神的、社会的、そして霊的問題の解決がもっとも重要な課題となる。緩和ケアの目標は、患者とその家族にとってできるかぎり可能な最高のQOLを実現することである。末期だけでなく、もっと早い病期の患者に対しても治療と同時に適応すべき点がある」としている。
図?のように、現状では癌に対して治癒の見込みが完全に絶たれた状態で初めて緩和ケアを考慮する考えが一般的である。しかも緩和ケア病棟で全人的ケアを受けられる人は、日本の癌罹患者のほんの一握りに過ぎない。これからは図?のように癌の診断がつき、治療開始とともに症状コントロールがなされ、個人の病期に適した、しかも個々のQOLが尊重された精神的、社会的、霊的、家族的援助が継続して、かつ連携された医療チームによって支えられることが理想的と考える。
? 現状における癌医療資源の使いかた
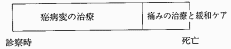
? 先進国における癌医療資源の使いかたについての提案
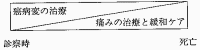
緩和医療を行うには
施設設置基準の概要(厚生省1990年)によると以下の8項目が規定されている。
?末期の悪性腫癌またはエイズ患者を対象とする。
?専任の医師が常勤している。
?看護婦が入院患者1.5人以上の割合で勤務している。
?該当病院が新看護または基準看護を行っている。
?病棟床面積が30?/人以上、病室床面積8?/人以上である。
?個室が病室の概ね5割以上である。
?家族の控え室、患者専用の台所、面談室、談話室がある。
前ページ 目次へ 次ページ