患者・家族の心の変化を予想し、また十分な観察をもとに、それに適した計画を立て精神的援助をしていかねばならないと考える。
(3)チームアプローチ
緩和ケア病棟では、患者の残された人生の質を高めるために、それらの基本的ニーズ(身体的・精神的・社会的・霊的)を満たしていくことが大切である。しかし、すべてのニーズを医師と看護婦だけで満たすことは困難である。そのため、他職種の人々とともに専門分野を生かしてチームを組み、患者のニーズを満たしていくことが重要となる。例えば、身体的ニーズにおいて?痛みをはじめとする身体的症状は緩和医、?不眠・混乱などは精神科医に相談が必要となることもある。?リハビリ的ニーズはリハビリ医やPT、?食事面は栄養士などとその専門性が必要となり、協力を要請しなければならない。そのためにも、フラットな立場でのアプローチの徹底が必要となる。しかし、一般病院では医師と看護婦の関係は縦型であり、これをいかにフラットな立場にするかが大きな課題と考えている。また、これから緩和ケア開設というメリットを生かし、開設当初より、医師・看護婦に加えて他職種(チャプレン・PT・OT・栄養課・ソーシャルワーカーなど)もまきこんでのチーム作りをしなければならないと考えている。さらに、チームの情報源であるカンファレンスには医師をはじめとする他職種の参加を定着させることが、チームアプローチの中心となる看護婦の重要な役割と考えている。カンファレンスの円滑な進め方のこつは実習で学ばしてもらい、今後に大いに役立てさせてもらいたいと思っている。
(4)症状コントロール
パトリシア・J・ラーソン先生の症状マネジメントを学んだとき、言葉としては馴染みが少ないことであったが、内容は私達看護婦が日常的に抱えている問題解決の一つであると思った。今まで、日本の医学は疾病と診断には強い関心を示すが、症状緩和に関する関心は低く、患者に我慢をさせ、我慢強い患者に潜在的に好感を持ち、訴えの多い患者を煙たがる現象がある。看護婦は患者が我慢していることもよく知っており、患者の苦痛が複雑な要因でなり立っていることもよく知っている。症状マネジメントに関する強い患者のニーズを最も感じているのは看護婦かもしれなへ近年緩和医療が叫ばれるようになり、症状コントロールの重要性が見直されるようになった。薬剤、特に麻薬に対して偏見を捨て、適切な使い方について知識を持つということ、医療チームの連携を強めること、そして重要なのが患者の訴えをそのまま信じることがいかに大切かということである。また、看護婦が患者の症状やそのマネジメントを適確に理解するためには、自分達がケアする患者によく見られる症状の機序とその現れ方について知識を持つ必要もあることが学べた。
そして、身体症状及び精神症状に対して、十分な症状コントロールをすることにより、その人らしさを取り戻すことができ、患者・家族のQOLを高めることに繋がる。
また、その症状がうまくコントロールできているかどうか、アセスメントしチームで検討する場が、毎日の申し送りである。一般病棟の場合、申し送りは簡潔にエピソードは抜きで申し送る傾向にある。しかし、緩和病棟では患者の表情・態度・言動・日常生活の変化を知ることによって患者の訴えだけでない症状を知る手掛かりになることが多いため、エピソードが重要になることもあると感じた。また、使用している薬剤の効果・副作用についてのアセスメントも日々繰り返し評価しなければならないし、今の患者にはなにが必要かの検討も申し送りの情報をもとに微調整していかねばならないと考える。
(5)精神的ニード
人間にとって死に直面することは、人生最大の危機状況といえる。末期患者の精神的ニーズを知り、援助していくためには危機や悲嘆の状態を知り、そのプロセスに応じた介入の方法をよく知っておく必要がある。心理的プロセスに関してはキューブラー・ロスの5段階を学び、これを活用し患者の心の変化を予測していくことができる。
(日本人の心理プロセス)
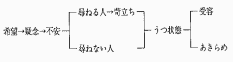
前ページ 目次へ 次ページ