? スタッフ同士が理解を深め、お互い助け合うことができる。
?方針の一致した看護ができる。
?スタッフがそれぞれ本来の任務を遂行できる。
チームの情報交換の場として朝の申し送り、カンファレンスがあるが、我々の実習した11施設ではほとんど看護婦のみならず医師、チャプレンも毎日参加していた。その場の雰囲気は、真剣な中にも和やかさがあり、縦関係がなかった。実習施設で学んだカンファレンスの円滑に行う方法として、?患者のバックグランドを表面に出し、?症状ばかりを取り上げない、?生活面に焦点をあて、少しでも快適に過ごせるためにという視点で、?日常的な言葉で全体のイメージを掴むようにする、?問題として取り上げる患者のプライマリーナースが司会、進行するとやりやすい、などである。
(3)進行がん患者の全人的苦痛とその援助について
緩和ケアの目指すものは、進行がん終末期患者が残された日々を家族とともにその人らしく生きられるよう援助することであり、患者の生活の質Quality of lifeをできるだけ高めることである。そのためには症状のコントロールおよびケアが重要である。患者の苦痛を身体的、精神的、社会的、霊的の4つの側面から構成されているととらえ、これらが相互に関連する全人的苦痛Total painとして理解することが重要であり、これらが十分にケアされると患者は自分らしさをとりもどすことができる。全人的痛みとは、近代ホスピス運動の創始者であるシシリー・ソンダースが、がん患者と関わった経験から、患者が体験している複雑な痛みのことを表現した概念である(図1参照)。
ターミナル期の患者の全身状態は進行性で変化しやすく、症状が増悪したり、新しい症状が現れることがしばしばである。そのため、看護婦は患者をよく観察し、患者の訴えに真剣に耳を傾けることが重要になる。また、表情・態度・言動・日常生活の変化を知ることで患者の訴えだけでない症状を知る手掛かりになることが多いため、看護婦の感性を磨くことも大切である。また、使用している薬剤の効果、副作用についてのアセスメントが必要で、日々繰り返し評価し、今、患者には何が必要かの検討をし、微調整を行っていく。少しでも早く、患者の苦痛を緩和すべくチーム全体の取り組みが大切である。
精神的問題に対しては、看護婦が自分自身の「死生観」をしっかりもち、患者から逃げずに共に引き受けていこうとする覚悟が必要である。また、患者のあるがままを受け止め、その感情を理解していくための対話の技術が看護婦には要求される。コミュニケーション・スキルとして傾聴・共感は基本であるが、患者の思いに一歩踏みこんで気持ちを明らかにしていく。「わかってもらえた」という情緒的満足は、患者・家族との信頼関係につながっていく。時には精神科医へ依頼することも必要である。
霊的ケア(スピリチュアルケア)に対しては、かなり専門領域であり看護婦には荷の重いことが多い。まさしく患者の“魂の叫び”であり、生きる意味への問いである。今生かされていること自体に喜び・希望を感じられるよう誠の愛で支えることである。患者の人生の「完成期」にかかわらせていただきありがとうございます、という感謝の気持ちで接することが大切となる。宗教の有無は問わないが、あればその人の宗教を大切にする。
(4) 緩和ケア病棟の運用方法について
?看護体制
看護方式はプライマリーナーシングがよいと考える。
その理由は
・患者に対する責任があるため、患者の問題解決が早くなされる。
図1 全人的痛み (Total pain)
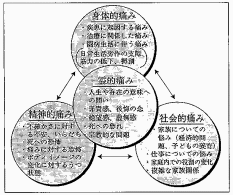
前ページ 目次へ 次ページ