|
(4)2次元放射温度計による計測
直射日光下の上甲板において2次元放射温度計により測定した1m四方64点の平均温度は以下のようである。
・上甲板温度:62.9。C、(遮光ネット下)42.3℃
・ハッチコーミング側面温度:51.0℃、(遮光ネット下)38.8℃
・ハッチコーミング側の配管温度:49.9℃、(遮光ネット下)38.6℃
・作業者衣服温度:37.6℃、(周囲温度)51.9℃
デッキ温度は60〜65℃(平均62.9℃)であり、一方ハッチコーミング側面は艤装品の影や日射の入射角が浅いこともあり、上甲板ほどの温度には至っていない。また、配管などもその色や材質の吸収率が小さいために、上甲板の温度ほど上昇していない。
熱対策として遮光ネットが張られ、その影に入っている上甲板温度は37〜47℃(平均42.3℃)であり、直射日光下とは20℃ほどの差がある。ハッチコーミング側面、配管においても10℃ほどの温度低下が見られる。全天日射量もネットの遮光率に応じて低下することから、遮光ネットは日射環境下での熱対策として非常に有用であると考えられる。
衣服温度は平均で37.6℃となっているが、汗による濡れが無い場合には衣服温度が40℃を超えることも予想される。
(5)作業内容および継続時間
上甲板では、ブロックの継目、艤装品の溶接とそれに伴うスラグ落とし、またはガス切断の作業が大半を占めており、その準備として重量物の運搬(移動)などが行われていた。この他には、ハッチコーミング周囲への足場の取り付け、ジャッキを用いたブロックの継目のズレ調整作業などが行われていた。
上甲板における作業の例として、ビデオカメラにより記録した軽度作業および中程度作業における作業内容毎の全作業時間に対する割合をTable 2に示す。軽度作業は船体外板の継目の溶接作業であり、代謝量の大きいスラグ落としや重量物の運搬などの作業が少なく、後述の作業と代謝量の関係より推定した平均代謝量も平均で1.80Metであったことから軽代謝速度と判定した。中程度作業は艤装品を上甲板に溶接する作業であり、溶接作業とスラグ落としが交互に繰り返され、代謝量も平均で2.08[Met]であったことから中代謝速度とした。
(6)熱対策
熱対策として採られていたのは、遮光ネット、冷却ファンによる送風、冷水機の設置などであった。
a)遮光ネットは、遮光ネットを張れない場所が多く、使用時の作業性などからその影に入らずに作業するなど、対策としての効果をあまり発揮していなかった。
Table 2 Time ratio of each work to the whole work
| Class |
Work contents |
Working time |
Ratio [%] |
| Low Metabolic work |
Preparation, Marking, Cleaning |
7m16s |
33.9 |
| Welding |
13m03s |
60.8 |
| Tearing off the slug |
9s |
0.7 |
| Taking a rest |
59s |
4.6 |
| Whole working time |
21m27s |
100 |
| Moderate Metabolic work |
Preparation, Marking, Cleaning |
5m25s |
17.9 |
| Welding |
17m47s |
58.8 |
| Tearing off the slug |
7m02s |
23.3 |
| Taking a rest |
0s |
0.0 |
| Whole working time |
30m14s |
100 |
|
b)冷水機は、近くで作業している作業者は頻繁に利用し、作業場所が遠くても水筒に冷水を入れて作業場所まで持って行く作業者がいるなど、設置場所や設置台数などを考慮すれば、より効果的な対策になると考えられる。
c)ダクトによる送風は、ダクトが数多くの作業場所に引かれ、作業場所の移動に伴い機具の移動と共にダクトを延長するなどして利用し、その依存性は高いように見受けられた。
3.3 作業と代謝量
ISO7243ではTable 3のように、代謝量は休憩中、低代謝速度、中代謝速度、高代謝速度、極高代謝速度の5つのクラスに分類されており、この表から各種の作業がどの程度の代謝量であるのかを推測することができる。
Table 3 Classification of levels of metabolic rate
| Class |
Metabolic rate range. M |
Value to be used for calculation of mean metabolic rate |
related to a unit skin surface area
W/m2 |
for a mean skin surface area of 1.8m2
W |
| W/m2 |
W |
0
Resting |
M<65 |
M<117 |
65 |
117 |
1
Low metabolic rate |
65<M<130 |
117<M<234 |
100 |
180 |
Examples
Sitting at case: light manual work (writing, drawing),
hand and arm work (inspection, assembly or sorting of light materials): arm and leg work (driving vehicle in normal conditions, operating foot switch or pedal).
Standing: drill (small parts): coil winding: machining with low power tools: casual walking (speed up to 3.5 km/h). |
2
Moderate metabolic rate |
130<M<200 |
234<M<360 |
165 |
297 |
| Sustained hand and arm work (hammering in nails, fitting): arm and leg work (off-road operation of lorries): arm and trunk work (work with pneumatic hammer, plastering, intermittent handing of moderately heavy material), pushing or pulling light-weight carts or wheelbarrows: walking at a speed of 3.5 km/h to 5.5 km/h: forging. |
3
High metabolic rate |
200<M<260 |
360<M<468 |
230 |
414 |
Intense arm and trunk work: carrying heavy material: shovelling: sledge hammer work: walking at a speed of 5.5 km/h to 7 km/h.
Pushing or pulling heavily loaded handcarts or wheelbarrows: chipping castings |
4
Very high metabolic rate |
M>260 |
M>468 |
290 |
522 |
| Very intense activity at fast to maximum pace: climbing stairs, ramp or ladder: walking quickly with small steps, running, walking at a speed greater than 7 km/h. |
|
前述の上甲板での作業それぞれを、作業の様子を記録したビデオとTable 3との比較により、作業内容に対する代謝量を以下のように推測した。
1)溶接機材の設置および準備、マーキング、後片付け:低代謝速度にあたると推測でき、代謝量を100[W/m2](1.72[Met])とする。
2)溶接作業:Table 3の作業例に無く、資料より代謝量は低代謝速度にあたる110[W/m2](1.89[Met])とする。
3)溶接のスラグ落とし:釘を打つのと同等作業と見て、中代謝速度にあたると推測でき、代謝量を165[W/m2](2.84[Met])とした。
4)休憩:代謝量65[W/m2](1.12[Met])とする。
4 代謝量・環境要因と人体蓄熱に関する実験
人体蓄熱量の限界値を超えないように、温熱環境要因を考慮して作業負荷を減らしたり、作業間に休憩を取るなどの暑熱対策を策定するためには、代謝量・環境要因と人体蓄熱の関係を把握する必要がある。そのために、日射環境下においてエルゴメーターを用いた運動による人体蓄熱実験を行った。
4.1 実験方法と条件
(1)実験の概要
実験は7階建屋上の一角に、気流速の影響を避けるためにアルミニウム製の囲い(幅3.1m×奥行3.2m×高さ2.0m)の中にエルゴメーターを設置して運動を行い、日射のある暑熱環境下における作業負荷や環境要因に応じた人体の皮膚温度を計測して、以下の3種類の要因の影響を調べる人体蓄熱実験を行った。
1)作業負荷の影響:エルゴメーターの負荷(作業による発熱量)を0W(安静立位)、110W(低代謝速度)、160W(中代謝速度)に設定して計測する実験
2)個人差の影響:4被験者による負荷160Wの運動による実験
3)日射量の影響を見るために日射量が少ない、中程度、多いの3ケースについての実験
なお、実験時の服装は、工場作業者に合わせて、ヘルメット、作業服上下、Tシャツ、パンツ、靴下、安全靴を身に付け、その被服量はおよそ1.0cloであった。
これらの実験の概念図をFig. 4に示す。
(2)環境要因および皮膚温度、鼓膜温度の測定
暑熱環境下において作業を行う人体の熱的状態は、太陽からの日射も含む温熱環境要因に依存し、作業による代謝産熱と呼吸・皮膚表面からの放熱により、人体基幹部の熱的恒常性を保っている。
Fig. 4 Conceptual state of experiment
ここでは人体を熱平衡が保たれている中核部と末梢組織からなる外殻層により取り囲まれている二重構造と考え、外殻層の表面温度は皮膚温度により代表し、中核部の温度を外部から容易に測定できる鼓膜温度によって代表した。この鼓膜温度は脳を灌流する内頸動脈血温度をよく反映し、深部体温の指標となり、赤外線センサーを用いた非接触温度計により測定できる。
蓄熱量計算に用いる環境要因の測定には、ISO7726に従ってアルミ板を張った囲いの中に設置したアメニティメーターおよびWBGT計により測定した。また、全天日射量の測定は同じ屋上の一角にて行った。
皮膚温度については、熱電対型センサーを後頸部t1、肩甲骨付近t2、手甲部t3、下腿部t4の4点に貼り付けて測定し、次式により平均皮膚温度Tskを算出する3)。
Tsk=0.28t1+0.28t2+0.16t3+0.28t4 [℃] (25)
この他に、参考値として衣服温度(大腿部、胸部)を測定した。
(3)実験の手順
1)実験開始時に黒球温度などが平衡状態に達している様に、開始30分前頃に囲いの中にアメニティメーター、WBGT計を設置し、計測を開始する。
2)全天日射計を影に入らないような位置に設置し、PCに接続されたデータロガー(江藤電気製CADAC2)に接続する。
3)被験者の体に皮膚温度計測のための熱電対端子を貼り付け、DETA COLLECTER(安立計器製AM-7052)により記録する。
4)服装の準備が出来たら、日陰にて5〜10分ほど安静にする。
5)実験開始1分前に囲いの中に入り、エルゴメーターの設定(負荷、年齢、時間)を入力し、心拍数センサーを取り付ける。
6)負荷が設定されたエルゴメーターによる運動を15分間行う。1分毎に心拍数と鼓膜温度を記録し、このモニタリングにより実験の継続・中止を決める。
7)運動終了後、再び日陰に移動し、十分に鼓膜温度が下がるまで安静にする。
(4)被験者の諸元
個人差の影響を調べる実験における被験者の諸元をTable 4に示す。また、普段の運動量により熱に順応する早さの差異が考えられるため、普段の運動の程度について調査した。
なお、被験者の代謝量および蓄熱量を計算するのに必要な体表面積Abは次式によって算出した3)。
A b= 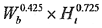 ×0.007246 [m 2] (26) ここで、Wbは体重[kg]、Htは身長[m]である。
Table 4 Principal conditions of examinees
| Examinee |
Age |
Height [cm] |
Weight [kg] |
Surface are [m2] |
Usual Exercise |
| A |
24 |
169 |
74 |
1.86 |
Beach vallyball (twice week) |
| B |
23 |
175 |
76 |
1.93 |
no exercise |
| C |
22 |
168 |
62 |
1.72 |
no exercise |
| D |
23 |
179 |
58 |
1.75 |
Softball (once a week) |
|
|