|
音楽(おんがく)のまち(2)―ロンドン
最近(さいきん)人気(にんき)の『ハリー・ポッター』や映画(えいが)の『ロード・オブ・ザ・リング』などは、イギリスの人々(ひとびと)の生活(せいかつ)に今(いま)も息(いき)づいている、古い(ふるい)伝統(でんとう)を題材(だいざい)にした物語(ものがたり)です。そこには、古代(こだい)のケルト人(じん)、アングル人(じん)、サクソン人(じん)、デーン人(じん)、ノルマン人(じん)、ローマ人(じん)など、海(うみ)をこえてイギリスにやってきた、さまざまな民族(みんぞく)の文化(ぶんか)が流れ込んで(ながれこんで)います。それは音楽(おんがく)も同じ(おなじ)。イギリスの音楽(おんがく)には、いろいろな民族(みんぞく)の音楽(おんがく)から受け継がれ(うけつがれ)てきたメロディや、ハーモニー、楽器(がっき)、リズムの伝統(でんとう)があります。そのため、イギリスは、昔(むかし)からヨーロッパ大陸(たいりく)とはちがう、独特(どくとく)な音楽(おんがく)の文化(ぶんか)を持って(もって)いると言われ(いわれ)てきました。それでいながら、ビートルズのように、時代(じだい)の最先端(さいせんたん)を行く(いく)ような音楽(おんがく)が出て(でて)きて、世界中(せかいじゅう)を熱狂(ねっきょう)させたりもする。―イギリスの音楽(おんがく)には、そんな不思議(ふしぎ)な魅力(みりょく)があります。
イギリスの人々(ひとびと)の音楽好き(おんがくずき)も、伝統的(でんとうてき)なものです。今(いま)から250年(ねん)ほど前(まえ)、まだ音楽(おんがく)が王(おう)や貴族(きぞく)だけの楽しみ(たのしみ)だったころに、誰(だれ)でも音楽(おんがく)を楽しむ(たのしむ)ことができる演奏会(えんそうかい)がまっさきに開かれた(ひらかれた)のがロンドンの町(まち)でした。野外(やがい)のコンサートや音楽祭(おんがくさい)は、現在(げんざい)でも各地(かくち)でよく開かれ(ひらかれ)、人々(ひとびと)はみなピクニックの気分(きぶん)で、気軽(きがる)に音楽(おんがく)を聴き(きき)に出かけ(でかけ)ます。一番(いちばん)有名(ゆうめい)で盛大(せいだい)な音楽祭(おんがくさい)は、毎年(まいとし)夏(なつ)にロンドンで開かれ(ひらかれ)ている「プロムス」でしょう。ロイヤル・アルバート・ホールの中(なか)には、立ち見(たちみ)の人(ひと)でいっぱい。入り(はいり)きれない人(ひと)は近く(ちかく)の公園(こうえん)に集まり(あつまり)、スクリーンで音楽(おんがく)を楽しみ(たのしみ)ます。そこで必ず(かならず)演奏(えんそう)されるのが、エルガーの『威風堂々(いふうどうどう)』。この曲(きょく)が始まる(はじまる)と、観客(かんきゃく)たちはじっとしていられません。全員(ぜんいん)がリズムに乗って(のって)体(からだ)をゆらし、大きな(おおきな)声(こえ)を合わせ(あわせ)て、ほこらしげに歌い出し(うたいだし)ます。
きょう聴いて(きいて)いただく作品(さくひん)は、イギリスの人々(ひとびと)が、美しい(うつくしい)メロディ、美しい(うつくしい)音楽(おんがく)を本当(ほんとう)に心(こころ)から愛し(あいし)、大切(たいせつ)にしているということが分かる(わかる)ものばかりではないでしょうか。エルガーが『ミュージック・メイカーズ』という作品(さくひん)に書いた(かいた)次(つぎ)の詩(し)は、そんな人々(ひとびと)の心(こころ)をよくあらわしています。―「私(わたし)たちは音楽(おんがく)の作り手(つくりて)。心(こころ)に夢(ゆめ)をいだいて、たった一人(ひとり)で大海原(おおうなばら)に舟(ふね)をこぎ出す(だす)。・・・だが私(わたし)たちは、世界(せかい)の心(こころ)を動かし、ふるわせることができるのだ」。
ロイヤル・アルバート・ホール
|
ヴィクトリア女王(じょおう)の夫君(ふくん)アルバート公(こう)の記念(きねん)会堂(かいどう)として1871年(ねん)に完成(かんせい)した由緒(ゆいしょ)ある円形(えんけい)のコンサートホール。座席数(ざせきすう)6500席(せき)。ロンドンの夏(なつ)の音楽風物詩「プロムス」の会場。
|
オーケストラ質問箱(しつもんばこ) 〜Q & A〜 このコーナーでは、皆さん(みなさん)からいただいた「オーケストラへの質問(しつもん)」に大友直人(おおともなおと)さんやオーケストラの楽員(がくいん)さんがお返事(へんじ)をします。疑問(ぎもん)を解決(かいけつ)して、コンサートをますます楽しんで(たのしんで)くださいね。
■大友(おおとも)さんはどうして指揮(しき)を始めた(はじめた)のですか? [鈴木結子さん 8才]
オーケストラの音楽(おんがく)が大好き(だいすき)だったからです。小さい頃(ちいさいころ)からずっと自分(じぶん)で作曲(さっきょく)した曲(きょく)をオーケストラで演奏(えんそう)したいと思って(おもって)いて、指揮者(しきしゃ)に憧れて(あこがれて)いました。 [大友直人(おおともなおと)]
■指揮者(しきしゃ)になるにはどんな勉強(べんきょう)が必要(ひつよう)ですか? [白石詩音さん 9才]
まず何(なに)か一つ(ひとつ)でも楽器(がっき)を深く(ふかく)勉強(べんきょう)することが大切(たいせつ)です。私(わたし)の場合(ばあい)はピアノとコントラバスでした。そしてたくさんの曲(きょく)を聴き(きき)楽譜(がくふ)をみて、あらゆる種類(しゅるい)の音楽(おんがく)に親しみ(したしみ)学ぶ(まなぶ)とよいと思い(おもい)ます。 [大友直人(おおともなおと)]
■指揮(しき)の手振り(てぶり)はどうして大きく(おおきく)なったり小さく(ちいさく)なったりするんですか? [山口基さん 9才]
指揮者(しきしゃ)が楽譜(がくふ)に書かれた(かかれた)音楽(おんがく)の表情(ひょうじょう)を奏者(そうしゃ)の人(ひと)に伝える(つたえる)ためには全身(ぜんしん)を使って(つかって)表現(ひょうげん)する必要(ひつよう)があります。自分(じぶん)のイメージする音楽(おんがく)をオーケストラから生み出す(うみだす)ために指揮(しき)をしていると、体(からだ)に表れる(あらわれる)のだと思い(おもい)ます。 [大友直人(おおともなおと)]
■ティンパニのばちを変える(かえる)のは、どんな意味(いみ)があるのですか? [森円花さん 11才]
演奏(えんそう)する音楽(おんがく)に一番(いちばん)ふさわしいおんしょくや音(おと)の響き(ひびき)を作る(つくる)ためです。時代(じだい)や作曲家(さっきょくか)、作品(さくひん)、旋律(せんりつ)によって音色(ねいろ)はすべて違い(ちがい)ますので、音楽(おんがく)にあったバチを選択(せんたく)して演奏(えんそう)します。自分(じぶん)のもとめる音(おと)をだすために、いつも木(き)の棒(ぼう)にいろんなフェルトを巻いて(まいて)手作り(てづくり)をするんですよ。本番(ほんばん)ではとてもたくさんのバチを使い分け(つかいわけ)ています。ずらりと並べて(ならべて)ありますので、舞台(ぶたい)の近く(ちかく)の席(せき)の人(ひと)は覗いて(のぞいて)みてくださいね。 [打楽器(だがっき) 奥田昌史(おくだまさし)]
■4月(がつ)に演奏(えんそう)した『ボレロ』で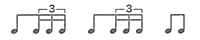 のリズムを数えて(かぞえて)いたら、90回(かい)位(ぐらい)吹いて(ふいて)いるように聞こえ(きこえ)ました。飽き(あき)ませんか?[関川杏さん 8才] のリズムを数えて(かぞえて)いたら、90回(かい)位(ぐらい)吹いて(ふいて)いるように聞こえ(きこえ)ました。飽き(あき)ませんか?[関川杏さん 8才]
ボレロは旋律(せんりつ)を演奏(えんそう)する楽器(がっき)が次々に変わり(かわり)、音楽(おんがく)がどんどん変わって(かわって)いく曲(きょく)です。変化(へんか)する音楽(おんがく)に寄り(より)そってきれいにとけこめるように、ホルンのねいろを変え(かえ)たり響き(ひびき)を変え(かえ)たりしているので、同じ(おなじ)リズムを続け(つづけ)ていても飽きる(あきる)ことはないですよ!ボレロの中(なか)ではホルンはそれほど目立たない(めだたない)のに、注意(ちゅうい)して聴いて(きいて)くれてどうもありがとう。でも、本当(ほんとう)は90回(かい)よりもう少し(すこし)たくさん吹いて(ふいて)いるんだよ(笑) [ホルン:竹村淳司(たけむらじゅんじ)]
■タンバリンには何通り(なんとおり)の叩き方(たたきかた)がありますか? [菊池樂さん 8才(さい)]
タンバリンの奏法(そうほう)に決まり(きまり)はないので、いくつあるかはわかりません! もともとは踊り(おどり)の音楽(おんがく)に使用(しよう)されていた楽器(がっき)で、演奏者(えんそうしゃ)が自由(じゆう)に叩いたり(たたいたり)振った(ふった)りして音(おと)をだしていました。「叩く(たたく)」「振る(ふる)」「こする」というのは、打楽器(だがっき)の三大要素(さんだいようそ)なんです。片手(かたて)で叩いたり(たたいたり)両手(りょうて)で叩いたり(たたいたり)、指(ゆび)でこすったり振った(ふった)り・・・。ほとんどが指(ゆび)を使った(つかった)奏法(そうほう)ですが、レスピーギの『ローマの松(まつ)』のように「バチ(ばち)で叩く(たたく)」と指示(しじ)される所(ところ)もあります。昔(むかし)から多く(おおく)の人(ひと)が知恵(ちえ)を絞って(しぼって)考え(かんがえ)てきた奏法(そうほう)を受け継ぎ(うけつぎ)ながら、私達(わたしたち)も毎日(まいにち)が研究(けんきゅう)です。アイデアを使って(つかって)様々(さまざま)な音(おと)を出して(だして)いますので、見て(みて)くださいね。 [打楽器(だがっき):塚田吉幸(つかだよしゆき)]
■コントラバスやテューバなど、大きい(おおきい)楽器(がっき)は何歳(なんさいぐらい)位から習える(ならえる)のですか?[宇佐見美和子さん 36才]
□コントラバス こどもむけにチェロ位(ぐらい)の小さい(ちいさい)楽器(がっき)があるので、小学校(しょうがっこう)の低学年(ていがくねん)から始め(はじめ)られると思い(おもい)ます。私自身(わたしじしん)は高校生(こうこうせい)から始め(はじめ)ました。身長(しんちょう)が150センチ少々(しょうしょう)あれば、フルサイズの楽器(がっき)を弾ける(ひける)のではないかな。コントラバスは大きい(おおきい)ので、移動(いどう)する時(とき)には抱え(かかえ)たり車(くるま)に乗せ(のせ)たり、大変(たいへん)です!でも大好き(だいすき)なのでやめられません・・・ [コントラバス:笠原勝二(かさはらしょうじ)]
□テューバ 体(からだ)が成長(せいちょう)してから始めた(はじめた)方(ほう)がいいと思い(おもい)ます。小学校(しょうがっこう)の4年生位(ねんせいぐらい)になれば、口(くち)の形(かたち)や顎(あご)、骨格(こっかく)が発達(はったつ)するので大丈夫(だいじょうぶ)でしょう。楽器(がっき)もこども向け(むけ)に小さな(ちいさな)サイズからありますので、興味(きょうみ)がある人(ひと)は挑戦(ちょうせん)してみてください! [テューバ:渡辺 功(わたなべ いさお)]
第(だい)2回(かい) イギリス(ロンドン)編(へん)
大和田(おおわだ)ルースさん(東京交響楽団(とうきょうこうきょうがくだん)第(だい)1ヴァイオリン奏者(そうしゃ))
「音楽(おんがく)のまちの風景(ふうけい)」第(だい)2回(かい)は、きょうみなさんに聴いて(きいて)いただいた音楽(おんがく)の故郷(ふるさと)「イギリス(ロンドン)」。日本(にほん)にいらして17年(ねん)。日本語(にほんご)はもちろん、フランス語(ご)、ドイツ語(ご)、ラテン語(ご)、・・・とたくさんの言葉(ことば)に堪能(たんのう)で、お料理(りょうり)も上手(じょうず)な大和田(おおわだ)ルースさんに、ご紹介(しょうかい)いただきます。
―ルースさんが生まれ(うまれ)育った(そだった)のは、どんなまちですか?
ロンドンから南(みなみ)のほうに電車(でんしゃ)で30分(ぷん)くらい行った(いった)クロイドンということころです。ロンドンの町中(まちなか)より自然(しぜん)が多く(おおく)て、とても住み(すみ)やすいところです。ロンドンにすぐ出られる(でられる)ので、父(ちち)も毎日(まいにち)通って(かよって)いましたし、私(わたし)もロンドンのロイヤル・カレッジにいたときは、3年間(ねんかん)うちから通って(かよって)いました。うちから40分(ぷん)ほどのサリーというとても美しい(うつくしい)村(むら)には、ヴォーン=ウィリアムズの家(いえ)があります。
―音楽(おんがく)の勉強(べんきょう)を始めた(はじめた)のは?
7歳(さい)のとき、父(ちち)の友達(ともだち)がピアノを手放す(てばなす)ことになり、その中古(ちゅうこ)のアップライトピアノを3000円(えん)で両親(りょうしん)が買って(かって)くれました。だいぶ前(まえ)のこととはいえ、ずいぶん安い(やすい)ですよね。それでピアノのお稽古(けいこ)を始めた(はじめた)のです。10歳(さい)のとき、新しい(あたらしい)学校(がっこう)で仲良く(なかよく)なった友達(ともだち)二人(ふたり)が、学校(がっこう)の帰り(かえり)にケースをもってどこかに行くのをみて、興味(きょうみ)をもって一緒(いっしょ)に行って(いって)みたら、ヴァイオリンのレッスンに通って(かよって)いたんです。私(わたし)もやりたくなって、習い始め(ならいはじめ)ました。ピアノもヴァイオリンも両方(りょうほう)大好き(だいすき)でしたが、12歳(さい)のときに、ユースオーケストラ(こどものためのオーケストラ)に入って(はいって)、ほかの人(ひと)たちと一緒(いっしょ)に演奏(えんそう)する楽しさ(たのしさ)を覚えて(おぼえて)から、将来(しょうらい)はオーケストラで弾ける(ひける)ようになりたいなと思い始め(おもいはじめ)ました。イギリスではユースオーケストラが盛ん(さかん)で、学校(がっこう)にもオーケストラがあるんです。合唱(がっしょう)もやりました。毎週(まいしゅう)土曜(どよう)はミュージックスクールに通って(かよって)、日曜(にちよう)はユースオーケストラ、ピアノのレッスンもずっと続けて(つづけて)いましたから、いつも音楽(おんがく)の練習(れんしゅう)で忙し(いそがし)かったですね。あと同じ(おなじ)学校(がっこう)に通う(かよう)妹(いもうと)と一緒(いっしょ)にガールスカウトの活動(かつどう)もしていました。アウトドア派(は)なので、キャンプも大好き(だいすき)です。
12歳(さい)の頃(ころ)
|
ヴァイオリンを習い始め(ならいはじめ)て2年目(ねんめ)
|
|
私(わたし)(10才(さい))と妹(いもうと)のジュディー(6才(さい))
|
|
新学期(しんがっき)におそろいのユニフォームを着て(きて)。
|
ガールスカウト姿(すがた)
―音楽大学(おんがくだいがく)ではヴァイオリンを専攻(せんこう)したのですか?
ピアノとヴァイオリン両方(りょうほう)です。ロンドンの大学(だいがく)は、ダブルで受験(じゅけん)して、両方(りょうほう)のコースをとることができるんです。いまはオーケストラが忙しく(いそがし)てピアノを弾く(ひく)時間(じかん)がないのが残念(ざんねん)ですが、60歳(さい)になったらピアノを再開(さいかい)して、あとヴィオラも練習(れんしゅう)したいと思って(おもって)います。
ロンドンの象徴(しょうちょう) ビッグ・ベン
|
英国国会議事堂(えいこくこっかいぎじどう)の時計塔(とけいとう)。
|
―どんな音楽(おんがく)が好き(すき)でしたか?
小さい(ちいさい)ときからずっとロマンティックな音楽(おんがく)が好き(すき)でした。いまもチャイコフスキー、ブラームス、エルガーが大好き(だいすき)です。ピアノでもシューベルトやブラームスを弾く(ひく)のが好き(すき)でした。もともとスケールの大きい(おおきい)、シンフォニックな音楽(おんがく)が好き(すき)なのだと思います(おもいます)。
―イギリス音楽(おんがく)はメロディがきれいなものが多い(おおい)ですね。
一度(いちど)聴い(きい)たら忘れ(わすれ)られないメロディ、親しみ(したしみ)やすい音楽(おんがく)がたくさんありますね。きょう最後(さいご)に演奏(えんそう)する行進曲(こうしんきょく)「威風堂々(いふうどうどう)」第(だい)1番(ばん)は、毎年(まいとし)、夏(なつ)の音楽祭(おんがくさい)プロムスのラストナイト(最後(さいご)の公演(こうえん))で演奏(えんそう)される曲(きょく)で、イギリスでとても人気(にんき)があります。
―最初(さいしょ)にオーケストラに入った(はいった)のは?
ドイツのパッサウという町(まち)にあるオペラ劇場(げきじょう)のオーケストラです。小さい(ちいさい)ときに『サウンド・オブ・ミュージック』の映画(えいが)をみて以来(いらい)、ずっとオーストリア、ドイツに行きたい(いきたい)と憧れて(あこがれ)ていました。大学(だいがく)を出て(でて)から3年(ねん)ほどこどもたちを教える(おしえる)仕事(しごと)をしていましたが、どうしてもオーケストラに入り(はいり)たくて、ここのオーディションを受け(うけ)ました。オーケストラの仕事(しごと)のほかに、ピアノでいろいろな人(ひと)の伴奏(ばんそう)をしたのも楽し(たのし)かったです。主人(しゅじん)(東京交響楽団(とうきょうこうきょうがくだん)ホルン奏者(そうしゃ)の大和田浩明(おおわだひろあき)さん)との出会い(であい)もこのオーケストラで、彼(かれ)の伴奏(ばんそう)をしたのがきっかけです。
第(だい)1ヴァイオリンが6人(にん)しかいない小さな(ちいさな)オーケストラだったので、シンフォニーオーケストラに入って(はいって)、大編成(だいへんせい)のブルックナーやマーラーが弾きたい(ひきたい)とずっと思って(おもって)いました。ですから、東京交響楽団(とうきょうこうきょうがくだん)に入る(はいる)ことができて本当(ほんとう)に嬉しい(うれしい)です。
―日本(にほん)にいらした当初(とうしょ)はたいへんなことがあったと思い(おもい)ますが、なにに驚かれました(おどろかれました)か?
一番(いちばん)驚いた(おどろいた)のはお葬式(そうしき)です。日本(にほん)にきて少し(すこし)たったとき、主人(しゅじん)の父(ちち)が亡くな(なくな)ってお葬式(おそうしき)を出した(だした)のですが、イギリスは普通(ふつう)の家庭(かてい)では日本(にほん)ほど大きな(おおきな)セレモニーをしないので、とてもびっくりしました。日本(にほん)では結婚式(けっこんしき)も豪華(ごうか)ですよね。私(わたし)たちは、主人(しゅじん)のボーナスで買った(かった)自転車(じてんしゃ)で市役所(しやくしょ)に婚姻届(こんいんとどけ)を出し(だし)に行った(いった)だけです。イギリスでホームパーティはしましたが、セレモニーはしませんでした。
そして当時(とうじ)はまだ英語(えいご)の表示(ひょうじ)が少な(すくな)かったかったので、買い物(かいもの)に行って(いって)も、なにがなんだかわからなくて、間違った(まちがった)ものを買って(かって)きてしまうということがよくありました。忘れられない(わすれられない)失敗談(しっぱいだん)としては、喫茶店(きっさてん)でアイスコーヒーを頼んで(たのんで)、待って(まって)いるときに小さな(ちいさな)カップが出て(でて)きたので、お水(おみず)だと思って(おもって)飲み干して(のみほして)しまったら、ガムシロップだったんです。イギリスではアイスコーヒーを飲む(のむ)習慣(しゅうかん)がないので、ガムシロップをみたのは、そのときが初めて(はじめて)でした。
―イギリスは紅茶(こうちゃ)が有名(ゆうめい)ですが、ルースさんのおうちでもティータイムがありましたか?
そうですね。学校(がっこう)から帰る(かえる)と母(はは)と妹(いもうと)と一緒(いっしょ)にティータイムを楽しみ(たのしみ)ました。母(はは)が作って(つくって)くれたショートブレッド(ビスケット)やケーキを食べ(たべ)ながら。料理(りょうり)は私(わたし)も大好き(だいすき)ですが、母(はは)の味(あじ)が基本(きほん)になっているような気(き)がします。
―みなさんからの質問(しつもん)にお答え(おこたえ)します―
・ヴァイオリンはどうやったら上手(じょうず)になりますか? こつがあったら教えて(おしえて)ください。
むずかしい質問(しつもん)ですね(笑(わらい))。練習(れんしゅう)をたくさんやるのはもちろんですが、楽しく(たのしく)やることが大切(たいせつ)と思います(おもいます)。弾いて(ひいて)みたい曲(きょく)、好き(すき)なメロディを弾いて(ひいて)みるとか、楽しく(たのしく)弾ける(ひける)工夫(くふう)を考えて(かんがえて)みてください。
・このまえの演奏会(えんそうかい)でピチカート(ヴァイオリンの弦(げん)を指(ゆび)ではじいて音(おと)を出す(だす)奏法(そうほう))をみました。どうしてそういうふうに演奏(えんそう)するんですか?
作曲家(さっきょくか)が楽譜(がくふ)に書いた(かいた)からです。調べて(しらべて)みたら、ピチカートはルネサンス時代(じだい)からあったようですが、よく使われる(つかわれる)ようになったのは、パガニーニの時代からです。ピチカート、グリッサンドや、スルポンティチェロ(駒(こま)の近く(ちかく)で弾く(ひく))など、いろいろな奏法(そうほう)ができるのが、ヴァイオリンの楽しい(たのしい)ところだと思います(おもいます)。
・ヴァイオリンのみなさんは仲(なか)がいいですか? ライヴァルですか?
ライヴァルというより、仲間(なかま)です。一緒(いっしょ)に心(こころ)をあわせて演奏(えんそう)しないと、いい演奏(えんそう)はできないのですよ。ヴァイオリンは二人(ふたり)一組(ひとくみ)になって同じ(おなじ)譜面(ふめん)をみて演奏(えんそう)するのですが、コンサートごとに席(せき)が変わる(かわる)ので、いろいろな人(ひと)とコンビを組む(くむ)のが楽しい(たのしい)です。オーケストラの楽しさ(たのしさ)は、たくさんの人(ひと)が力(ちから)をあわせてひとつの音楽(おんがく)を作り出す(つくりだす)ことです。
質問(しつもん)を募集(ぼしゅう)します
次回(じかい)のテーマは「ウィーン」。ウィーンに留学(りゅうがく)したことのあるクラリネット奏者(そうしゃ)の小林利彰(こばやしとしあき)さんが登場(とうじょう)します。小林(こばやし)さんに聞いて(きいて)みたい質問(しつもん)を、別紙(べっし)に書いて(かいて)、「オーケストラヘの質問箱(しつもんばこ)」に入れて(いれて)ください。郵便(ゆうびん)、Eメールの場合(ばあい)は次(つぎ)の宛先(あてさき)にお願い(おねがい)します。締切(しめきり)は7月(がつ)30日(にち)です。
東京交響楽団(とうきょうこうきょうがくだん)「オーケストラヘの質問箱(しつもんばこ)」係(がかり)
〒212-8554 川崎市(かわさきし)幸区(さいわいく)大宮町(おおみやちょう)1310 ミューザ川崎(かわさき)5F
Eメール tokyosymphony@musicinfo.com
|