|
次に、バーがカスプと同周期で存在する場合(in-phase)を考える。この場合も位相以外は先の計算と同様の値を用いて地形を作成した。入射波は周期を6.0sに固定して波高を変化させて計算を行った。波高0.25m、0.5mのケースの計算結果を図−2.3.57に示す。
図−2.3.57 計算結果
(a)H=0.25m
(b)H=0.5m
図を見ると、(a)の場合では汀線凹部で離岸流が発生し、バーを通り越して流れが沖へと向かっているのが分かるが、その流速は非常に小さい。一方、(b)の場合では汀線凸部で離岸流が発生しており、out-of-phaseのケースと類似した流況となった。また流速に関してもほとんど差はない。
(a)、(b)両ケースの流況の違いもout-of-phaseの場合と同様に砕波位置の違いによるラディエーション応力の違いが影響していると考えられる。図−2.3.58にはDSX、DSYを示している。この場合もH=0.25mでは2次砕波がおきており、それによって汀線付近でDSX、DSYのピークが現れている。このピークがバー内の流れを引き起こしたものと考えられる。
図−2.3.58 ラディエーショの応力の比較
|
汀線凸部
|
汀線凹部 |
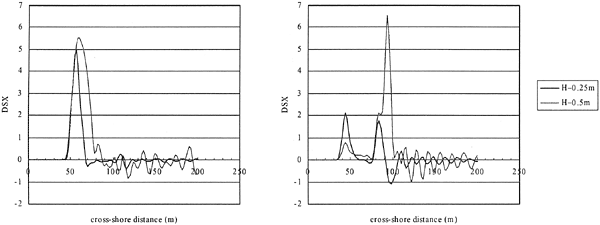 |
|
汀線凸部
|
汀線凹部 |
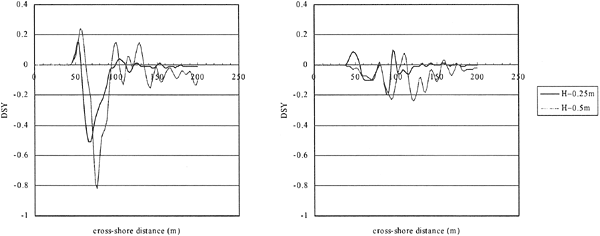 |
さらにin-phaseのバーが存在する場合の波向きに関する流れの影響を検討する。out-of-phaseの場合と同様に波高0.75m、周期6.0sの波を入射させ、波向きは10°、20°、30°として計算を行った。図−2.3.59に計算結果を示す。しかし結果としてはout-of-phaseの場合とほとんど同じ結果となり、波向きが20°になると沖方向の流れはなくなり、沿岸流が卓越する結果となった。以上の波向きの検討から離岸流の発生には波向きがほぼ直角入射の時に限られ、約20°が発生の限界である。
図−2.3.59 波向きによる流れの変化
(a)a=10°
(b)a=20°
|