|
図−2.3.53 波高分布
(a)H=0.25m
(b)H=0.5m
ここで前述(2)と同様に、バーの外側での流れのパターンと内部で循環が発生する場合のDSX、DSYについて検討する。図−2.3.54に(a)のケース、(b)のケースのDSX、DSYの分布を示している。
DSXについてみると、汀線凸部ではバーが存在していないためピークの値も同程度あり、波高の大きいH=0.5mでやや分布が広い結果となっている。一方でバーの存在する汀線凹部では両者に明確な差が生まれている。まずH=0.5mはバーで大きく砕波するため、約100mで大きな値をとるが、それ以降は波高が小さくなるために値が小さくなっている。H=0.25ではバー部分でやや砕波した際に少し値が上昇するが、汀線近辺でもう一度値が上昇しているのが分かる。これはバーでの砕波の程度が小さかったために汀線付近で2次砕波した影響と考えられる。DSYでは汀線凸部の値は若干の砕波位置の違いによる岸沖方向の変化はあるが、全体的な分布形状は類似している。しかし汀線凹部ではバーでの砕波後に汀線凸部と同様にH=0.25では再度ピーク値をとっている。またH=0.5mではバーの沖側でもDSYの比較的高い値が広く分布している。
このようにバーの内・外で両者のラディエーション応力の差があり、これらが両者の流況の差を発生させたと考えられる。
図−2.3.54 ラディエーション応力の比較
|
汀線凸部
|
汀線凹部 |
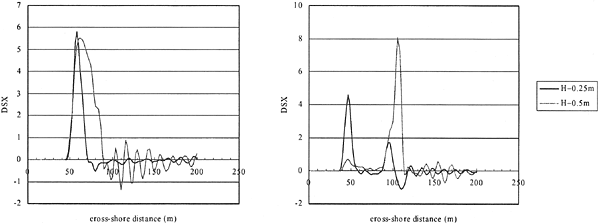 |
|
汀線凸部
|
汀線凹部 |
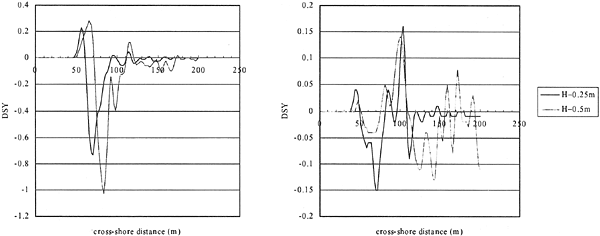
|
|