|
[参考1]
船体計画保全検査の実施のために必要なISMコードの要件
船体計画保全検査制度では、船舶所有者(船舶管理会社)がISMコードに適合する優良・適切な「船体の保守管理等体制」を有することが求められており、任意ISM証書の交付を受けていることが標準とされています(「検査の方法」4. 承認基準(1))。他方、何らかの事情により任意ISM証書の交付を受けていない場合にあっても、船体計画保全検査の審査の一環として、ISMコードに適合する優良・適切な「船体の保守管理等体制」を有することが確認されることになっています。
この場合の「船体の保守管理等体制」とは、船体の保守管理並びに船体の基準適合性(法令で定める船体に係る技術基準に適合することをいう。)の維持に直接影響する運航管理及び船員管理を指します。
すなわち、任意ISM証書を受有していない場合は、船体計画保全検査を実施するため、ISMコードに規定される要求事項のうち、船体の基準適合性維持に直接影響する範囲で必要最小限の安全管理システムを構築することも制度的には認められています。ただし、現実的には、こうした限定した範囲で安全管理システムを構築することは、却ってシステム構築のための作業やその後のシステム改善のための運用を難しくすることも想定されるため、特殊な事情でもない限り、推奨できるものではありません。
他方、任意ISM証書を受有している標準的な場合にあっても、船体計画保全検査を実施しようとする場合、船体の基準適合性の維持に直接影響する範囲について、ISMコードの概念や規定との関係で理解を深めておくことは有益と考えられます。
このため、ここでは船体の基準適合性維持に直接影響する安全管理システムの範囲について、解説します。
(1)船体計画保全検査に必要なISMコード要件の概念
ISMコードは、包括的・概念的に規定されているため、このうち、船体の基準適合性維持に直接影響するものを網羅的・明示的に列挙することは必ずしも容易ではありません。このため、通常、ISMコードに基づき運用される安全管理システムの概念のうち、関連部分を示したものを次ページの図1に示します。
また、通常、ISMコードにしたがって作成する安全管理規程関連文書(管理文書)のうち、船体の基準適合性維持に直接影響する規程等を例示したものを表1に示します。
|
図1:
|
船体計画保全検査に必要なISMコード要件の概念
|
|
(拡大画面:117KB)
|
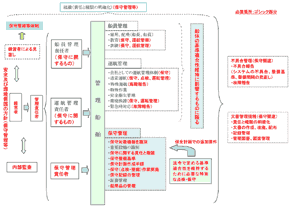 |
表1: 船体の基準適合性維持に直接影響する規程等の一例(取消線付きのもの以外)
(2)船体計画保全検査に不要なISMコード要件の概念
上記(1)とは逆に、ISMコードの規定を参照しながら、船体の基準適合性維持に直接影響しないと考えられる代表的なものを例示すると、以下のとおりです。
(例)
・会社の方針において、船体の保守に関係のない部分(コード2)
・要員の責任と権限の明確化のうち船体の点検、保守に関するもの以外のもの(コード3.2)
・管理責任者の責任と権限のうち船体の保守に関するもの以外のもの(コード4)
・船員の雇用、配乗(コード6.2)
・教育訓練のうち機器の取扱いなど船体の保守に関するもの以外のもの(コード6.3、6.4、6.5)
・船内業務計画の策定のうち、緊急時の連絡及び報告、荒天航海の報告、機器の取扱い要領など直接船体の基準適合性維持に影響するもの以外のもの(コード7)
例:貨物の取扱い、旅客に関する業務、特殊運航、特殊作業、船員の安全・衛生、船内廃棄物の管理要領、環境保護に関する事項(油水分離装置の取扱い要領を除く。)
・緊急事態への準備のうち、緊急事態発生後の対応、緊急時の行動に関する訓練及び演習等直接船体の保守に関係のないもの。(コード8)
・重要機器の識別及び特別な保守(コード10.3)
・文書管理のうち船体の保守に関するもの以外のもの(コード11)
・証書、検証及び監督(コード13)
入渠時における点検・整備内容、注意事項等の例示
| ※1: |
必要に応じて、写真撮影、外板展開図を利用することが望ましい。 |
| ※2: |
発錆状況の点検
発錆が無くても防汚塗料(A/F)が剥離している場合は、前回塗装作業にスウェット状態にあった等、塗装の問題又は防錆塗料(A/C)と防汚塗料(A/F)の密着性に問題があるケースがあるので、ペイントメーカーと下地処理法を含めて十分打ち合わせる必要がある。 |
| ※3: |
二年以上入渠しない場合は全数新替えが望ましい。 |
|
|