|
4. 現行機関計画保全検査の導入経緯
4.1 機関計画保全検査の制定時の背景
平成9年9月に船舶安全法の一部改正が行われ、船舶検査証書の有効期間が4年→5年になった。この際、併せて、船舶検査の方法も船舶所有者の保守管理が良好なものについては事情聴取及び書類確認により直接検査を一部省略できることとなった。
具体的には機関の計画的検査として、継続検査に加えて計画保全検査が導入された(その後、平成15年6月に一部改正)。また、その他、補機関係について検査官による直接検査を一部省略することとなった。
この船舶安全法の一部を改正した理由における技術的観点は次のとおり。
(1)船舶製造等に係る技術の進歩
(1)設計技術の進歩
a. コンピューターを利用した精密強度計算の実現
b. 損傷データの蓄積及びその詳細解析による損傷防止対策の確立
(2)材料技術の進歩
a. 船体構造における耐食アルミニウム合金材の使用
b. クランク軸等における特殊鋼(Cr-Mo鋼等)の使用
(3)溶接及び工作技術の進歩
a. 自動溶接機による溶接を広範囲に用いることによる溶接品質の向上
b. 数値制御式自動切断機等の導入による工作精度の向上
c. 特殊な工作機械(研磨及び切断)の開発による高精度の軸受の製作が可能となった。
(4)船舶保全技術の高度化
a. 耐食塗料の普及によるバラストタンクの腐食防止
b. 電気防食装置の普及による外板の腐食防止
c. 油潤滑式船尾管軸受の普及によるプロペラ軸の腐食防止
(5)検査技術の進歩
a. 超音波探傷機及び磁気探傷機等の活用による材料内部欠陥の検査技術の確立
b. X線探傷機の活用による溶接線内部欠陥の検査技術の確立
製造及び工作技術の進歩により以下のとおり船舶の信頼性が向上した。
(2)船舶の信頼性の向上
(1)構造を起因とする船体損傷率が漸減
(2)船舶とう載機器の信頼性が向上
a. オイルショック以降の燃料油の低質化、乗組員減少による船上における保守管理が簡素化したにもかかわらずクランク軸折損等の重大事故が減少し主機の信頼性が向上した。
b. 主機の事故件数が減少したことに加え、多数搭載されている電気機器、補機類の故障件数も減少しており、これらの機器の信頼性が技術的に成熟の域に到達。
(3)(1)及び(2)により、ハードを起因とする海難事故件数は安定的に低い水準にあり、長期的には漸減傾向にある。これらは機器の信頼性に加え、船舶所有者の自主整備等の保守管理が有効に機能してきたためである。
(1)従来の検査
管海官庁が行う船舶の機関の検査は、船舶安全法施行規則及び同告示により定期的検査の準備が規定されているほか、当該船舶の現状及び保守が良好なものついては主機及び補機類に係る定期検査をそれぞれ5年を超えない間隔で、かつ、全部が5年以内に結了するように定期的に順次行う継続検査を認めている。当該継続検査は計画表に基づき解放を行い、すべての項目にわたり検査官による直接検査を原則としている。
(2)機関計画保全検査の導入
上記船舶安全法の一部を改正した理由で明らかなように、機器の製造技術、信頼性及び耐久性の向上、更には船舶所有者による保守管理の有効性が確立された現在にあっては、機関の検査項目のすべてを直接検査する必然性が低くなってきた。また、運転状態に応じた機器類に対する適切な整備(過剰整備の回避)を考慮する必要が生じてきたことから、ある一定の基準(ISM的保守整備等)を満たす船舶所有者は当該船舶の運航状態に応じた時間管理を基とする適切な整備要領を定めることとし、それらの一部を自主整備とすることを認める計画保全検査を導入することとした。
【参考】NK鋼船規則への機関計画保全検査の導入理由(平成7年2月)
従来から採用されている機関の継続検査に対し、最近ではこれをより合理的に発展させた方式として機関の計画保全方式による検査が採用されつつある。機関計画保全方式は機器の運転時間をベースに機関継続検査を発展させたものである。
(平成7年NK会誌 抜粋)
機関の検査の現状(貨物船)
|
(拡大画面:53KB)
|
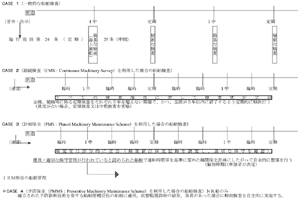 |
機関の検査の現状(旅客船)
|
(拡大画面:45KB)
|
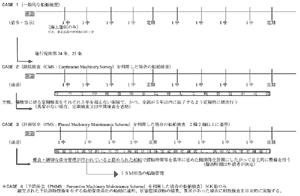 |
|