|
2.1.3 解体廃棄物の輸送計画
現在、運転中に発生する低レベル放射性廃棄物の輸送と埋設処分は軌道に乗り、地元はもちろん一般社会からも安心感をもって見守られている。
原子力発電所の解体廃棄物として発生する低レベル放射性廃棄物は、埋設処分の上から、放射能レベルの比較的高い低レベル放射性廃棄物(L1)、放射能レベルの比較的低い低レベル放射性廃棄物(L2)および放射能レベルの極めて低い低レベル放射性廃棄物(L3)に分類されるが、商業用原子力発電所から発生する放射性廃棄物のうち、これまでに埋設処分が行われた実績があるのは原子炉運転中に発生する低レベル放射性廃棄物のみであり、上記の中間に分類されるものに相当する(L2相当)。原子力発電所の解体により発生する低レベル放射性廃棄物はこれらのどれかに区分されるが、安全輸送の観点からは放射能濃度及び総放射能量によってIP型輸送物またはB型輸送物に分類される。これらの輸送物の特徴としては、大型であり、重量物になるとともに、短期間に比較的大量の輸送物を運搬する必要が生じることなどがあげられる。更に、廃止措置に際しては、大口径配管やタンク類を輸送容器や処分容器として使用する方法も検討されている。
これらの輸送に際しては、特別措置の適用を想定したシステムを構築する方法と従来と同じ方法で実施する方法とが考えられる。合理的な輸送を追求するためには、その安全性を担保しつつ、法令の改正を視野に入れて検討を進めることが必要であり、現実的には、安全確保を最重要課題とするが、輸送コストの低減化を目指し、短期間に大量の輸送物を運搬できる、より合理的な輸送システムを模索し、構築することが重要である。
東海発電所の解体放射性廃棄物、即ち、L1廃棄物、L2廃棄物、L3廃棄物およびガスダクト一体廃棄体輸送物などの発電所から埋設処分施設までの輸送システム案を表2.1.3-1に示す。これらの中でL3廃棄物の発生量は約8,100トンと推定されている。この処分場所は、発電所サイト内、あるいは、サイト外のいずれに設置されるかについては検討されているところであるが、今後の安全輸送を幅広く検討するために、事業所外埋設、事業所外運搬についても必要に応じ検討する。
表2.1.3-1 東海ガス炉解体廃棄物輸送システム案
| 廃棄物 |
発電所内 |
船積港 |
海上輸送 |
荷卸港 |
埋設センター |
[黒鉛ブロック]
(放射能レベルの比較的高い低レベル廃棄物、IP-2型輸送物) |
廃棄体作成:モルタル詰処分容器に遠隔でブロックを収納、モルタル充填、蓋部閉め線量率・汚染測定―廃棄体確認検査
1.3mL×1.3mW×1.3mH、質量6t、670個
輸送物作成:遮へい付輸送容器に2廃棄体装荷、蓋閉め、線量率・汚染測定、緩衝体、3.5mL×1.3mW×1.7mH、質量50t、330個 |
輸送物作成建屋クレーン(55t)下に車両、キャリア又はトレーラーに2輸送物積載、吊具準備
既設ジブクレーンで船積 |
499GT型貨物船注1)、固縛は船倉床に仮設装置、立入制限区域及び巡視通路を確保
船倉床(22mL,10mW)、載貨質量(1,300t)から、20輸送物を積載17回輸送、荷役陸送は1日作業 |
岸壁150tクレーンで荷卸(吊具準備)
既存キャリアに2輸送物積載
車両表面・1m点の線量率測定 |
輸送物取卸、廃棄体取出し、検査の専用スペース、天井クレーンを準備
埋設場所への移送用車両 |
[炉内構造物・挿入物]
(放射能レベルの比較的高い低レベル廃棄物、B型輸送物) |
廃棄体作成:処分容器使用のほかは同上、1.3mφ×1.3mH、質量13t、個数900個
輸送物作成:円柱のB型輸送容器使用、1個の廃棄体装荷のほか同上、
輸送架台、2.4mφ、質量55t、900個
発送前検査 |
同上 |
同上
18輸送物を積載、50回輸送
荷役陸送1日作業 |
同上 |
同上 |
[放射化コンクリート]
(放射能レベルの比較的低い低レベル廃棄物、IP-2型輸送物) |
廃棄体作成:処分容器使用のほかは同上
3.2mL×1.6mW×1.1mH、ツイストロック(吊り金具)、質量16t、100個
輸送物作成:角型輸送容器使用のほか同上廃棄体の輸送容器装荷にスプレッダー準備
質量46t、100個 |
同上 |
同上
20輸送物を積載、5回輸送
荷役陸送1日作業 |
同上 |
同上
天井クレーン下にスプレッダー準備 |
[汚染金属その他雑廃棄物]
(放射能レベルの比較的低い低レベル廃棄物、IP-2型輸送物) |
廃棄体兼輸送物作成:兼用容器詰、モルタル充填、蓋閉め、線量率・汚染測定
3.2mL×1.6mW×1.1mH、ツイストロック(吊り金具)、スプレッダー準備
質量12-21t、1,300個 |
同上
スプレッダー準備 |
同上
2段積、60個積載、22回輸送
荷役陸送2-3日作業 |
同上 |
同上 |
[ガスダクト一体]
(放射能レベルの比較的低い低レベル廃棄物、IP-2型輸送物) |
廃棄体兼輸送物作成:ガスダクト直管部に吊金具取付け、雑固体廃棄物を収納、モルタル充填、両端部溶接、線量率・汚染測定
緩衝体、2.2mφ×6mL、18個 |
輸送物作成建屋クレーン共用なら質量を限定、キャリア又はトレーラーに1輸送物積載吊具共用化、
既設ジブクレーンで船積 |
同上
9個積載、2回輸送、荷役陸送1日作業 |
同上
吊具共用化 |
同上 |
[極低レベル雑廃棄物]
(放射能レベルの極めて低い低レベル廃棄物) |
IAEA安全輸送規則の見直し提案中。これが採用され、我が国規則に取り入れられれば核燃料輸送物としないで輸送が可能 |
|
|
|
|
|
注1):全長約70m、幅13m、総トン数499トン、載貨重量約1,500トン
2.2.1 IAEA輸送規則
危険物の国際輸送については、国連(United Nations,UN)がすべての輸送モードに共通であること、および、適切な輸送容器に収納すれば危険物も一般貨物と同様に運送できることを目指して、危険物輸送に関するモデル規則を勧告している。この規則は、危険物輸送に関する国連勧告(国連モデル規則、The United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods. 通称"Orange Book")と呼ばれ、国連危険物専門家委員会(The United Nations Committee of Experts on the Transport of Dangerous Goods,UNCETDG)が策定している。
危険物はClass1からClass9の9種類に区分され、そのうちのClass7が放射性物質である。放射性物質の輸送に関する規則の策定は、国連から国際原子力機関(International Atomic Energy Agency,IAEA)に委託され、IAEAの輸送安全基準委員会(Transport Safety Standard Committee, TRANSSC)で加盟国のコンセンサスに基づいて策定および改定されている。この規則が、放射性物質安全輸送規則(Regulations for the Safe Transport of Radioactive Material,TS-R-1)である。IAEAでは、輸送規則TS-R-1のほかに、助言文書(Advisory Material for the IAEA Regulations for the Safe Transport of Radioactive Material,TS-G-1.1)、緊急時対応計画(Planning and Preparing for Emergency Response to Transport Accidents Involving Radioactive Material,TS-G-1.2)などのガイド文書またはドラフトを策定するなどして、放射性物質輸送を支援している。
IAEA輸送規則TS-R-1は、輸送物をその収納物の性状、放射能量または濃度に応じて、A型、B型、IP型、核分裂性等に分類し、その分類に応じた要件を輸送容器の設計・製作等および輸送方法に課すことにより、他の危険物と同様の輸送安全を確保している。
IAEA輸送規則は、国連からの委託を受けて1961年に初版を策定以来、1973年、1985年、1996年に大改定が行われてきたが、1999年以降は他の危険物規則とあわせて2年ごとに改定が行われるようになった。遇数年の7月頃までに加盟各国からの規則および助言文書の改定提案が集められ、その年の秋の見直し会合(Review Panel)で選別された結果を奇数年春のTRANSSCで承認した後、選別された提案は加盟国の120日レビューに付され、そのコメントおよび提案国の対応を奇数年秋の見直し会合で審議して規則改定案をまとめる。それを遇数年春のTRANSSCで審議、承認した後、必要に応じて上部委員会、理事会の承認を得て発行(国連へ答申)される。
国連はIAEAからの答申を受けて、他の危険物に関する規則とあわせて国連勧告を改定する。
解体廃棄物等を含む放射性物質の国際輸送は、基本的にはこの国連勧告を反映した輸送モードごとの規則(輸送モーダル規則)に準拠して行われる。
2.2.2 IMO/IMDG/INFコード
海上における危険物輸送は、国際海事機関(International Maritime Organization,IMO)が定める国際海上危険物規定(International Maritime Dangerous Goods Code,IMDGコード)に準拠して行われる。IMDGコードは、国連勧告(国連モデル規則、Orange Book)に海上輸送特有の事項を追加したものであり、放射性物質の輸送に関する規定については、基本的にはIAEA規則と同等のものである。
IMDGコードは、海上人命安全条約(International Convention for the Safety of Life at Sea,SOLAS条約)の2002年5月24日の改定で(Resolution MSC.123(75))、附属書第VII章「危険物の運送」Part A のRegulation 3(Requirements for the carriage of dangerous goods)として「梱包された形態の危険物の運送は、IMDGコードの関係する規定に適合しなければならない」との規定により、締約国に義務化された。各国は、自主的には2003年1月1日、強制的には2004年1月1日までに取り入れることとされた。
一方、SOLAS条約附属書第VII章Part Dには「容器に収納した照射済核燃料、プルトニウム及び高レベルの放射性廃棄物の船舶による運送のための特別要件(Special requirements for the carriage of packaged irradiated nuclear fuel, plutonium and high-level radioactive wastes on board ships)」として一部の放射性物質を運送する船舶の構造等の要件を定めている。この規定は、策定時の旧称"Code for the safe carriage of irradiated nuclear fuel, plutonium and high-level radioactive wastes in flasks on board ships"のときから、"irradiated nuclear fuel"の頭文字をとってINFコードと通称されている。本コードも上記と同様にSOLAS条約締結国に義務化されている。
2.2.3 我が国の規制体系と輸送関連規則
我が国の放射性物質に関する輸送規則も、基本的にはIAEA輸送規則をベースとしているが、法体系の関係上、輸送物が核燃料物質等輸送物か、放射性同位元素輸送物か、また、輸送モードが陸上輸送(自動車、鉄道)か、海上輸送(船舶)か、航空輸送(航空機)かによって、多少の違いが生じている。
原子炉施設解体廃棄物の輸送を想定した場合、核燃料物質等輸送物の陸上輸送と海上輸送に該当することから、主に以下の法規に基づいて実施することとなる。
・陸上輸送
− 原子炉等規制法(第59条の2および3等)および関係法令
− 核燃料物質等の事業所の外における運搬に関する規則および告示
− 核燃料物質等車両運搬規則および告示
・海上輸送
− 船舶安全法(第28条等)および関係法令
− 危険物船舶運送及び貯蔵規則および告示
− 船舶による放射性物質等の運送基準の細目等を定める告示
これらのうち、海上輸送についてはIAEA規則を取り入れたIMDGコードのSOLAS条約締結国への義務化がなされているため、IAEA規則の改定がほぼそのまま一定期間後に我が国に取り入れられる。一方、陸上輸送についてはIAEA輸送規則を受けた国連モデル規則は勧告であり、多くの国はIAEA輸送規則に基づいて国内規則を規定している。このため、陸上輸送と海上輸送の間に規定の相違や取入れ時期の相違が生じることがあり、注意する必要がある。
これらの相違は、我が国で2005年に予定されるIAEAによる放射性物質安全輸送評価サービス(Transport Safety Apprasal Service,TranSAS)等の機会を通じて整合性の向上が図られると期待され、今後、IAEA輸送規則がよりタイムリーに、かつ、陸上輸送の規定に取り入れられることになると考えられる。
2.3.1 IAEA輸送規則の課題と対応
本項では、原子炉施設解体廃棄物の輸送について、IAEA輸送規則への適合の観点からの課題とその対応を検討する。
(1)LSAとしての条件である「全体に分布」の件
解体廃棄物のうちの多くの物は、IAEA輸送規則で定める低比放射性物質(Low Specific Activity,LSA)に該当する。LSA-IIでは放射性物質が全体に分布していること、LSA-IIIでは放射性物質が全体に均一に分布していることが要件となっており、1m3以上の輸送物では10分割した各部の放射能濃度のバラツキが10倍以内とされている。
しかし解体廃棄物の場合、生体遮へいコンクリートや黒鉛ブロック等のようにその配置などから放射化傾向に一定の法則があるので、解体部分の推定平均比放射能の最大値がLSA-IIの比放射能限度である10-4A2/gを超えないならば、バラツキが10倍以上であっても安全上はなんら問題ない。このように、その廃棄物の履歴や条件により安全性が十分合理的に説明できる場合は、バラツキが10倍以内であることの確認は不要であり、我が国はこの点をIAEA安全輸送規則の解説として助言文書の226.14項に明記することを提案した。当該提案を資料1に示す。
本提案は2002年9月の見直し会合で問題なく受け入れられたが、助言文書の最新版ドラフト(2003年改定及び2005年改定の両方を加えたもの)の226.14項には反映されていない。
(2)一般の試験条件について
IP-2型輸送物として区分される輸送物の質量が通常15トン以上(一部は12〜15トン)と想定されており、IP-2型輸送物の一般の試験条件は次のとおりである。
(1)落下試験 0.3m高さからの落下
(2)積み重ね試験 質量の5倍
その際の適合基準は、
(1)輸送物表面の線量率の著しい増加がないこと(最大線量率は2.4mSv/h)
(2)放射性物質の漏えいがないこと
であり、解析や試験により廃棄体容器および輸送容器の健全性を確認する。
一方、炉内構造物や挿入物を収納するB型輸送物の一般の試験条件は、次のとおりである。
(1)水の吹付け試験
(2)落下試験 0.3m高さからの落下
(3)積み重ね試験 質量の5倍
(4)貫通試験 直径3.2cm、質量6kgの丸棒を1m高さから落す
(5)環境試験 38℃の環境に1週間置く
その際の適合基準は、
(1)輸送物表面の線量率の著しい増加がないこと(最大線量率は2.4mSv/h)
(2)放射性物質の漏洩量 A2×10-6/hを超えないこと
(3)表面温度が専用積載で85℃以下であること
(4)表面汚染が密度限度以下であること
である。解析や試験により廃棄体容器及び輸送容器の健全性を確認する。また、処分・輸送兼用容器、特に、大口径配管などを処分容器として内部に廃棄物を収納して固化し、そのまま輸送容器も兼ねる場合に、輸送物の健全性をどのように立証するかについては今後の検討を必要とする。
(3)特別の試験条件について
特別の試験条件はB型輸送物に課され、その条件は次のとおりである。
(1)落下試験 9m高さからの落下
(2)貫通試験 直径15cm、長さ20cmの軟鋼棒上に1m高さからの落下
(3)耐火試験 38℃の環境で800℃、30分
(4)浸漬試験 深さ15mの水中に8時間
その際の適合基準は、
(1)輸送物表面から1mの点で10mSv/hを超えないこと
(2)放射性物質の1週間当りの漏えい量がA2値以下であること
であり、解析や試験により廃棄体容器及び輸送容器の健全性を立証する必要がある。ただし、収納廃棄体の放射能は大半が放射化、あるいは、固定汚染であり、モルタル充填固化されているので、密封機能の損傷に伴う放射能の漏えい率を評価するための基礎データの確立が重要となる。更に、廃棄体容器と輸送容器に課される密封機能の要件については今後の検討対象である。
これら、試験条件も含めた輸送物ごとの技術要件への適合性の検討検討を表2.3.1-1にまとめる。
(4)核分裂性輸送物の適用除外要件について
解体廃棄物にはごく微量の核分裂性物質や特定の減速材(重水素、ベリリウム等)が含まれることがある。これらが微量の場合輸送物または運搬物の未臨界性に与える影響は無視できることから、IAEA輸送規則では672項に適用除外規定を設けて、これらのものが核分裂性輸送物とならないよう配慮している。
この適用除外規定については、1996年改定版の策定時より様々な議論が続いており、特に将来の解体廃棄物等の大量輸送を念頭においた規制強化・緩和両面での提案が検討されてきている。米国からは従来の量的規制に濃度規制を加える提案が出され(汚染土壌を列車で大量輸送する場合の緩和を目的としているといわれる)、前回改定サイクルでは審議未了となったが、本年5月に関係国の参加による専門家会合(Consultant Service Meeting)CS-41を開催して今回改定サイクル向けの提案骨子をまとめ、9月の輸送規則見直し会合で他提案も取り込んだ共同提案をまとめている。CS-41には我が国の専門家も参加しており、解体廃棄物輸送の観点から今後とも本規定の改定動向を注視する必要がある。この共同提案を資料2に示す。
また、我が国は、低レベル放射性廃棄物の大量輸送に影響を与えるものとして、前々回改定サイクルで適用除外質量を算出する際の特定減速材のうちの重水素量の計算において、天然重水素は除外するよう提案して各国の賛同を得て2003年版規則本文に取り入れられたが、今回サイクルでは微量のベリリウムも除外できるとの提案をし、9月の見直し会合では広範な計算結果を示して濃度0.1%以下のベリリウムは除外できるとの修正提案をまとめた。この提案を資料2にあわせて示すが、助言文書に記載された「日本の検討」を公開文献としてまとめる必要がある。
表2.3.1-1 各廃棄体および輸送物の
技術基準への適合性とその確認方法等について(1/2)
|
(拡大画面:96KB)
|
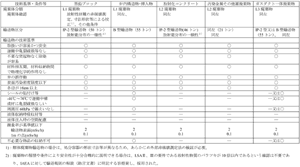 |
表2.3.1-1 各廃棄体および輸送物の
技術基準への適合性とその確認方法等について(2/2)
|
(拡大画面:111KB)
|
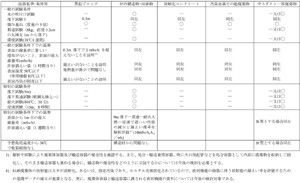 |
|