|
THANKS!
味の明太子の(株)ふくやさんから明太子を提供していただきました。ありがとうございました。
ワールドカルチャーフェスティバル当日は、取材にもきてくれました。
社内報「THEふくやジャーナル2004.01 No.191」
開催に向けての準備や当日の様子は、福岡市NPOボランティア交流センター
あすみんの情報誌でも紹介されました。情報誌「あすみんVol.14」
|
(拡大画面:188KB)
|
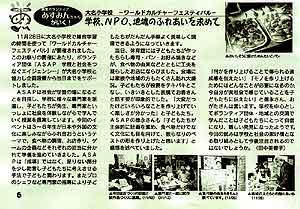 |
『地域や専門家とともにつくる授業』
有田小学校・・・
藤本英樹先生・佐々木妙先生・西田純子先生〈担任〉
野中佳昭先生〈総合学習担当教諭〉
専門家・・・
益田啓一郎さん〈地図の専門家〉
ASAP・・・
おがたたかひろ・小河けい・林由季子
有田校区では、地域と学校が連携して、専門家が参加する授業に継続的に取組んできました。これまでの取組みを振り返りながら、H15年度の取り組みの反省もかねて『地域や専門家とともにつくる授業』をテーマに座談会を開き、それぞれの立場からのお話をうかがいました。
ASAP:有田校区では、地域や専門家との授業が3年目になるわけですが、まずは、今年度の取り組みについてお聞かせください。
藤本:地域との関わりということで、まちづくりをテーマに継続的に取り組んできましたが、そろそろいい意味での脱皮が必要だな、と感じています。もっとテーマを広げてもいいかと・・・。ひとつのプロジェクトが終わってから、「もっとこんなことがしたかった」と子どもからやりたいことが出てくるんですよね。
ASAP:子どもたちにとっては初めての取組みですし、それが終わったからこそ、あらたにやりたいことが出て来たのかも知れません。今まで有田小では、毎年6年生がやってましたが、同じ子どもたちが4年生から始めて5年6年と、継続していくと、発展していくかもしれませんね。
益田:毎年、同じ授業企画でもいいのでは?
ASAP:それもいいですよね。同じ企画でも違うものができるでしょうし。
西田:2度目になると前にやってないもの、あたらしいことをやらなければいけない!と思ってしまうんですよね。クラスを3つに分けた(※1)のは、大変でした。(時間も方向性も)全ての授業を調整するのが負担でしたね。でも、いつものクラスをバラバラにすることで、子ども達には効果もあるんですよね。専門家が関わることで作品の完成度が高くなって、そこは子ども達も満足していました。
※1: 子どもたちが希望のコースを選択できるように日頃のクラスではなく選べる3コースとしました。
益田:作品が出来上がると達成感は違うでしょうね。
西田:でも、地域、専門家の方、ASAP、学校と(関わるところが多いから)事務連絡には負担がかかりましたね。
藤本:専門家と教師、ASAPの間の連絡系統をシステム化していくのは必要でしょうね。一方で専門家と教師でもっと直接にやり取りしたい思いもありましたね。
ASAP:難しいんですよね。間にクッションがあったほうがいい場合と直接やり取りしたほうがいい場合があって。やり方はひとつに決められない・・・
藤本:そうなんですよね。
ASAP:インターネット上に連絡用掲示板をつくるのはどうですか?
益田:連絡の手段がインターネット上の掲示板だと見ている人見ていない人が出てくるから、それはそれで問題が起きるかもしれませんよ。
西田:教師側が専門家の方の専門性をよく分かっていなくて、充分に活かせていないところもありました。「ものづくり」の場合は子どもたちも分かりやすくて(専門家との)関わりが深くなった気がします。お話を聞くだけの方の場合が難しい。いいお話をされているのだけれど、聞いている時にはよく分からない。
藤本:子ども達のアイデアや問いに教師の現実的な感覚で答えて終わってしまうんですよね。専門家が関わっているのに教師と専門家の関係になってしまって、子ども達と専門家の関係はできていない。その間をつなぐ人がいるといいかもしれませんね。
ASAP:学生なんかが参加するのは、どうですか?子ども達のチームリーダーみたいな感じで。子ども達と一緒に専門家から学ぶような。もしくは子ども達のグループの中でリーダーを明確にしていくとか?
益田:それは、あるかもしれませんね。何に主眼を置くかにもよると思うんです。チームを組んで何かをやることとかリーダーシップを身につけることを目的にしていいと思うんです。自然とまとまってリーダーが決まって、細かいことが得意な子は黙々と作業をして・・・そうして自然に役割分担のできたチムができればいいと思う。そういうグループは理想だし、そういうグループは作品も良かったと思う。
藤本:リーダーばかりのグループもダメですね。チーム分けは難しいですよ。
ASAP:6年生は理解度とか能力の差が大きいですからね。ものづくりには、粘り強さも大切だし、黙々とやる子もいるでしょう。
佐々木:いました、そういう子。休み時間もひとりでも作業を進めて、完成させようとする子。でも、完成すると、その子だけじゃなくてみんなうれしいんですよね。
西田:そういう役割分担は、自然と出来ていた感じがしますね。
益田:だったら正解ですよ。
野中:確かに作品の完成度は高かったし、その点では本当に良かったすごかったと思っていますけど、やはり大変でしたよ。6年生の先生方はかなりの時間を・・・休日も使っていました。良くできた成果物を求めるのはやりがいはあるのですが、(あくまで学校としては)あらかじめ決まった時間枠の中での授業計画が必要ですし、総合のねらいからすれば、完成させることより過程が大事で、時間がきたらある程度でやめても過程が評価できれば、学校としてはそれでいいわけです。
ASAP:それでも有田校区は、地域からの資金面での援助や授業のときにも呼びかけに応じてサポートしてくれます。これは、他の地域では簡単なことではありません。ただそのためには地域に対して何らかの成果物が求められますし・・・。
西田:地域が何をやってるのか、教師が知らない・・・というところはありますね。子ども達のほうは知っているのかもしれませんが。保護者も意外と地域のことを知らないみたいなんですよね。子ども達の発表をみて「始めて知った」「知らなかった」と感想を書いていました。
ASAP:こういった取組みへの保護者の理解はどうですか?
藤本:こういった取組みというより、「総合」事体への不信感があります。なんか楽しい時間と思われている。けれど、こういった取組みを継続していくことで理解してもらえるようになると思う。
ASAP:今後やってみたいテーマや一緒に授業をしたい専門家はいますか?
益田:子ども達にラジオ番組をつくらせているところもありますよね。
佐々木:でも、教師がやりたいことより子どもたちがやりたいことをやりたいですね。
藤本:校庭に秘密キチづくりとか、やりたいですね。そこに泊まったりして。
ASAP:有田の草花で草木染めなんてどうですか。それを商品化することも考える授業。
西田:商品化!
ASAP:福岡には、子ども達が自分たちで竹炭をつくって商品として売る、ということをやっている学校もあります。
益田:商品化なら作業所と連携したりするやり方もありますね。
ASAP:いろいろな方向にひろげていくことができそうですね。
佐々木:今回の取組みで福祉がテーマだったけれど福祉といっても色々なことがあって、とても広いテーマで難しかった。
ASAP: 福祉も安全も環境もそれぞれに大きなテーマでもっとテーマを絞ったほうが、考えやすくなるかもしれませんね。盛りだくさんにしすぎないほうが、いい案がでやすかったり、考えやすかったりして、取組みやすいでしょうね。テーマ選びももっと考えていきたいですね。
『地域や専門家とつくる授業』
大名小学校・・・
前田友子先生〈3年担任〉土井三幸先生〈4年担任〉浦 美保子先生〈5年担任〉木下宏仁先生〈6年担任)楠原貴己子先生(少人数指導担当)佐木玲子先生(弱視学級〉
専門家・・・
副島信次さん〈福岡市経済振興局コンベンション課主査・アジアマンス担当〉
ASAP・・・
おがたたかひろ・徳永昭夫
大名小学校では、3年生から6年生までが、専門家の力をかり、協力してフェスティバルを作り上げました。またフェスティバル当日は地域の方にもたくさん来ていただきました。『地域や専門家とともにつくる授業』をテーマに、今回の取組みの反省と今後の課題について、それぞれの立場からのお話をうかがいました。
ASAP:今回のプロジェクトを終えての印象などをまず教えていただけますか。
土井:ほんとに自分が楽しめました。自分もすごく興味をもって取り組めました。
佐木:(1年、5年各1人弱視児童有)K君(5年生)に話を聞いたら「いろんな人と関わりが持てたからよかった」と。ひとつのものをみんなと一緒に作り上げる経験をここでできたのが彼にとってすごいよかったかなと思います。
楠原:学園祭の企画を経験した人とか、韓国料理だったらそういう人を、子供たちのニーズにあった人を連れてきて下さったのはさすがコーディネートの方たちだなと。
前田:それと明太子をあれだけもらってくださったりね(笑)。やはり専門家の人はすごいなと、私たちじゃ発想できないことをしてもらった。ただそれを子供たちにどう活かすか、とても悩んだんですね。私が興味深かったのは「お茶どうね?」と言ったときに、今まで3時間話し合って、ご飯とパンとおまんじゅうだったのにそれはどうなっているんだ? ということが子供側から出てこなかった。それと私は自分のクラスの子の評価ができないんですね。
楠原:私たちが課題の持たせ方にこだわってないからそういうことになったので、評価のところまで打合せを教師側で持って行くことかなと思ったんですね。
木下:ある程度方向性までを指導していく濃さが3・4年と5・6年では違うのかなと思ってました。5・6年生のほうは子ども達がこだわる部分を大事にしていきたかったので、多岐にわたっているけど、自分達のしたいことを計画からしていったという達成感はあったと思う。フェスティバルだから活動的な深まりとか成功するとかっていう目に見える部分での成長と、目に見えない部分、内面的な成長を教師としては見守っていく必要があります。
楠原:ゴールを集会に持ってきたのが失敗だったかなと思います。やっぱり時間が短かったからですね、ASAPの主導で、やはりこっちから投げ渡してしまったところもあって。
ASAP:僕も完成度をもとめるよりも、それを達成するだけではなくてその過程をほんとにそれでいいのか、気付いてほしいなと思って。
土井:今回、5、6年の食事を作ることと、3、4年生で食事を作ることの活動の質の差が見えなかったんですよ。追求の深さとか、もう一回考えて行かなくてはいけないことかなと思いますね。
前田:5・6年が話し合ったというものを3・4年におろして、3・4年は福岡市のものをPRしてくれということだった。だからもしお茶だったら八女茶とか、そこに立ち戻ったり。思うと、そのときは錯綜してたんですよ。子供に比べて大人たちの思いが多かったかなと反省してます。
ASAP:今回、お金のやりとりをしない状態だったということだけが、引っかかっていて。リアルに生きていくための大事なことと、思ったんですけどね。
浦:一番の感想は、子供たちが一生懸命とりくむ姿を目にすることができたこと。学校の職員だけではあそこまでできなかった。ただ足りなかった点は、まず年間の計画を私たちが持ってなかったということ、子供にいたっては、先生例年と全然違うけどいったい僕達どこまでやったらいいんですかって。来年はうまくやれそうだからもう一回させて欲しいという感想が強く出てます。もう一つ反省すべき点は果たして総合的学習と言えたんだろうか。5・6年でいうところの課題追求で本当にこの学習を通じて自分の生き方が何か変わるほど子どもたちが追求できただろうか。その原因は私たちがイベント的な捉え方しかまだできてなくて、この単元でねらうものを明確に持てなかったのではと・・・。イベントを成功させてその過程でどんな力をつけさせたいといったところが不足してたかなという、私たちの反省なんですけどね。
楠原:一応それは職員(会議)には掛けて初めての試みなので今回はなしで行こうと。予算内でやりくりすることの大切さを感じた5・6年も随分いましたし、グループで追求するなかでけんかもしながら協力していくことの大切さも知っていったし、子供たちにとってすごく大きな意味があった。それに地域の多くの方々からこれだけするのだったら、お金出していいって。やってみて、実態を分かってもらえれば「次は私たちも考えますね」って言えるんですよ。(笑)
ASAP:副島さんが入るタイミングは遅かったと思うんです。
楠原:コンセプト決める時ぐらいのときに来てもらえるといいかな。
副島:タイトル見て、ワールドカルチャーってすごいなと、でも中身見るとフードフェァかなと、あまりにもタイトルとのギャップも感じまして。状況もよくわからなかったけど、子供たち随分勉強されてもう結構進んでましたね。でも当日はそれが貼り出してあるだけで、料理もあれば言葉も衣装もあるし、いろんなカルチャーがある、せっかくあそこまで興味持って調べたなら、そのへんがもう少し入っていればおもしろくなったかなと。
楠原:祭りにするなら、その前に20時間ぐらい必要だったと思う。自分の調べたい国を徹底的に調べる、そのなかで一番自分の心を揺り動かされたのは何か、それをどうやってみんなに知らせて行こうかな、その時に祭りっていうテーマはどうかな、って出てくれば・・・。でも今年はもうこれしかなかったとは思うんですね。
ASAP:今年度に経験した3年生から5年生までみんな上がって祭りにする時に、20時間ぐらいかけて、じっくり考えようとする素地ができているという期待はありますかね?
木下:年間計画をたてて行く時にどういうかたちにするか。最後のゴールは、かわらないかもしれないけど、プロセスそのものを変えることは可能ではないかなと思います。総合学習として単元化していくときには3年生では遊びという観点から、4年生では食とか、または国際の助け合いのレベルで見るとか、学校全体のテーマの高まりを作っていかないといけない。3年生から食、食、食と行ってしまうと5年生になったらあっぷあっぷですよ。
前田:(生徒達は)学年が終わったらもうおしまいっていう感覚なんですよ。え〜4年生になっても?って。
木下:全体計画をつくらないといけないというのはそのへんでしょうね。
楠原:ただそれは学年で観点を決めてしまうと、分けるときが難しくなりますよね。3、4、5、6ぐらいでつくるのか、2つの視点を3・4年に盛り込む、または5・6年に2つ盛り込むというところが、いるかな〜と思いますね。
ASAP:今後やってみたい授業はありますか?
土井:将来の天神を、町のデザインをしてみたいですね。大名の古きよき時代、伝統を大事にしながらも時代と融合したまちづくり、将来どう変わって行くのか、どう変えて行きたいかとか・・・。
前田:課題を持つ前に子供たちに現実の世界を見せる、例えば都市計画とかでも、じゃあなんのために都市計画するのか、そこに住んでいる人とかのなにかがないと課題を持たないですよね。
楠原:いろんな人に出会わせたい。夢とかあこがれとかを持てる人になって欲しいなーっていうのがあるんですね、それがあればいいほうにのびていきたいと思うんじゃないかなと思って。
前田:私が今回学んだのはただこれをやりたいといった行動ありきじゃなくて、そこに人とのつながりがあるんだな、とすごく感じて、どれをやりたいというのは人のつながりがあってできたということですね。
|