|
☆ほいくの両極☆(78)
日保協県支部について思う(2)
太田 象
筆者が地方にいた頃の印象でいうと、日保協の県支部は、総じて時代、政策の動向に敏感な保育所が多く、地元自治体に対する働きかけも強力で素早い集団であった。他の団体が、どちらかといえば玉石混淆の集団であるのに対し、日保協県支部加入の保育所は県内保育所の精鋭集団であったと思う。
☆ ☆ ☆
地元自治体にとっては、日保協県支部の加入保育所は、現場の実情を知る上で頼れる存在であるとともに、ときにうるさい存在である。県支部の運動は、ときとして政治色を帯びることもあり、自治体でもないがしろにできない。案件によっては議会議員、首長クラスに話が飛んだりするので、筋道の通った対応をしないといけない。
また、情報の面でも優れていて、国、中央の情報が、日保協の本部から、常にリアルタイムで県支部、ひいては加入保育所にダイレクトに送られてくる。伝達が早く、しかも正確で、市町村の行政担当者が県を経由して間接的に得るよりも、日保協県支部加入の保育所の方が、国の動向に関する情報を早く手に入れることがあるのは日常茶飯事であった。解説や助言など付加価値がついて流れてくることもしょっちゅうあった。このあたりにも、中央直結型組織の強みが現れていたように思う。
このように、日保協の県支部の存在意義は、中央直結型の組織らしい情報の質と量、早さ、動きの機敏さと、精鋭集団としての取組の熱心さ、保育水準の高さ、地元自治体との良き緊張関係にあると思う。
通り一遍の情報、活動であれば、他の団体に加入していれば足りる。が、しかし、今、保育業界は民間参入はもちろん、大きく状況が変動しつつある。少子化の問題もある。
そうした中で、適切、安定的な保育所運営、地域から頼られる保育所作りをしていくためには、これまで以上に国、中央の制度、政策の動向を先取りした経営感覚が求められる。
逆にいうと、県支部は、そうした民間保育所経営者のニーズに応えられるような活動を行うことが求められると思う。常に中央からの情報に能動的に対応すること、地元の実情にあわせた独自性のある保育水準の向上のための活動を行うこと、自治体との関係など、県支部に加入し、会費を支払うだけの価値ある活動が求められるのではないか。
はっきりいって、この辺になると支部長はじめ県支部幹部の力量によるところが大きい。支部長の交代によって、それまでの先鋭な活動から、単なる年中行事だけを行う支部になってしまったところもある。五年くらいはそれで持つかもしれないが、いつかほころびがくる。加入保育所の意識水準も下がり、県支部に加入している意義も薄れてきて組織がもろくなる。
保育所が多く作られた時代の保育所経営者がだんだんと引退の時期を迎えつつある今から、四〇代の若手が保育業界の屋台骨を担うようになるまでの間、日保協の地方組織にはもうひと踏ん張りが求められているように思う。
○「ほいくの両極」についてのご感想、ご意見等がございましたら、
E-mail: hoiku@jobs.co.jpまで。
食料の六割は輸入品
―平成十四年度食料自給レポートから―
武蔵丘短期大学学長 実践女子大学名誉教授 藤沢 良知
はじめに
昨年十二月に農水省から、平成十四年度食料自給レポート・食料需給表が公表されている。食料需給表はフードバランスシートともいわれ、FAOの統一的な作成手引に基づいて毎年度農水省が作成し、FAOやOECDに報告されている。
作成方法は、わが国で供給される食料の生産から輸出入量を考慮し、国民一人一日当たりの供給純食料及び熱量、たんぱく質、脂質などの供給栄養量を示したものである。
国民栄養調査は家庭の食事摂取面からの統計であるが、食料需給表は食料の生産供給面からの統計であり、両調査とも国民栄養の実態把握上意義ある統計である。
食料需給表は、世界のおよそ一六〇か国でもほぼ同一基準で作成されているので、各国の食料供給や栄養水準の国際比較も可能である。
保育所給食をすすめるに際しても、日本の食料生産や供給がどうなっているか、使用食品は国産品か輸入品か等を踏まえて、食料の廃棄やロスをいかに少なくするかなど食料資源を大切にするとともに、地産地消といわれるが、地元の農水産物の給食への活用を図りたいものである。
一、脂質エネルギー比は二九%に
国民一人一日当たり供給熱量は、平成十四年度で二七五八kcal、たんぱく質八六・〇g、脂質八三・六gとなっている。最近の動向をみると景気低迷もあってか、減少傾向が続いている(表1)。
表1 国民1人1日当たり供給栄養量
| |
熱量kCal |
うち米の比率(%) |
たんぱく質(g) |
うち動物性たんぱく質 |
脂肪(g) |
| 昭和60年 |
2,727 |
28.0 |
82.1 |
50.2 |
75.4 |
| 平成2年 |
2,787 |
25.9 |
85.5 |
52.9 |
79.7 |
| 平成12年 |
2,800 |
23.8 |
86.8 |
55.1 |
84.2 |
| 平成14年 |
2,758 |
23.5 |
86.0 |
55.2 |
83.6 |
|
資料:食料需給表
表2 PECエネルギー比率(%)
| |
たんぱく質(P) |
脂質(F) |
炭水化物(C) |
| 昭和60年 |
12.7 |
26.1 |
61.2 |
| 平成2年 |
13.0 |
27.2 |
59.9 |
| 平成12年 |
13.1 |
28.7 |
58.2 |
| 平成14年 |
13.2 |
29.0 |
57.8 |
|
資料:食料需給表
供給エネルギーに占めるたんぱく質、脂質、炭水化物の割合を示すPFCエネルギー比をみると、昭和六十年度に比べ、たんぱく質、脂肪エネルギー比が増加し、漸次食の洋風化傾向が進んでいることを示している。
脂質エネルギー比は、幼児期から青少年期は二五〜三〇%、成人期で二〇〜二五%が目標とされているが、平成十四年度は国民平均二九・〇%と過去最大で適正水準を超え、脂肪摂取に赤信号がともってきている(表2)。
幼児期から脂肪の多い食品を少なくし、米などでん粉質食品をなるべく多くとる食生活を習慣化させたい。
二、エネルギーは何から摂っているか
供給される食料による熱量の推移を、主要食品群でみると、米からの供給割合が減って畜産物、油脂類からの摂取割合の増加の著しいことがわかる(図1)。
三、増やしたい食品、減らしたい食品
農水省では、平成十二年に食料・農業・農村基本法に基づいて、食料自給率の向上、健康面の配慮もあって、平成二十二年を目途とした主要食品の摂取目標が示されている。
この摂取目標値と比べて摂取量の増加若しくは摂取量の維持が必要な食品として、米、野菜、牛乳、乳製品、大豆、魚介類をあげている。
米の摂取増は、脂質摂取過多を抑え、食料自給率の向上、食料の安定供給にも役立つが、近年食の外部化や多様化に伴い年々減少を続けているが摂取増加が望まれる。
野菜・果実はビタミンA・C等をはじめ、各種ミネラル、食物繊維に富む食品で健康面からみた摂取増が望まれるが、近年野菜は摂取が減少傾向であるが、幼児期から野菜好きの子どもに育てたい。
牛乳、乳製品、魚介類は、たんぱく質、カルシウム等のミネラルに富む食品で、健康面から摂取増が期待される。近年横ばいで推移しているが、幼児期から十分摂るようにしたい。
健康面から摂取量を減らしたい食品としては、肉類、鶏卵、油脂類があげられる。肉類、鶏卵は子ども達の大好きな食品で近年増加傾向をみせているが、脂肪エネルギー比を適正に保つ上からも、適量摂取を心掛けたい。
図1 我が国の食生活の変化(1人1日当たり供給熱量の構成の推移)
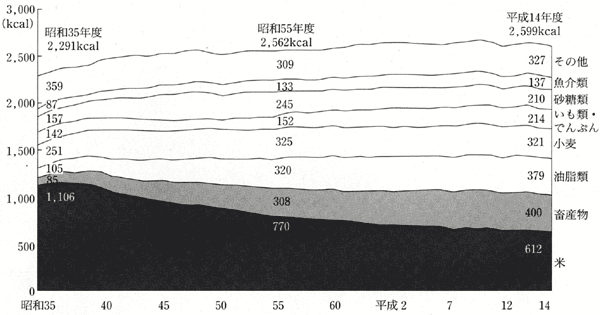 |
|
(資料)「食料需給表」
(参考)米・畜産物・油脂類の合計の水準にほとんど変化はない。
主食のごはん(米)が減少(昭和35年度から4割減)する一方で、畜産物(同約5倍)、油脂類(同約4倍)が増加してきたことが分かる。
資料:食料需給表
|
四、熱量自給率は四〇%
食料自給率は、国内の食料消費について、国産の食料でどの程度賄えるかを示す指標である。食料自給率の示し方には、カロリーベースで示す熱量自給率、主要食品の品目別自給率、穀物自給率がよく使われている。
うち最もよく使われているのがカロリーぺースの食料自給率(供給熱量総合自給率、熱量自給率ともいう)である(図2)。
図2 我が国の食料自給率の推移

|
|
(資料)「食料需給表」
|
わが国の熱量自給率は、昭和六十年は六三%、平成二年は四八%であったが、その後減少傾向を辿り、平成十年度以降四〇%となっている。
これは、現在わが国が輸入している主な農産物の生産に必要な海外の農地面積は、国内農地面積(四七六万ヘクタール)の約二・五倍の約一二〇〇万ヘクタールに及んでいることを示すもので、食料資源が少ない上、飽食時代を反映する日本の現実を示すものである。
五、自給率の低い大豆、小麦、油脂類
主な食品別の食料自給率をみると、平成十四年度で米が九六%(前年度九五%)、鶏卵九六%、次いで野菜の八三%である。また、関税率の引き下げや円高で肉類の輸入が増加し、肉類自給率は五三%となり、うち牛肉自給率は三九%となっている。平成十五年十二月には、米国でBSE発生で輸入が中断されるなど異常事態が起きている。
自給率の低いものは大豆五%、小麦一三%、油脂類一三%、砂糖類三四%である。
穀物自給率(食用+飼料用)は、昭和六十年度で三一%であったが、漸次低下傾向をたどり、平成十三年度で二八%、平成十四年度も二八%となっている(表3)。
表3 主要食料の自給率(%)
| |
昭和60年 |
平成2年度 |
平成12年度 |
平成14年度 |
| 米 |
107 |
100 |
95 |
96 |
| 小麦 |
14 |
15 |
11 |
13 |
| 豆類 |
8 |
8 |
7 |
7 |
| うち大豆 |
5 |
5 |
5 |
5 |
| 野菜 |
95 |
91 |
82 |
83 |
| 果実 |
77 |
63 |
44 |
44 |
| 肉類 |
81 |
70 |
52 |
53 |
| (うち牛肉) |
72 |
51 |
33 |
39 |
| 鶏卵 |
98 |
98 |
95 |
96 |
| 牛乳・乳製品 |
85 |
78 |
68 |
69 |
| 魚介類 |
93 |
79 |
53 |
46 |
| 砂糖類 |
33 |
32 |
29 |
34 |
| 油類 |
32 |
28 |
14 |
13 |
| 供給熱量自給率 |
53 |
48 |
40 |
40 |
| 主食用穀物自給率 |
69 |
67 |
60 |
61 |
穀物(食用+飼料用)
自給率 |
31 |
30 |
28 |
28 |
|
|
|
資料:食料需給表
|
六、先進国で最低の食料自給率
供給熱量自給率の国際比較をしていくと、アメリカ一二二%、フランス一二一%、ドイツ九九%と比べ、日本の四〇%はいかに低いかがわかる。
なお、経済発展に伴い欧米化の進んだ韓国においては、日本と同様食料自給率は低下している(図3)。
図3 各国の食料自給率(カロリーベース)の推移
 |
|
(注)日本以外のその他の国についてはFAO“Food Balance Sheete”等を基に農林水産省で試算。ただし、韓国については、韓国農村経済研究院“Korean
Food Balance Sheet 2001”による(1970、1980、1990及び1995〜2001年)。なお、1990年以前と1995年以降では算出方法が違うため、データは連続しない。
|
七、食物を大切にする心を
二十一世紀は人類の食料問題の大転換期、地球上には飽食の生活や肥満が問題になっている国がある一方、発展途上国の中には、飢餓と慢性的な栄養不足状態にある約八億人がいる。そのうち五歳未満の子どもが約四分の一を占めるなど小児の栄養不足は深刻である。
世界中で五歳未満の子どもで死亡する者は年に一一〇〇万人、多くは肺炎や下痢による脱水症状などで予防できるものであるが、その半数は栄養不良が関係しているといわれている。
わが国は飽食時代といわれ、食料の廃棄やロスも多く、今の子供達は嫌いなものは食べない、食べ物の大切さがわからないなど淋しい限りである。
食物の六割をも輸入しながら、食べ物の二〜三割もが廃棄されている現実をもっと真剣に考え、幼児期から食の大切さが身につくような食育運動を積極的にすすめたいものである。
参考資料
一、平成十四年度食料自給率レポート、わが国の食料自給率、農林水産省平成十五年十二月
|