|
結婚後第1子出生までの期間、すなわち夫婦だけの期間が短縮する傾向にあるが、日本との比較では多少長いことがわかる。次に、第1子出生から全出産終了までの平均出産期間は経年ごとに短縮され、この四半世紀に3.7年から1.6年と2.1年程度も短くなり、日本と同程度になっている。子どもを産み始めたら短期間で産み終える出生行動に転換している。結婚から全出産終了までの期間をみても同様の傾向がみられる。結婚年齢は23.9歳から27.8歳と3.9歳晩婚化が進行しているにもかかわらず、全出産平均年齢は28.8歳から30.7歳へと1.9歳程度しか遅くなっていない。子どもを産み始めたら短い期間で少ない子を産み終える、子女出産期の短縮傾向が明らかとなっている。
表1 平均初婚年齢および平均出産年齢の推移
| 年次 |
(1)
初婚年齢 |
(2)
初産年齢 |
(3)
出産年齢 |
(4)
(2)-(1) |
(5)
(3)-(2) |
(6)
(3)-(1) |
| 1975 |
23.9 |
25.1 |
28.8 |
1.2 |
3.7 |
4.9 |
| 1980 |
23.4 |
25.0 |
28.2 |
1.6 |
3.2 |
4.8 |
| 1985 |
24.2 |
25.8 |
28.4 |
1.6 |
2.6 |
4.2 |
| 1990 |
25.3 |
26.8 |
28.9 |
1.5 |
2.1 |
3.6 |
| 1995 |
26.8 |
28.4 |
30.0 |
1.6 |
1.6 |
3.2 |
| 2000 |
27.8 |
29.1 |
30.7 |
1.3 |
1.6 |
2.9 |
| (参考:日本) |
| 1975 |
24.7 |
25.7 |
27.5 |
1.0 |
1.8 |
2.8 |
| 1995 |
26.3 |
27.8 |
29.4 |
1.5 |
1.6 |
3.1 |
| 2000 |
27.0 |
28.0 |
29.7 |
1.0 |
1.7 |
2.7 |
|
資料)Council of Europe, 2002. 日本の初婚年齢は、厚生労働省統計情報部『人口動態統計』、初産および出産年齢は、同資料により国立社会保障・人口問題研究所が算出したもの。
結婚行動、出生行動など、スペイン女子のライフコースの前半部分が大きく変化していることがわかる。これは同時に女性の社会進出とも関連しているが、出産の開始時期の遅れがその後の出産間隔の縮小によって取り戻し効果に直結しているとはいえない。コーホートの完結出生力が置き換え水準を大幅に下回る水準であることを考えると、出産タイミングの変化は最終的な出生力水準に大きく影響している。いずれにしても、南欧諸国では出産のタイミング、家族形成のタイミングが大きく変化している。
4)普通離婚率と合計離婚率
図13 合計離婚率の推移
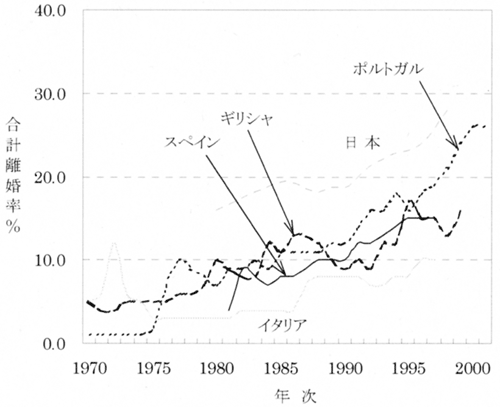 |
|
出所)Council of Europe, 2002. 日本は、小山泰代・山本千鶴子「日本の婚姻・離婚の動向:1996〜1998年」『人口問題研究 Vol.57-3』国立社会保障・人口問題研究所。
|
普通離婚率(crude divorce rate)の推移をみたのが図13である。離婚は出生過程の中断を意味するが、南欧諸国ではそもそも正式に離婚が認められるようになって日が浅く、離婚については厳格であった。しかし、各国とも徐々に普通離婚率は上昇する傾向にあり、1998年にギリシャ0.74、イタリア0.58、ポルトガル1.51、スペイン0.94であるが、北西欧諸国より低く、日本の1.94よりも低位である。たとえば、スペインでは1981年6月に離婚が合法化され、その後半年のうちに9,500組が登録、普通離婚率は0.3‰、翌年の1982年には2万組、0.6‰であった。1981年から1989年までの間年平均ほぼ2万組の離婚があり普通離婚率は0.5‰で推移した。1998年には36,072組が離婚し、0.92‰と上昇したが日本の半分程度の離婚率である。したがって、比較安定的な夫婦関係が営まれているといってよい。南欧諸国の初婚率が高いのは離婚が少ないことも要因となっていることがわかる。
また、各国の1995年の合計離婚率は、ギリシャ17%、イタリア8%、ポルトガル16%、スペイン15%程度であるが、近年増加する傾向にある。
(2)有配偶行動の変化
イタリア、スペインなど南欧諸国は、北西欧諸国に比べると婚姻外出生は少ない、その意味で婚姻率の動向は出生率に影響を及ぼす。
スペインの有配偶割合の推移をみたのが表2である。この推移をみると、女子有配偶者割合は急速に低下しており、逆に未婚者割合は急激に増加している。2000年には、20-24歳、25-29歳、30-34歳の未婚率は日本を凌いでいる。とくに25-29歳層では、有配偶率32.9%、未婚率65.4%と、この世代のほぼ3人に2人が未婚者である。未婚者が過半数を超えた日本よりもさらに10%以上も高いという状況にある(男子未婚率81.3%)。25-29歳層では、有配偶率が1981年75.9%、1991年53.5%、2000年には32.9%と、10年間隔でそれぞれ20%づつ低下している。この20年間に40%以上の低下であり、未婚化、晩婚化が急激に進行した。
南欧諸国にとって婚姻水準の変化は出生力水準に直接影響を与えており、婚姻の停滞と出生力とは密接に関連している。未婚率の上昇が1970年代後半から1980年代にかけての急速な出生率低下と符合し、結婚行動の変化は出生力変動に影響を与えた最大の要因といえる。
表2 スペインの女子有配偶割合の推移
| |
1981 |
1986 |
1991 |
1996 |
2000 |
2000
(日本) |
| 15-19 |
5.3% |
3.6% |
2.3% |
1.2% |
1.2% |
0.9% |
| 20-24 |
39.7 |
28.4 |
21.6 |
8.5 |
6.2 |
11.3 |
| 25-29 |
75.9 |
67.9 |
58.8 |
42.4 |
32.9 |
43.5 |
| 30-34 |
85.1 |
82.2 |
78.2 |
74.3 |
69.3 |
68.9 |
| 35-39 |
87.0 |
85.6 |
83.3 |
82.9 |
79.1 |
79.2 |
| 40-44 |
86.7 |
86.2 |
84.7 |
85.0 |
83.4 |
83.3 |
| 45-49 |
84.4 |
85.2 |
84.6 |
84.8 |
82.5 |
83.7 |
|
出所)INE,各年版。
日本は、総務省統計局『国勢調査報告』。
(3)同棲・婚外子
1)同棲
1996年の各国の同棲率を示すのが図14である。1996年の16−29歳の同棲率は、ギリシャが15%(1994年9%)、イタリア9%(6%)、ポルトガル11%(10%)、スペイン10%(14%)であり、全年齢では各国とも2〜3%程度である。EU15ヶ国の16-29歳の平均31%と比較すると、南欧諸国の同棲率はヨーロッパ諸国の中では最も低いといえライフスタイルとしては一般化していない。
図14 ヨーロッパ諸国の年齢別同棲率
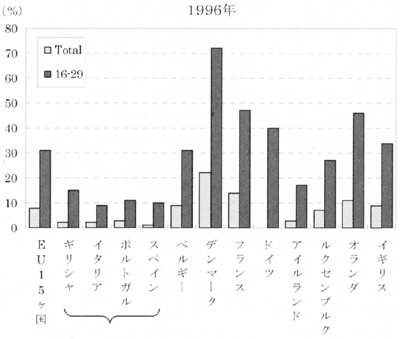 |
|
出所)The Clearinghouse on International Developments in Child,
Youth and Family Policies at COLUMBIA UNIVERSITY
|
南欧諸国では、結婚はパートナーシップの通常の形であり、近年非婚同棲は増加傾向にあるがほかの北西欧諸国に比べまだ低く、大多数の同棲は子どもが生まれるか生もうとする場合には早晩結婚に移行している。同棲の発生の低さは、法律的保護の欠如によってある程度説明される。
2)婚外子
北西欧諸国では、婚姻はもはや出産の開始を示すシグナルではないと言われる。多くの西欧諸国ではかなりの婚姻外の出生がみられ出生率にも影響を与えている。婚外出生割合の推移をみたのが図15である。
図15 婚外出生率の推移
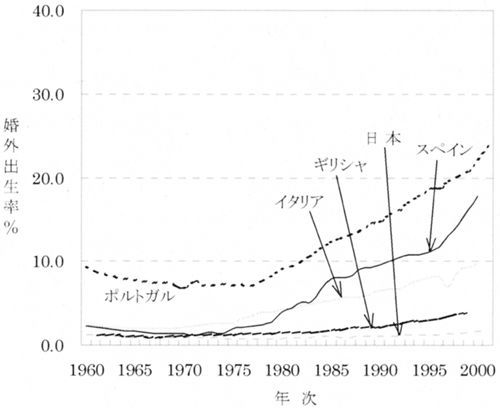 |
|
出所)Council of Europe, 2002。日本は、厚生労働省統計情報部『人口動態統計』による。割合は、全出生に対するもの。
|
1999年の各国の婚外子割合は、ギリシャ3.9、イタリア9.2、ポルトガル20.9、スペイン16.3となっており、南ヨーロッパ諸国のなかでは、近年婚外子割合が急増するスペイン、ポルトガルのイベリア半島の国と、イタリア、ギリシャとでは多少地域差がみられる。
南欧諸国の結婚や出生力関係の指標は他の西欧諸国の後追い傾向がうかがえ、同棲割合や婚姻外出生についても近年増加傾向にある。しかし、フランス41.7、スウェーデン55.3、イギリスの38.8と比べれば低い水準にある(日本は1.6である)。しかし、前段でも見たように、スペイン、ポルトガルのイベリア半島の諸国は、イタリア、ギリシャに比べ「ピレネー以北」の新しい結婚行動、出生行動のパターンが進行していることも伺わせる。
|