|
――シカ刺しとE型肝炎――
たべものの話(109)
道野英司
みなさんはE型肝炎という病気をご存じだろうか。肝炎というとB型やC型がよく話題になるが、E型はA型と同様、食物や水で経口感染する急性肝炎であり、慢性化し、肝臓ガンの原因となるB型やC型とは異なるタイプの肝炎である。
最近、このE型肝炎に関する様々な調査結果がマスコミに報道される機会が増えてきたので、今月はE型肝炎について紹介することとしたい。
E型肝炎は、E型肝炎ウイルスの感染によって引き起こされるが、十年前の健康な日本人の血液を調査したところ、すでに過去にE型肝炎に感染したことを示す抗体保有率は平均五%程度であり、二十代以下では○・四%、年代を追って高くなり五十代では二三%だった。実際に抗体陽性の人でも症状が現れない不顕性感染が多いが、発症すると、平均六週間の潜伏期の後に発熱、腹痛等の消化器症状、肝腫大、肝機能の悪化などがみられるが、大半の症例では安静にしていれば治癒する。しかし、妊婦が感染した場合は致死率が二〇%に達するとの報告もあり、注意が必要とされている。
E型肝炎の発生状況は開発途上国と先進国では大きく異なっている。開発途上国では患者が散発的に発生しているが、多くの人が使う飲料水が汚染されると、大規模な流行を引き起こすことが知られている。一方、先進国においては、開発途上国への旅行者の感染事例が多かったことから専ら「輸入感染症」として認識されてきた。しかし、近年、国内で渡航歴のない「国内感染例」も見つかるようになり、日本でも四年間に一〇例以上の国内感染例が学会などで報告され、日本におけるE型肝炎の発生はさらに多く存在すると推定されている。
最近、先進国において急性肝炎患者から検出されたE型肝炎ウイルスが豚から採取されるウイルスと極めて類似していることから、E型肝炎が人獣共通感染症ではないかと指摘する専門家が現れ、野性動物や豚からの感染リスクが議論されるようになってきている。
こうした中で本年二月に鳥取県でイノシシの肝臓を生で食べ二人がE型肝炎に感染し、一人が亡くなった事例や本年三月に兵庫県でシカ肉を刺身で食べた四人がE型肝炎を発症した事例が国際的な学術雑誌で公表された。イノシシの肝臓を食べた事例は患者が食べた肝臓が残っていなかったため、肝臓のウイルス検出ができず、因果関係の証明に至らなかったが、シカ肉の刺身を食べた事例は患者四人から検出されたE型肝炎ウイルスと残ったシカ肉から検出されたウイルスが遺伝学的に一致したため、特定の食品がE型肝炎の原因になったことが直接的に証明された世界で最初の事例とされた。野性のシカは、狩猟や有害鳥獣駆除によって全国で年間約一〇万頭捕獲され、二〜三百トンが食肉処理業者によって解体処理され、食肉として流通している。野性動物が人獣共通感染症や食中毒の原因となる病原微生物、寄生虫類等を保有している可能性は、常に念頭におく必要があるが、E型肝炎ウイルスは通常の加熱によって死滅することが知られていることから、野性動物の肉等を食べる際には加熱を十分に行うことにより感染を避けることが重要である。
また、本年九月発行の英国の学術誌には、北海道の食料品店で市販されていた包装済みの豚生レバーの一・九%からE型肝炎ウイルスが検出され、そのひとつは北海道のE型肝炎患者から検出されたウイルスと一致し、さらにE型肝炎に感染した患者十人のうち九人(九〇%)が、発症前の二〜八週の間に焼いた又は加熱不十分な豚レバーの喫食歴を有していた。この報告では、同一の豚レバーを食べた患者家族に感染がなぜなかったのか、以前から豚レバーを食している患者がなぜ今回感染したのか、豚レバーには感染力があるE型肝炎ウイルスが存在したのかなど、解明するべき疑問はあるものの、加熱不十分な豚レバーが人にHEVを感染させる可能性を指摘している。
豚レバーなどに万一ウイルスが残っていたとしても、通常の加熱調理を行えばHEVは感染性を失うため、豚レバーなどの豚由来食品を食べることによる感染の危険性はないので、通常の加熱調理を確実に行うことが重要である。
いずれにしても聞き慣れないE型肝炎という病気やこの病気と豚、シカ、イノシシなどの関係について、最新の情報を厚生労働省ホームページにも掲載しているので、興味のある方は是非ご覧いただきたい。
なお、腸管出血性大腸菌食中毒予防の観点から若齢者、高齢者のほか抵抗力の弱い者に対しては、生肉を食べさせないよう厚生労働省では従来から注意喚起を行っていることも忘れないでいただきたい。
(厚生労働省食品安全部監視安全課課長補佐)
夫婦出生力の変化(2)
――結婚と出産に関する全国調査(平成12年)――
国立社会保障・人口問題研究所
高橋重郷・金子隆一・福田亘孝・釜野さおり・大石亜希子・佐々井司
池ノ上正子・三田房美・岩澤美帆・守泉理恵
3、妻の世代による比較
(1)九〇年代以降、夫婦出生力に低下が見られる
妻の年齢別に夫婦の平均出生子ども数の推移をみると、一九九〇年前後(第九〜十回調査の間)に二〇歳代後半から三〇歳代前半で最初に低下が見られ、その低下は三〇歳代後半へ広がりながら九〇年代半ば(第十〜十一回調査)へと継続したことがわかる(図III-3-1)。さらに、二〇〇〇年前後(第十一〜十二回調査)でも三〇歳以上で低下が続いているが、二〇歳代の若い層では低下に歯止めがかかっている。これらの動向を妻の世代別(生まれ年別)にみると、一九六〇年代生まれの世代が二〇歳代の終わりに達した頃から夫婦の出生力が低下していることがわかる(図III-3-2)。
IV、子ども数についての考え方
1、理想子ども数・予定子ども数
(1)予定子ども数の減少で、理想子ども数との差がやや広がる
本調査では、夫婦にとっての理想的な子どもの数(理想子ども数)と、実際に持つつもりの子どもの数(予定子ども数)をたずねている。今回調査では、平均理想子ども数は二・五六人、平均予定子ども数は二・一三人であった。平均理想子ども数は前回調査と比べ、ほぼ横ばいであったが(表IV-1-1)、平均予定子ども数は結婚後十五年未満の比較的若い夫婦を中心に減少が見られ(表IV-1-2)、これらのグループで予定子ども数と理想子ども数との差がやや広がった。また、結婚後五年未満の若い夫婦では、一九九〇年代以降、理想、予定子ども数ともに比較的急な低下傾向が見られる。
図III-3-1 妻の年齢別にみた、平均出生子ども数
図III-3-2 妻の年齢階級別にみた、妻の出生年別、平均出生子ども数
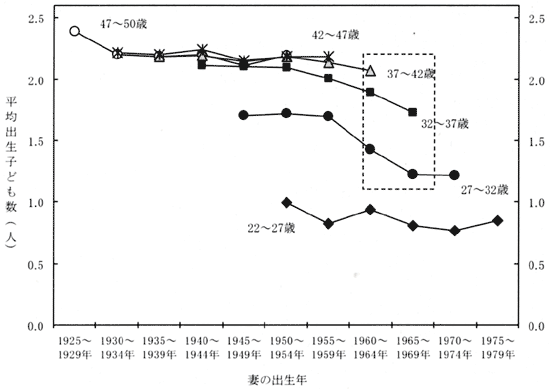 |
|
注:図中、破線の囲みは夫婦の平均子ども数に低下が見られる部分。
なお、年齢階級の境界は年半ばとなる。
|
表IV-1-1 調査別にみた、結婚持続期間別、平均理想子ども数
| 結婚持続期間 |
第7回調査
(1977年) |
第8回調査
(1982年) |
第9回調査
(1987年) |
第10回調査
(1992年) |
第11回調査
(1997年) |
第12回調査
(2002年) |
| 0〜4年 |
2.42人 |
2.49 |
2.51 |
2.40 |
2.33 |
2.31 |
| 5〜9年 |
2.56 |
2.63 |
2.65 |
2.61 |
2.47 |
2.48 |
| 10〜14年 |
2.68 |
2.67 |
2.73 |
2.76 |
2.58 |
2.60 |
| 15〜19年 |
2.67 |
2.66 |
2.70 |
2.71 |
2.60 |
2.69 |
| 20年以上 |
2.79 |
2.63 |
2.73 |
2.69 |
2.65 |
2.76 |
総数
(標本数) |
2.61人
(8,314) |
2.62
(7,803) |
2.67
(8,348) |
2.64
(8,627) |
2.53
(7,069) |
2.56
(6,634) |
|
注:初婚どうしの夫婦(理想子ども数不詳を除く)について。
表IV-1-2 調査別にみた、結婚持続期間別、平均予定子ども数
| 結婚持続期間 |
第7回調査
(1977年) |
第8回調査
(1982年) |
第9回調査
(1987年) |
第10回調査
(1992年) |
第11回調査
(1997年) |
第12回調査
(2002年) |
| 0〜4年 |
2.08人 |
2.22 |
2.28 |
2.14 |
2.12 |
1.99 |
| 5〜9年 |
2.17 |
2.21 |
2.26 |
2.19 |
2.12 |
2.07 |
| 10〜14年 |
2.18 |
2.18 |
2.20 |
2.25 |
2.18 |
2.10 |
| 15〜19年 |
2.13 |
2.21 |
2.18 |
2.18 |
2.23 |
2.22 |
| 20年以上 |
2.30 |
2.20 |
2.24 |
2.18 |
2.19 |
2.28 |
総数
(標本数) |
2.17人
(8,129) |
2.20
(7,783) |
2.23
(7,995) |
2.19
(8,295) |
2.17
(6,427) |
2.13
(6,564) |
|
注:初婚どうしの夫婦(予定子ども数不詳を除く)について。
図IV-1-1 結婚持続期間別にみた、平均理想子ども数と平均予定子ども数
第12回調査
|