|
―資料研究―
保育所費用の地域差について
保育所運営費一般財源化の平成十六年度実施については表出しなかったが、地方への税財源移譲、国庫補助金削減、地方交付税圧縮の「三位一体改革」問題の議論は引き続き行われている。そこで保育所関連費用について、地域差の観点からグラフで眺めて見ることにした。
保育所関連費用については次のような算式が成り立っている。
保育費用は、児童の保育のために市町村から保育所に支払われる費用、即ち保育所の運営費であり、行政用語では「支弁額」という。保育所と在籍児童との態様よって児童一人当りの月額として定められた「保育単価」に基づいて算定される。保育単価は、児童の年齢が小さいほど高く保育所の規模が小さいほど高く設定されていて、その差は非常に大きい。また、大都市ほど高額になっている。(表1)。
表1 保育単価例(乙地域・平成14年度)
| 保育所の定員 |
児童の年齢 |
| 0歳児 |
1・2歳児 |
3歳児 |
4・5歳児 |
20人定員
151人以上 |
202,960
145,570 |
139,340
81,950 |
91,690
34,300 |
85,330
27,940 |
|
保育料は保護者が市町村に納付するもので「徴収金」と称される。保護者の所得及び児童の年齢によって定められており、これまた金額の差は極めて大きい。なお、本稿でいう保育費用(支弁額)及び保育料(徴収金)は、ともに国が定めた基準によって算出されたものを指している。(自治体によっては独自に費用を嵩上げし、保育料を減額している場合がある。)
市町村は保育費用を一旦保育所に支弁する一方保護者から保育料を徴収するので、その差額が純公費負担となることを前述の算式が示している。見方を変えれば
ともいえることを念頭において、下のグラフを見ていただきたい。
1、管内人口当り公費負担額及び保育所在籍児童数
保育費用の公費負担額と保育所在籍児童数とについて、管内人口一人当りで算定し都道府県別に比較したものが図1である。なお、入手出来た人口関係資料の都合で、指定都市及び中核市については夫々の都道府県に一括計上せざるを得なかった。
公費負担額(黒棒)を多い順に並べてあるが、一瞥して都道府県によって格差が非常に大きいことがわかる。県民一人当り月額一二九八円の宮崎県は二七八円の神奈川県の四・七倍である。格差を生ずる要因としてまず考えられるのは保育所の利用状況である。人口当たりの保育所利用児童数(白棒)に差があることだ。しかし保育所の普及率が高いことで知られる長野県が五〇三円で、全国平均値を下回っているデータが示すように相関関係はさほど強くなく、それだけでは説明がつかない。
保育所運営費の二分の一国庫負担を止めて一般財源化すべしという議論がある。その際増加する地方負担については交付税で手当てをすることを前提にしている。即ち、国庫負担金が減額しても同額が交付税でカバーされるはず。さすれば財政の数字上はプラマイゼロだ。交付税算定にあたっては人口等を基礎としつつも、更に保育所在籍人員による所要の補正がなされているではないか、と。しかしこのグラフはそれだけでは片付かないことを示している。児童数以外の要因としては、保育所児童一人当りに要する費用がありその額には自治体間で差があるためだと推測される。
2、保育所在籍児童一人当り費用の地域差
保育費用を公費負担及び保護者負担に区分して都道府県・市別に保育所在籍児童一人当りで算定し、公費負担額の多い順に並べたのが図2である。
児童一人当り公費負担額は全国平均では三万六千六百円であり、最高の沖縄県六万二百円は最低の豊田市一万五千二百円のおよそ四倍である。
グラフでは見づらいが保護者負担は全国平均二万七千六百円、最高は横須賀市三万七千九百円、最低は沖縄県一万九千五百円である。また、公費負担と保護者負担の合計である保育費用総額(保育単価の平均)は全国平均六万四千二百円、最高秋田市八万三千百円、最低豊田市四万三千百円である。
沖縄県と豊田市が二度登場した。沖縄県の公費負担額が多いのは保護者負担額の少ないことが大きな要因であり、豊田市の公費負担が少ないのは保育費用総額(保育単価)の影響が大きい。児童一人当りの公費負担額に大きな差があること、及びその理由は保育費用(保育単価)及び保護者負担(徴収金)に自治体間で格差があることをグラフから読み取ることができた。
3、保育費用の負担割合の地域差
都道府県・市別に保育費用に占める保護者負担と公費負担との割合を比較したのが図3である。この表は保護者負担の多い順に並べてあるので、残余の部分が公費負担になる。またまた豊田市(六四・七%)と沖縄県(二四・五%)が登場した。やはり自治体間の格差は大きい。ここでは指定都市及び中核市以外の市町村は各都道府県ごとに一括し平均値で示されているが、全市町村別に比較したら格差が更に広がることは間違いない。
以上見たように保育所運営費用に対する国庫負担は児童と保護者との属性によって大きな差を生ずる仕組みになっていることが実証された。いわば児童保育経費の二分の一を国庫負担することで国の財源の極端な傾斜配分がなされているのである。保育所運営費の国庫負担を廃止し一般財源化することになれば、愛知県下の多くの市町村の収入役さんは笑顔になり、沖縄県、宮崎県の多くの市町村長さんは苦渋することになろう。保育現場の関係者が保育所運営費の一般財源化に不安を拭えないのは以上のことを直感的に承知しているからであろうか。
本稿作成に当って使用した統計資料は全て総務省及び厚生労働省から公表されているものである。
(藤本勝巳)
図1 管内人口当り保育費用公費負担額・保育所在籍人員
図2 在籍児童1人当り保育費用(月額)
図3 保育費用に占める保護者負担額の割合
|
(拡大画面:321KB)
|
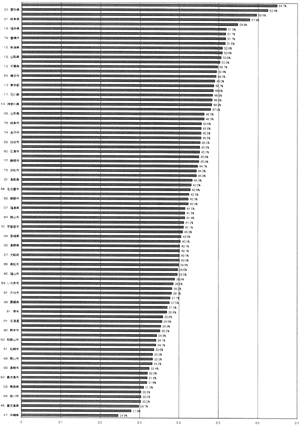 |
|