|
――子どもと食生活(32)――
幼児期の生活リズム・食事リズム
――早寝・早起きの効用――
武蔵丘短期大学学長
実践女子大学名誉教授
藤沢良知
一、大切な生活リズム
私達が毎日の生活を健康的に過ごすためには、肉体的にも精神的にも活動と休養を上手に組合わせてリズミカルな生活を行い、体調を整えることが大切である。
特に幼児期はからだの動きは非常に活発で、起きている間は絶えずからだを動かしているのが普通である。寝相が悪いというのも、眠っているときでも動かなければならないほど子どもは活動的であると考えてよいわけである。
幼児は静的姿勢の持続時間が短く、つねに動的であるが、その動き自体はそれほど素早いもの、強力なものではない。幼児の自発的身体活動を安全な環境でリズミカルに伸ばしてあげたいものである。
最近の子どもはカバン以外に重いものをもったことがないと言われているが、鉛筆削り一つにしてもナイフで削らせ、手指を十分使うような生活にしたり、食卓を拭く、食器を並べる食事づくりの手伝いなども時々させ、自分のことは自分でするといった日頃の生活指導が大切である。
また、平日と日曜日との生活行動が極端に違う幼児も多いようであるが、できるだけ同じにすること、少なくとも就寝、起床は一定にしたいものである。
大人になってからの生活では種々な制約が多く、毎日規則正しい生活ができないことも珍しくないが、小児期に十分な規則的生活を習慣づけて生物時計的リズムを完成しておけば、基本的体調の変化を起こしにくく、くずれた場合もなおりやすいといわれている。
二、幼児健康度調査
最近気になるのは、大人の生活習慣の乱れが子どもに大きな影響を与えていることである。小児保健協会が昭和五五年、平成二年、平成十二年と十年毎に行った「幼児健康度調査」の結果から睡眠・生活リズムの実態をみてみたい。
就寝時刻は午後九時が最も多く全体の四一%であり、次いで十時が三六%と多かった。昭和五五年値、平成二年値との比較では、全般に十時及び十一時就寝が年齢を追って増加し、その分八時就寝が減少している。
午後十時以降に就寝する児の割合は二歳児で昭和五五年二九%、平成二年三六%、平成十二年五二%、五〜六歳児で一〇%→一七%→四〇%となり、この二〇年間で幼児の就寝時刻は年々遅くなっており、夜型生活の傾向を強めていることがうかがえる。(図)
図 午後10時以降に就寝する児の割合
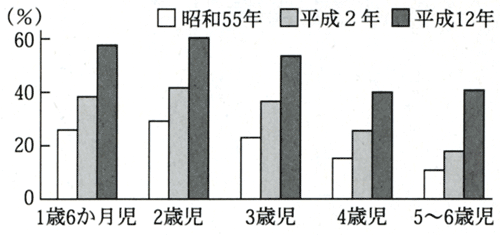 |
|
資料)日本小児保健協会:平成12年度幼児健康度調査
|
起床時刻は、全年齢において午前七時がピークであり、全体では五二%、三歳児以降の年齢では四九〜六四%が午前七時に目覚めている。次いで午前六時が一一%、午前八時二九%、午前九時以降に起床する者は七%であった。
平成二年値と比べると、午前六、時七時起床がやや減少し、九時以降に起床する者が三%から七%になり、起床時刻がやや遅くなっていることが明らかにされている。
このように起床時刻はやや遅くなっているものの、就寝時刻が顕著に遅くなり、幼児の睡眠時間が短くなり、保健指導面での課題が大きいといえよう。
三、リズムある生活の確立を
私達の生活はテレビの発達などから、夜型に変わっているが、その影響を受けて子どもの生活も夜型となり、その結果睡眠不足や朝食抜きなどの基本的生活習慣の乱れがみられる。
また、最近は朝からあくび、姿勢が悪い、アレルギーが多い、貧血ぎみ、年中風邪ぎみといった微症状を持つ子どもが多いといわれるが、これらも生活リズムの乱れからきているといってよいようである。
幼児の食事、睡眠、遊びなどの基本的な生活リズムについては、親や保育者はもっと自信をもって子どもが真に、子どもらしい生活をとり戻せるよう配慮してあげたい。生活のリズムはその家庭における最も基本的なもので、生活の便利さに押し流されることなく厳しさを持った子育てを心掛けたい。
食事の健康的なとり方としては、個々人の身体状況に見合って、しかもその生体リズム、生活リズムといかに調和させながら摂取するかが大切である。
私達のからだは、神経系や内分泌系の影響を受けて、体内の活性は微妙に調節されているものであり、生体リズムが乱れると体の不調をきたすことになる。
従って、健康生活習慣を確立するためには、生体リズムに合わせて日常生活をいかに規則的にするか、食事を三度三度いかに規則的にとるかが重要である。朝・昼・夕の規則正しい食事時間は、一方では生活を規則正しくし、体の健康にもよい影響を与えることになる。欠食児や食欲不振の子どもには、早寝早起きの効用を、生活体験として実践させたいものである。
四、自律起床のすすめ
自分で朝一人で起きることを自律起床というが、自律起床の子どもは、朝早く起きる者ほど多く、遅く起きるほど少ないといわれる。
自律起床する子どもは、このように早く目覚め自分で起きて、一日の生活リズムを積極的につくりあげていくため、行動が能動的・積極的で生活リズムも健全に規律化されていくものと考えられる。
NHKの国民生活時間調査によると、国民の平均就寝時刻も起床時刻も遅くなり、日本人全体の遅寝遅起きが進んでおり、当然幼児の生活もそれにひきづられて同じ傾向が進んでいる。
夜遅くまで起きていると、朝無理やりに起こされて朝食をとらずに保育所にきても、とても元気に遊んだりできず、実際に生理的に目覚めるのは二〜三時間後ということになる。
早寝早起き、そして自律起床して、体を動かすことによって体も目覚め、食欲も出、朝ご飯がおいしいということにもなるのである。
自律起床の習慣は、幼児期につけなければならないが、それにはリズムある生活習慣をしっかり確立することが大切である。
五、朝食はきちんと
早寝早起き、そして朝食まで少なくとも三〇分以上の時間をとり、朝食をしっかり食べて一日のスタートをゆとりをもって、リズミカルに方向づけたいものである。
起床後すぐには、体の交感神経が活発に働かないので、血圧や体温も低く、脳もからだも活動する状態にならない、食欲もわいてこない。従って、子どもは朝早くに起きるようにして、食事も三〇分位してからゆっくり食べる、そして保育所に行くまで十分な時間的ゆとりをもたせることが大切である。
子どものリズムをみると、寝入りばなに睡眠が深くなり、次に中程度の睡眠が続き、そして深夜の午前二〜三時頃ふたたび睡眠は深くなるといわれる。
ところが、最近の子どもは寝る時間がおそくなっているため、この時間帯が明け方にずれ込み、十分に深い睡眠をとらないうちに起きることになり睡眠不足となる。寝る子は育つという諺があるが、子どもは睡眠中に成長ホルモンが分泌されて成長するといわれており、睡眠不足では健全な成長も期待できないことになる。
以前私達が保育園児の起床から朝食までの時間と食欲や食事バランスを調査したことがある。その結果は起床から朝食まで十五分以内が二七%、十五分から三〇分未満が五〇%であった。朝食までの時間が長いほど、よく食べる子が多く、食事の栄養バランスも整っていた。
子どもは本来よく遊び、よく食べ、よく眠るのが健康のもとである。乳幼児期の健康づくりにあたっては、日常の生活リズムを健康的に整え、規則正しい生活、バランスのとれた食事・十分な睡眠・休養の大切さを身につけさせることが大切である。
――日保協速報 15・4・14
「次世代育成支援施策の在り方に関する研究会」が設置される
厚生労働省では、別々の制度で運営されている現在の子育て支援施策のあり方を検討するために、「次世代育成支援施策の在り方に関する研究会」を設置しました。検討項目としては、
(1)給付の在り方(地域における子育て支援、保育サービス、経済的支援)
(2)財政枠組み(財源)のあり方(現行の公費負担制度、事業主負担などの基本的考え方)
(3)当面の改革の方向
の三項目が検討されることになっています。
次世代育成支援施策の在り方に関する研究会の設置について
(15・4・10 少子化対策推進本部)
[設置の趣旨]
○少子化対策の一段の充実強化が求められる中で、次世代育成支援対策推進法案等が国会に提出されるとともに、十六年度に向けて、児童手当制度、育児休業制度の見直しなどの課題への対応とともに、年金制度改革においても、少子化への対応が課題となっている。
○さらに、規制改革、地方分権等の議論の中で、保育所を始めとする地域の子育て支援施策の在り方について、その将来像を明らかにすることが求められている。
○こうした状況の中で、保育、児童手当など制度、財源が種々に分かれている現行の子育て支援に関連した施策について、総合的な見直しを行い、新たな次世代育成支援施策の在り方の将来像を検討することが必要である。
○こうした認識の下で、今後の次世代育成支援施策、特に、子育て支援関連施策に関する基本的方向や取組について、考えられる選択肢を制度・実務の両面から研究・整理する観点から、有識者により構成される研究会を設置する。
[研究会の開催]
○厚生労働省少子化対策推進本部事務局の研究会(雇用均等・児童家庭局と一体となって運営)
○第一回は、平成十五年四月二十一日(月)十時から開催予定。(会議は非公開。)
[検討項目]
○給付の在り方
種々の制度に分かれる現行の子育て支援に関連した給付に関し、見直しの基本的考え方、給付体系のイメージなどについて
・地域における子育て支援の在り方
・保育サービスの在り方
・経済的支援の在り方
○財政枠組み(財源)の在り方
給付を支える財政枠組みについて、現行の公費、事業主負担などの役割分担を踏まえつつ、その基本的考え方、考えられるスキームなどについて
○当面の改革の方向
次世代育成支援施策の将来像を前提とした場合の当面の施策の基本的方向について
[研究会委員]
・柏女霊峰 淑徳大学教授
◎京極高宣 日本社会事業大学学長
・新澤誠治 東京家政大学教授
・杉山千佳 子育て環境研究所代表
・鈴木眞理子 岩手県立大学助教授
・武石恵美子 東京大学社会科学研究所助教授
・栃本一三郎 上智大学教授
・堀勝洋 上智大学教授
・宮武剛 埼玉県立大学教授
・山縣文治 大阪市立大学助教授
・山崎泰彦 神奈川県立保健福祉大学教授
まとめ
最近の子どもは就寝時刻と起床時刻が遅くなり、また年齢とともに睡眠時間が減って不規則な生活となり、それが朝食時刻を遅らせ、食事時間の不足、朝食の欠食といった悪循環をくり返すことになっている。
人間のからだには体内時計と呼ばれる機能があり、太陽が昇っている間は、人間のからだを活動的にさせ、沈むと休息に入るよう指示する体内リズムがある。
人間の本来の体内リズムに沿って、朝・昼・夕の三食を規則正しくとり、生活リズムを健全なものにしたい。平成十二年に文部省、厚生省、農水省策定の食生活指針には「一日の食事のリズムから、健やかな生活リズムを」として朝食の大切さなど食事リズムの大切さがうたわれている。
参考資料
(1)平成十二年度幼児健康度調査報告書、(社)日本小児保健協会 平成十三年三月
(2)文部省、厚生省、農林水産省決定食生活指針、平成十二年三月
――レポート――
片岡進
「月刊・私立幼稚園」
編集長
女性会長の手腕と執念への期待
全日本私立幼稚園連合会(三浦貞子会長)は先頃、幼児教育の抜本的見直しを求める政策提言を発表し、その対応を政府と自民党に求めました。これは、少子化の進行や幼児虐待、育児放棄に見られる親子関係の歪みなど子どもの問題が拡大していることから、幼稚園・保育園を一体的にとらえて子育てについての哲学と環境をわかりやすく再構築していこうというもので、次の四つの論点を提起しています。
(1)すべての子どもたちに良質な教育を保障する「家庭教育の重要性と子どもを育てる上での家庭の責任を再確認し、その前提のもとで家庭教育と学校教育との連携のあり方を明確にする。その上で幼稚園と保育所における良質な教育をすべての子どもに保障する」
(2)子育て家庭への支援策「労働時間は週四八時間から四〇時間へと劇的に短縮された。その一方で保育所での保育時間は長時間化が進み、週五〇時間から六〇時間の保育も例外ではなくなっている。家庭において幸福に育つという子どもの権利の観点からきわめて遺憾な事態であるばかりでなく、親として育つ機会を保護者から奪うことにもなっている。また保育時間の極端な長時間化は少子化対策としては機能していない。子育て家庭の支援策を、就労のあり方を含めて検討し、有効かつ公正な具体策を立案する」
(3)子ども省(仮称)の設置「幼稚園教育は文部科学省、保育所は厚生労働省という二元行政を解消し、子ども省(仮称)として行政を一本化する。わが国の子どもたちを全体として把握した合理的かつ効率的な施策を展開し、生涯教育の観点から一貫した教育体系を構築する」
(4)利用者にとって平等な公的助成「行政を子ども省(仮称)として一本化した上で、公費の公正かつ効果的な支出を実現する。わが国のすべての子どもたちに公平で、納税者の立場からも適正な公費負担のあり方を確立する」
そしてこの四つの論点を協議し、具体的政策を立案するための機関(小学校入学前の乳幼児の教育・養護のあり方を検討する会議)を内閣府に設置することを求めています。三年前、私立幼稚園の全国組織で初の女性トップが誕生したとき、三浦貞子(ていこ)会長(青森県・白ゆり幼稚園理事長)は「私に対する期待は、混迷する幼・保問題に新しい道筋を作ってほしいということだと受けとめています。その願いに命がけで応えていきます」と約束しましたが、その決意がいよいよ本格的に動き出したと見ることができます。
今回の提言作成の作業は昨年秋から始まり、幼稚園がイメージするもっと具体的な姿を提起する予定だったと聞きますが、結果的には大づかみな理念と方向性を示すにとどまり、後は協議機関に委ねる形になりました。それは当然ながら、保育園側の政策論と積極的に摺り合わせていこうという配慮からで、その姿勢にこそ、過去の提言とは違う強い意志を感じます。
また幼稚園界の中では、保育園化を強める動きと、伝統的なスタイルを守っていこうという動きがあり、その二極化が激しくなっていただけに、全国組織がひとつの方向性を示したことは、内部の結束をはかる上で大きな意味があると言えます。
少子化対応策を模索する自民党は、この提言の考え方は検討する必要があると協議機関の設置に前向きです。幼・保がともに手を取り合って進んでいける道筋ができることを、私も真剣に期待しているところです。
|