|
2.4 船上保守要領
2.4.1 船上保守要領については、一般手入れのほか、下記の点に留意の上、各判定基準に従って十分管理しなければならない。
下記以外の部分については、それらの詳細を記録しておいて、本船が長期係留時或いはドック時に修理を行う。
(1)ワイヤーロープ
1)ワイヤーロープを交換するのかについて明記する。
a. 素線の切れ
ワイヤーロープの1ピッチ間で素線の数の10%以上の素線が切断した場合
b. ワイヤーロープの磨耗
ロープ径の減少が公称径の7%を超えた場合
c. 型崩れ
撚りの戻り、キンク等がある場合
d. 腐食
著しい腐食がある場合
2)ワイヤロープの根止め部分の確認
根止め部分の素線が飛び出していないか、抜けかかっていないか点検する。
3)ボートフォールの交換
2年半を超えない期間でロープの両端を入れ替え、消耗により必要になった場合、或いは5年より短い期間のいずれか早い時期に新換えする。
(2)ボートウインチ
注:ボートウインチの整備のときは、ボートを動かないように十分に固縛しておくこと。
1)オイルの補給及び交換
・オイルが褐色又は乳白色に変色しているときは交換する。
・油量が不足している場合はオイルゲージの中央まで補充する。
2)ブレーキライニングの交換
a. ガバナーブレーキライニング
・ブレーキレバーを取り外した後、ブレーキユニットを取り外し、ブレーキライニングの磨耗状態を点検する。
・ブレーキライニングの焼結層の摩耗、欠落、焼付き、異常なむしれがある場合は交換する。
b. ハンドブレーキライニング:予備品として船内に保管されているのか
・ブレーキレバーを取り外した後、ブレーキユニットを取り外し、ブレーキライニングの磨耗状態を点検する。
・ブレーキライニングの溝が無くなるまで磨耗した場合は交換する。
3)各歯車の歯面を点検し、異常がある場合は修理又は交換する。
4)ベアリング、オイルシールの状態を点検し、異常がある場合は交換する。
適切に潤滑を行うことは重要である。ボートダビットの構造及び作動を十分に理解し、規則的な給脂及び点検を行う。
給脂詳細:
a. グリース
ボートダビット各部にはグリスニップルを備えてある。グリスニップル箇所は1ヶ月に1回の給油を行う。
b. ギヤ油
ボートウインチ内部のギヤ油は、定期的に油量の確認、変色の有無、水分の混入などの点検をする。
c. ワイヤロープ
ワイヤロープ油は、定期的な油切れの有無を点検する他、2ヶ月に1回程度給脂する。
給油箇所
LUBRICATION POINT
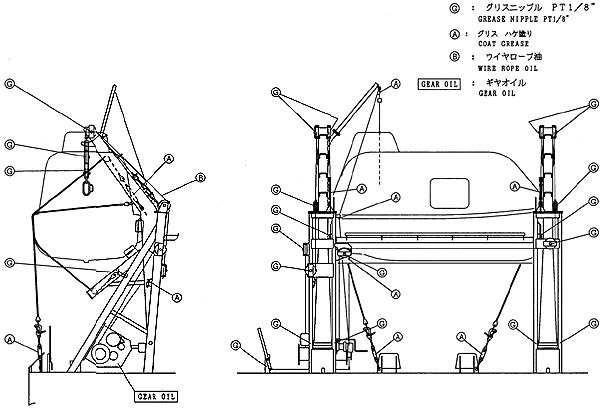
| 項目 |
点検 |
点検整備要領 |
フレーム、ダビットアーム
(ヒンジピン、シーブピン)・
サスペンションブロック |
外観 |
キープレートの変形、ボルトの腐食、折損の有無を確認する。 |
| 作動 |
・ダビットの振り出し及び降下の作動を行い、ヒンジピン及びシーブピン部分から異音、振動、連れ回り等の異常がないか確認する。
注: 異常が認められる場合は、分解してピン及びブッシュの当たり面の状態を確認する。 |
| 開放 (摩耗・腐食の確認) |
・異常が認められる揚合は、分解してピン及びブッシュの当たり面の状態を確認する。
・異常の原因となる部品は修正又は新替えする。
・必要があれば、ボルト・ナットの増し締めを行う。 |
| グリスの点検・給油 |
・グリスガンで新しいグリスを給油し、グリスが軸受け部周辺に十分行き渡っていることを確認する。
・必要があれば、グリス穴の詰まり、グリスニップルの変形がないか確認し、異常があれば整備する。 |
ダビットアーム
ストツパー装置 |
外観 |
溶接部の欠陥、キープレートの変形、ボルトの腐食、折損の有無を確認する。 |
| 作動 |
・ハンドルの作動、ストッパーの離脱に問題がないことを確認する。
注1:格納時にボートフォールにより荷重を指示された状態で確認作業を行う。
注2:異常が認められる場合には、分解して確認する。 |
| 開放 (摩耗・腐食の確認) |
・異常が認められる場合は、分解してピン及びブッシュの当たり面、ストッパーの当たり面の状態を確認する。
・異常の原因となる部品は修正又は新替えする。
・必要があれば、ボルト・ナットの増し締めを行う。 |
| グリスの点検・給油 |
・グリスガンで新しいグリスを給袖し、グリスが軸受け部周辺に十分行き渡っていることを確認する。
注:必要があれば、グリス穴の詰まり、グリスニップルの変形がないか確認し、異常があればグリスニップルを交換する。 |
| ボートフォール |
外観 |
ボートフォール表面に摩耗・腐食の他素線切れ、型崩れの有無を確認する。 |
| 使用限界基準 (摩耗・腐食) |
異常が認められる場合は、下記の基準に照らし合わせて新しいボートフォールに交換する。
1. 素線切れ
ワイヤロープの1ピッチ間で素線の数の10%以上の素線が切断しているとき。
2 摩耗
ロープ径の滅少が公称値の7%を超えたとき。
3. 型崩れ
撚りの戻り、キンクがある場合。
4. 腐食
著しい腐食がある場合。 |
| グリスの塗布 |
・ボートフォール表面に、油(製造者により指定されたワイヤコンパウンド又はグリス)を塗布する。 |
| 端替え |
・2年半を超えない期間でワイヤの両端を入れ替える。 |
| 新替え |
・5年を超えない期間で新替えする |
| アジャスト用ターンバックル |
作動状態の確認 |
・外観検査により、ターンバックルに損傷、部品の脱落、腐食が無いか確認する。
・必要に応じてターンバックルを操作し、ボートフォールの長さが調整できることを確認する。
・必要に応じて、ボルト、ナットを増し締めする。 |
| ラッシングライン |
外観 (摩耗・腐食の確認) |
・外観検査により、ラッシングワイヤ表面に摩耗・腐食の他、素線切れ、型崩れの有無を確認する。
・外観検査により、ターンバックル、ワイヤ金物(シンプル、ワイヤクリップ、シャックル)に摩耗・腐食・変形などの異常がないか確認する。
注:著しい異常が認められた場合は、新しいものと交換する。 |
| 緩みの確認 |
・救命艇をダビットに格納し、サスペンションブロックがダビットアームホーンに乗っている状態でラッシングしてあることを確認する。
・ラッシングに緩みがある場合は、ターンバックルを増し締めする。 |
| 作動状態の確認 |
・ウインチのブレーキレバー及び舷側操作装置のトグルピンを抜き取り、舷側操作装置のレバーを操作し、ウインチのブレーキレバーが問題なく持ち上がることを確認する。 この時、ブレーキレバーが開放されることを確認する。
・舷側操作装置のレバーを戻したとき、ウインチのブレーキレバーが規定の位置まで問題なく下がること。
注:前記の確認を行った後、舷側操作装置により、ダビットの振り出し、降下の作動試験を行い、舷側操作装置によりブレーキ装置の制御が正常に働くことを確認する。 |
| グリスの塗布 |
・舷側操作装置の軸受け部及びリモコンワイヤにグリスを塗布する。 |
| 舷側操作装置 |
試験前の確認 |
試験前に次のことを確認する。
1. ウインチのブレーキレバーは水平か確認する。
2. ブレーキレバー中心の六角ボルトに緩みはないか確認
3. ブレーキレバーサポーターに変形はないか確認
4. リモコンシープブロックにワイヤが引っかかる要因はないか。
5. リモコンワイヤに腐食、変形等の異常はないか
上記の項目で異常があれば調整又は新替えする。
注:ダビットを格納し、ダビットストッパーをセットした状態で舷側操作装置を単独で作動させる。 |
| 作動状態の確認 |
・ウインチのブレーキレバー及び舷側操作装置のトグルピンを抜き取り、舷側操作装置のレバーを操作し、ウインチのブレーキレバーが問題なく持ち上がることを確認する。 この時、ブレーキレバーが開放されることを確認する。
・舷側操作装置のレバーを戻したとき、ウインチのブレーキレバーが規定の位置まで問題なく下がること。
注:前記の確認を行った後、舷側操作装置により、ダビットの振り出し、降下の作動試験を行い、舷側操作装置によりブレーキ装置の制御が正常に働くことを確認する。 |
| グリスの塗布 |
・舷側操作装置の軸受け部及びリモコンワイヤにグリスを塗布する。 |
| 艇内リモートコントロール装置 |
試験前 |
試験前に次のことを確認する。
1. ウインチのブレーキレバーは規定の位置か確認する。
2. ブレーキレバー中心の六角ボルトに緩みはないか。
3. ブレーキレバーサポーターに変形はないか。
4. リモコンシーブブロックにワイヤが引っかかる要因はないか。
5. リモコンワイヤに腐食、変形等の異常はないか。
6. リモコンウエイトの取り付け位置は適正か。
7. 救命艇内に導入されたリモコンワイヤに引っかかる要因はないか。
上記の項目で異常があれば調整又は新替えする。
注:ダビットを格納し、ダビットストッパーをセットした状態で艇内操作装置を単独で作動させる。 |
| 作動状態の確認 |
・ウインチのブレーキレバーのトグルピンを抜き取り、救命艇内からリモコンワイヤを引きウインチのブレーキレバーが開放されることを確認する。
・艇内のリモコンワイヤを戻したとき、ウインチのブレーキレバーが規定の位置まで問題なく下がること。
注:前記の確認を行った後、艇内操作装置のワイヤを救命艇内から操作し、ダビットの振り出し、降下の作動試験を行い、艇内操作装置によりブレーキ装置の制御が正常に働くことを確認する。 |
| グリスの塗布 |
艇内操作装置のリモコンワイヤにグリスを塗布する。 |
| その他 |
外観検査 |
・塗装及び腐食の進行している部分はブラシサンダー等で下地処理の後、錆び止め塗装、仕上げ塗装を行う。
・検査点検作業で塗装が剥離した部分はただちにタッチアップを行う。
・トグルピン類、ボルト・ナット類で著しい腐食・損耗が見られるものは新替えする。
・操作説明銘板、注意銘板、シンボルマークで著しく表示が不鮮明になったものは新替えする。 |
|
|