|
アンケートより
実演家へ
学校にとって実演家はパートナー
ゲストとして招かれて実演を行う―実演家と学校との関わりは、このケースがほとんど。しかもその多くは、比較的少人数での実演を鑑賞するという一方通行になりがちです。実演の経験回数も1回から多くても4回。子どもたちの自由な発想や創造力を育むことができるパートナーとなるには、先生との緊密な協力、プログラム内容の研究、実践とフィードバックの積み重ねなどがもっと必要です。
●学校で、参加した実演プログラムは?
課外活動の指導を除くと、鑑賞を中心とした公演がほとんど。先生対象の体験研修や授業への協力機会も増えているようですが、提供可能なソフトやノウハウの開発はまだ十分とはいえません。
| (拡大画面:90KB) |
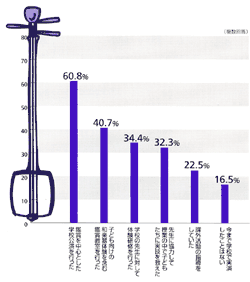 |
●和楽器導入に実演家の協力は必要なの?
ほとんどの先生方は、専門家の協力を仰ぎたいと考えています。和楽器のことをよく知らない、生徒に実技を教えられるほど習熟していない―など、自分だけで授業を行うのは難しいと感じる先生が多いということでしょうか。
●どんな協力がほしい?
ナマの演奏を見せる、聴かせる。次いで、実技指導・講義、体験学習など。そこには、専門家の手腕に期待するところが大です。しかし、どう協力してほしいかという点では、それぞれの先生の知識やキャリア・目的意識・学校環境によってかなり違いがあり、具体的なイメージを描けないという先生もいます。
| (拡大画面:27KB) |
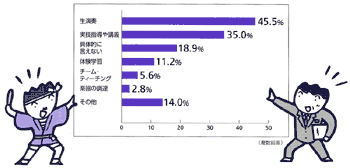 |
アンケートより
学校の先生へ
「地域」と「ひと」が生み出す関係づくり
実演家と学校をつなぐキーワードは「地域」と「ひと」。学校へ行ったことのある実演家たちの多くは、知り合いから頼まれて・・・と答えています。自分から積極的に働きかけてという例はあまり多くはありません。受け身の実演家の姿に、外からのサポーターを受け入れにくい学校の状況が重なります。地域の実演家と学校が、お互いをよく知り、親しく気軽に付き合えるような関係づくりが求められています。
●協力者はだれ?―お願いする人、される人
実演家が学校を訪れるきっかけは、大きく2つのパターン。(1)身近な「知り合い」を介して依頼された、(2)所属する協会組織などから派遣された、というもの。もっといろいろな可能性を探ってみてもよいのではないでしょうか。
| (拡大画面:39KB) |
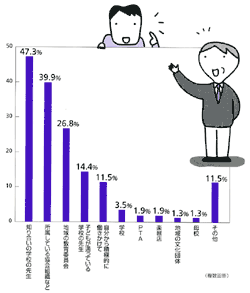 |
●実演家の外部講師経験度は?
鑑賞教室や音楽の授業に、邦楽の実演家を招いたことのある先生は半数余り。ほとんどが鑑賞主体のプログラムです。実演家が先生のパートナーとして授業に関われるような関係づくりは、まだ特別なものと捉えられているようです。
●協力者は身近にいる?!
実演家を外部講師として招いた経験のある先生のうち、約8割が地域の実演家の協力を得たと答えています。専門家としての技術や知識以上に、地縁を優先する傾向があります。
| (拡大画面:10KB) |
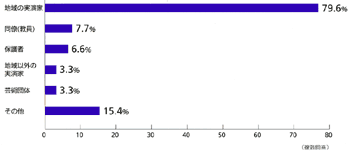 |
アンケートより
学校の先生へ
学校と実演家、聞きたい?聞けない!関係
実演家の協力はほしいが、どれくらいの経費が必要なのか見当がつかない。「いくら?」と聞くのは失礼だし、支払えそうもない金額を提示されても困るし・・・。謝礼の相場や適正価格はあるのだろうか?なんとなく敷居が高そうに見える邦楽の世界。知識や経験が乏しいことがネックになっているようです。お願いしたいこと、できること、お互いに情報や知識を共有するための努力は欠かせません。
●実演家への謝礼の額は?
謝礼の実態は千差万別。所属団体から実演家が派遣される場合は最低限の報酬が予算化されているようです。それ以外には、給食の提供から楽器の借用料、運搬費が用意された例もあります。相互にきちんとした予算項目や経費に対する認識が必要でしょう。
●和楽器授業―なにが不安?
実演家への協力依頼をためらう理由はさまざま。予算や時間がないことが最大のネックです。どうやらその根底には「邦楽の世界や実演家たちについてよく知らない」という不安感が潜んでいるようです。
| (拡大画面:104KB) |
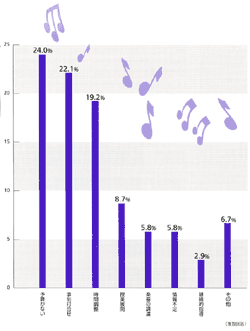 |
|