|
2. 長門地区精神保健家族会の行っている事業(その2)
(2)長門地区精神障害回復者共同作業所事業
(目的)長門健康福祉センター管内の障害者に対し、共同作業を通して、社会生活の適応と社会復帰の促進を図る。
(1)共同作業の運営及び指導
(2)社会生活及び家庭生活上必要な学習
(3)レクリエーション等の活動を通じた社会適応訓練
(4)その他、目的を達成するために必要な事業
◎平成13年度事業実績は・・・
1. 業務報告
(1)開所状況
a. 開所時間 9時00分から16時00分まで
b. 開所日数 年間217日 月曜日から金曜日
(2)通所訓練実施状況
a. 通所者実数(月平均21.4人) 在籍者数A24人 年間実人数3,004人
|
(拡大画面:76KB)
|
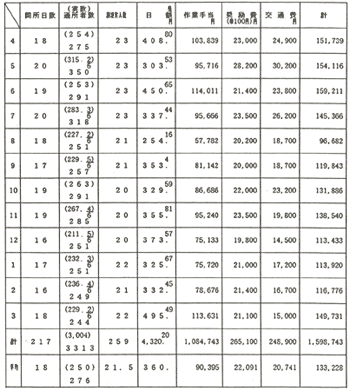 |
(3)社会復帰した者
| (内訳) |
|
| ・就労 |
3人 |
| ・家業・家事(手伝いを含む) |
0人 |
| ・その他 |
0人 |
| 小計 |
3人 |
|
(4)中止した者
| (内訳) |
|
| ・再入院 |
0人 |
| ・死亡 |
1人 |
| ・その他 |
0人 |
| 小計 |
1人 |
|
(5)社会復帰した者の割合 3/24・・・12.5%
(6)継続している者 19人
(7)その他(中止・継続の分類不明 3人) (新規2人)
2. 反省と今後の対策
・作業所で行っている作業種目の内、自動車配線部品の組立作業は車種が増えて、作業内容も複雑化してきている。
・平板の節の埋木作業は、会社側の計画が市場ペースにあわなかった。
・コーヒー販売事業も市内大手の販売価格に押され売上が伸びなやんでいる。
・平成10年度以降経済不況下の作業出来高は下げ止まりとなった。
・通所することで生活のリズムを取り戻し、作業能力を回復して自信をもち、指導者に相談したり、自分で仕事を捜したりする者がいる。また、この作業所の活動が再発防止や社会参加につながっている。
・毎週金曜日には通所者・ボランティア交流会 デイケア会をおこなっています。
※第2金曜日 共同作業所・ボランティア(若鯉会)交流会が盛会。
※第1・3・4金曜日はデイケアで新年会・書道・花見・ボーリング大会・水泳会・研修旅行・忘年会・クリスマス会等をにぎやかにやっています。
|
(拡大画面:90KB)
|
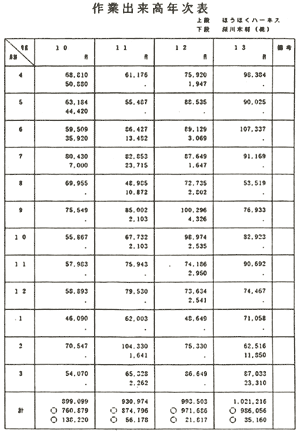 |
3. 今後の課題
(1)現在言われているいくつか判っていること。
◎この病気は残念ながら長期化、慢性化しやすい病気。
◎「完全寛解(治癒ということ)に至るのは全体の1/3にしか過ぎない」と言われている。
◎「陽性症状が強く、興奮している時は抗精神病薬を服用し、入院などで静かな環境を確保するのがよい」と言われる。
◎「社会から隔絶された環境に長くおかれると、陰性症状が悪化し、「施設症」が起きる。社会適応がますます困難になる」と言われている。
(2)社会の中の根強い偏見とは・・・
「決して治らない」
「恥ずかしい病気」
「遺伝のせい」
「親の育て方が悪かった。」
「このことが患者本人や家族さえ、そう思いこんでいることが少なくない」と言われているときく。
(3)「親亡きあと−」と思う心は・・・
この親が思う心情をこうとらえたとしたら・・・(世話人になってから5年余、ずっと考え続けて、結論が出ないままに・・・)
“私が死んだら、その先この子はどう生きてゆくのだろうか。それならどうしてやったらよいのか・・・と”
社会の中の根強い偏見に押し潰されているのではないだろうか。これは親側から見た“おもい”でしょう。それでは「その子」はどのように考えたら良いのでしょう?「その子」=「この子」は何もそんな悩みは知らないのではないでしょうか(親の思いを知らない。)・・・だとしたら“親の死後、当事者が困らないように自分独りで楽に生きていける術を身につけさせることが必要でしょう。私(親)が生きている間、早いうちから(退院可能になったら)、地域社会の中でリハビリをさせることでしよう。(作業所やデイケアセンターで)
(4)いくつかの視点
◎共同作業通所者はおおむね“受け入れてくれる家族”がいる。
◎グループホーム入居者はおおむね“受け入れてくれる家族”がいない。
◎当事者にも普通の人と同じように老後がやってくる。
◎各人いずれも異なった人生(ケース)である。
4. 障害者の安心・安定を求めて
〜目標〜 みんな仲良く 助け合い 健康に 明るく暮らそう。
※・・・働き場をともに捜して=グループホーム当事者に援助する
地域内の業者「ハローワーク」を訪問し仕事探し・・・
※・・・障害者の作業可能な発注企業廻りして
毎月の目標高を定めて「ハローワーク」や企業廻り・・・
障害者の主な自立生活の指針は
・経済的自立
就労により生活費用を稼ぐことが出来る。
年金や生活保護費を自分で管理できる。
・身辺自立
困った時や介護が必要になった時・・・
どこに相談したらよいか知っておく。(相談相手がいる。)
・精神的自立
自己決定や自己選択ができる。
自分がしたことの結果に責任がとれて納得する。
・社会的自立
社会の普通の秩序・道徳が守れ、身につける。
四つの自立の内、実際に必要なことは
・グループホーム当事者はお金儲けに一生懸命になる。
・共同作業所通所者は作業手当支給日(毎月10月)に出勤者も多く、支給額や単価の高い作業に注目が集まる。
障害者の経済的自立をまず保障することから
◎閉じ込めたり、置き去りにしないよう、地域でふつうの生活を送る方策や制度として支援体制づくりの推進をはかろう。
◎みんなと同じように老後がくるし、生きる術を身につけてもらおう。
そのためには長期社会的入院者をつくらず、退院して町で暮らせるよう援助しよう。
支援ネットワークの作り方
保健所には情報が集まりやすいため、保健所・保健婦が核になることが望ましい。その周囲に医療、福祉、民生委員、社会復帰施設指導員がネットワークされ、必要に応じて精神障害者本人の家族、友人、職場の同僚・上司などを呼び入れて個別に対処する。定期的なケース検討や情報交換、勉強会を持つことが必要。
|