|
VI. 持ち物と注意
1. 持ち物
・帽子(ひさしの大きい方が影ができて、水面の光反射を防ぎ、水中が見やすい)
・軍手、マイナスドライバーかピンセット(水中に落としやすいので紐をつける)
・履物(海岸のタイプによる:本文参照)
・プラスチック製箱(壊れない、浮く、逃がさない:採集物を入れるので透明で蓋つきがよい、ポリ袋が良く使われるが、軟らかいものがつぶれたり壊れやすい)
・水中眼鏡(マスク型:箱めがねの代わりにもなる)
2. 注意 楽しく、有意義な時を過ごすためには、次の点に注意してください。
(1)浜辺には、いろいろなゴミや貝殻などが流れ着いている。特に、廃油ボールに触れると非常に厄介なことになる。足元に注意をはらう。
(2)磯や崖では、岩の上など滑りやすいので、常に前かがみの姿勢でゆっくりと歩く。
(3)干潟にはいろいろなゴミや貝殻等が埋まっていて、足を怪我することがある。また、草履や運道靴などでは、砂で擦り傷をつくることがある。観察揚所の海岸のタイプに適した履物を工夫する。
(4)危険な動物に注意する。関東周辺には次のような動物が時々見られる。
*ウツボ、トラウツボ(鋭い歯)、ガンガゼ、ラッパウニ(毒針)・・・岩の下や穴、窪みに不用意に手を突っ込まない。
*ゴンズイ、ハオコゼ、オニカサゴ、ミノカサゴ(背びれや胸びれに毒針)・・・砂地の海底にいる。踏みつけたりすることがある。気絶するほど痛い。
*アカエイ、トビエイ(尾のつけねに毒針)・・・海底の砂地に潜っている。
*シロガヤ(刺す、有毒)・・・岩に海藻などに混じって付着している。
*カツオノエボシ(刺す、有毒)・・・水面に浮遊していたり、波打ち際に打ち上げられていたりする。俗称「電気くらげ」。クラゲ類は一般的には刺す。
*ヒョウモンダコ(噛む、有毒)・・・コントロールできないので、絶対触らない。
*ベッコウイモ(刺す、有毒)・・・海藻のある岩の溝などにいる。イモガイ類は要注意。
*フジツボ、カキの仲間(殻で切り傷)・・・岩の表面などに付着している。
よく目に触れる者たち
★危険な連中
| (拡大画面:41KB) |
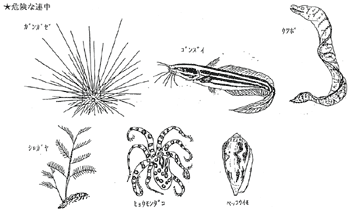 |
★お友達になろう
海綿動物
腔腸動物
へン形動物
環形動物
節足動物
| (拡大画面:52KB) |
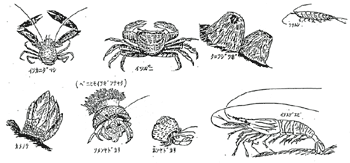 |
軟体動物
| (拡大画面:43KB) |
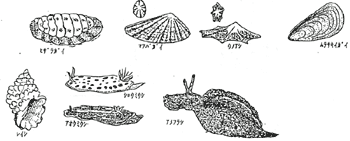 |
キョク皮動物
| (拡大画面:25KB) |
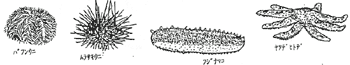 |
原索動物
脊椎動物
緑藻植物
| (拡大画面:20KB) |
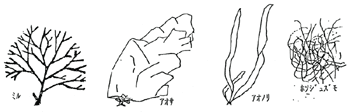 |
褐藻植物
| (拡大画面:41KB) |
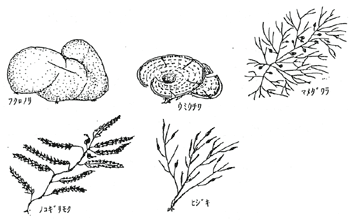 |
紅藻植物
| (拡大画面:27KB) |
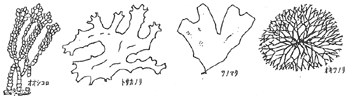 |
種子植物
|