|
(まとめ)
1. 「ちょっと遊んでみよう」は、遊んでみてどうでしたか。
(1)アラレタマキビ
コップに海水を汲んで、アラレタマキビ(タマキビでもよい)を10個体ほど入れて、その行動を観察してみよう。
| 今まで干からびて死んだように動かなかったのがいっせいに動き出す。慌てふためくように、水の中から逃げ出す。アラレタマキビは海にすむ動物なのに、海水中を好まない。これらの貝がどこにいたのか、もう一度見直してみよう。潅水帯の動物である。採餌と生殖時は海水中に入るが、後はひたすら寝て暮らす仲間だ。頑張り時を捉え損なったら大変。 |
|
(2)アメフラシ
もし、アメフラシをみつけたら、浅い潮溜まりの中に置いて、背中の襞の間を指で探って見よう。中はどうなっているか。何が起きるか。
| 指先に何か硬いものが触る。薄い貝殻が体内にあるのだ。巻貝の仲間であることの証拠である。こんなにぐにゃぐにゃで、敵が来たらどうするのだろう。ちょっといじめて見るとわかる。紫色の汁が海水中に広がってくる。タコの墨のように。特技を持とう。 |
|
(3)カニ
潮溜まりの中に、カニの死骸が沢山落ちていないか。カニにとってそんなに悪い環境なのだろうか。そっと拾って、丁寧に観察しなさい。特に眼や甲羅の後部と腹側の継ぎ目を上にちょっと引っ張ってみる。
| 箱の蓋が開くように、甲羅の後端部が上に開く。目を見ると、そこだけ透明であることに気づくだろう。これは死骸だったのではなく、目やひげや足先まできれいに抜け出てしまった脱皮殻だ。環境は悪いのではなく、逆にカニにとって成長できるとても良いという証拠なのだ。カニは、硬い鎧のような殻を着ている。だから、それを脱ぎ捨てないと大きくなれないからである。古い殻を脱ぎ捨てて、大きく成長しよう。 |
|
(4)カサガイ
マツバガイ、ヨメガカサなどの大きめのカサガイを見つけたら、素手で獲る工夫をしてみよう。
| タコはエビやカサガイや二枚貝が大好物である。タコが近づいてくると、貝達は固い貝殻の中に閉じこもる。一旦閉じこもった貝殻は、人の力をしても開くことができないほどしっかりとくっ付いている。ところが、結局は食べられてしまう。貝の閉殻筋(貝柱)は、急激な力に対しては、非常に強くて、開くことができない。ところが、静かにじっと貝を引っぱっていれば、ついには開く。ついつい気が緩むのかもしれない。タコも、どうしても食べたい時には諦めずじっと引っ張りつづける。継続は力なり。 |
|
(5)二枚貝の貝殻
打ち上げられている二枚貝の貝殻を見てみよう。きれいな丸い穴が開いているものがいくつもある。この穴はどうしてできたのだろう。
| 磨り減ったと主張する人は、実験してみる。こんなにうまくはあかない。犯人はツメタガイで、酸で根気よく穴をあけて、消化液を注ぎ込んで、消化できたところで吸い取りご馳走様。シジミやハマグリ養殖場の大敵。もし運良くツメタガイを見つけたら、海水に中に入れて観察すると面白い。出るわ出るわ、貝殻の3・4倍の大きさの座布団のような足が貝殻の中から。物理的に常識には外れますが。固定観念から一歩踏み出そう。 |
|
(6)褐藻類と緑藻類
観察できた褐藻類の数と緑藻類の数を調べ、次の式で計算して、その数値を表の数値と比べてみなさい。どのようなことがいえるか。
| (観察できた緑藻の種類数) ÷ (観察できた褐藻の種類数) = ? |
| 三陸 |
常陸 |
房総 |
南伊豆 |
紀伊 |
伊豆大島 |
神津島 |
八丈島 |
鹿児島 |
| 0.4 |
0.5 |
0.6 |
0.6 |
0.6 |
0.7 |
0.9 |
1.5 |
0.9 |
|
日本の海は、海藻の種類も量も非常に豊富である。北に行くにつれて種類数は減少し、コンブなど褐藻類の大型のものが多くなる。南に行くにつれて緑藻類が多くなり、さらに熱帯の方に行くと普通の海藻は見られなくなり、植物プランクトンや石灰藻と呼ばれる紅藻類の仲間ばかりが目につく。太陽光の強さと水温が大きく影響している。
緑藻と褐藻類だけを比較するこの方法は、日本付近で適用できる方法かもしれないが、その法則性に気づいて貰いたい。視野をどんどん広げよう。新しい考えの手がかりが得られる。 |
|
2. 関東付近の磯で観察できる主な動物と海藻
(1)動物
| 原生動物門 |
(ヤコウチュウ) |
| 海綿動物門 |
ダイダイイソカイメン、クロイソカイメン、ムラサキカイメン、ツボアミカイメン |
| 腔腸動物門 |
ミズクラゲ、ヨロイイソギンチャク、ウメボシイソギンチャク、タテジマイソギンチャク、イソバナ、カイウミヒドラ、シロガヤキクメイシ、(カツオノエボシ)、(ギンカクラゲ) |
| 扁形動物門 |
ツノヒラムシ、ウスヒラムシ |
| 紐形動物門 |
クロヘラヒモムシ |
| 苔虫動物門 |
ミサキアミガイ |
| 星口動物門 |
サメハダホシムシ |
| 環形動物門 |
ゴカイ、スゴカイ、ウズマキゴカイ、ヤッコカンザシ、ケヤリムシ、クマノアシツキ |
| 軟体動物門 |
ヒザラガイ、ケハダヒザラガイ、ケムシヒザラガイ、ヤスリヒザラガイ、ウズヒザラガイ、マツバガイ、ウノアシ、ヨメガカサ、ツタノハ、ベッコウザラ、サザエ、コシダカサザエ、スガイ、イシダタミ、クロズケガイ、トコブシ、クボガイ、ウラウズガイ、ニシキウズガイ、バテイラ、エビスガイ、ギンタカハマ、アマガイ、アマオブネ、タマキビ、アラレタマキビ、オオヘビガイ、マガキガイ、イボニシ、レイシ、シワホラダマシ、カコボラ、ボウシュウボラ、オニサザエ、イソニナ、ヘナタリ、ホソウミニナ、ハナビラダカラ、イトカケガイ、キクノハナガイ、タツナミガイ、アメフラシ、シロウミウシ、クロシタナシウミウシ、アオウミウシ、ホウズキフシエラガイ、クモガタウミウシ、アサリ、ケガキ、ムラサキインコ、ムラサキガイ、マダコ |
| 節足動物門 |
ウミユスリカ、イソカニムシ、シマウミグモ、クロフジツボ、アカフジツボ、イワフジツボ、カメノテ、フナムシ、イソヨコエビ、イソスジエビ、テッポウエビ、アシナガモエビ、ホンヤドカリ、オニヤドカリ、イソヨコバサミ、イソカニダマシ、コノハガニ、ヒライソガニ、ヒヅメガニ、イソクズガニ、ショウジンガニ、スベスベマンジュウガニ、(ウミホタル) |
| 毛顎動物門 |
(ヤムシ) |
| 棘皮動物門 |
ムラサキウニ、バフンウニ、コシダカウニ、ナガウニ、アカウニ、タコノマクラ、マナマコ、ウミシダ、クモヒトデ、ヤツデヒトデ、イトマキヒトデ、モミジガイ |
| 原索動物門 |
イタボヤ、ユウレイボヤ、マメボヤ、ベニボヤ、(ギボシムシ) |
| 脊椎動物門 |
ウツボ、トラウツボ、ギンボ、メジナ、アゴハゼ、キヌバリ、カエルウオ、クサフグ、キタマクラ、ソラスズメ |
|
(2)植物
| 褐藻植物門 |
フクロノリ、ウミウチワ、マメダワラ、ノコギリモク、ヒジキ、ホンダワラ、ワカメ、カジメ、アラメ、ウミトラノオ、イソモク、イシゲ |
| 紅藻植物門 |
トサカノリ、ツノマタ、オキツノリ、オオシコロ、フクロフノリ、マフノリ |
| 緑藻植物門 |
ミル、アオサ、アオノリ、ホソジュズモ |
| 種子植物門 |
アマモ、(イソギク)、(トベラ)、(ラセイタソウ) |
|
| (拡大画面:122KB) |
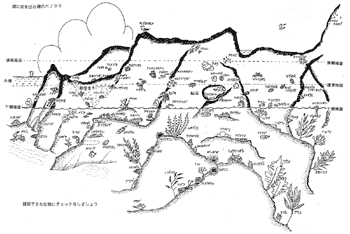 |
|