|
IV. 生物観察
1. 浜 日が高くなる前に波打ち際の漂流物の中を見よう。海水中は、水中眼鏡をつけて、ゆっくりと移動しながら海底を観察する。潜水するのがよいが、背のたつところで覗いてみるだけでも、試してみる価値は充分にある。しかし、動物達は拡散していて種類数も個体数も少ないし、一般的な生物観察には向かない場所である。もし、海水がよどんでいるような所があれば、赤潮などを観察できるかもしれない。赤潮は、異常発生した動植物プランクトンの集まりである。持ち帰り、顕微鏡で観察すると、ツノモなどに混じって原生動物のヤコウチュウ(夜光虫)が見つかることもある。
(1)植物 砂浜には、分類上のグループ名はないが、海浜植物と言われるものが見られる。塩分を避けるためか、共通して肉厚か有毛のもの、あるいは硬い葉の陸上植物が多い。ハマナデシコ、イソギク、トベラ、ハマボウ、ハマオモト(浜木綿)、ハマヒルガオなどが生育する。
浅い海底は砂が移動しやすく不安定で、海藻は殆んど見られない。波の影響などがやや緩和される明るい海底には、種子植物のアマモの仲間などで陸上の草原を思わせる景観が見られることもある。また、海底を離れて波のまにまに漂う流れ藻として、いろいろな種類の海藻が流れ着き、打ち上げられ、時には珍しい種を見つけることもある。台風などで海の荒れた日の翌日はチャンスだ。
(2)動物 夕方の砂浜には、スナガニの仲間が目にも止まらぬ速さで走り回っている。打ち上げられた海藻にはトビムシやヨコエビ、ワレカラ、小型の貝類などが見つかる。はるばる遠くの地方から運ばれ、あるいは付近の海にすむ各種の動物達が打ち上げられていることもある。外洋棲で、普通はなかなか見られないアサガオガイやルリガイを採集したこともある。砂地の海底には、二枚貝の仲間、バイやツメタガイなど砂地棲の巻貝、カレイやウシノシタなどの魚類が、砂に潜るようにして目だけ出している姿を見かけることもある。砂でできた底の抜けたお椀を見つけたら、ツメタガイの卵だ。ゴンズイやハオコゼに刺されると動けなくなる。ゆっくりと移動するようにしよう。初夏の波打ち際には、サメの子供が波と戯れるように泳いでいるのを見ることもある。
2. 干潟 海には機械類はなるべく持参したくないが、ここでは双眼鏡が威力を発揮する。どこかに腰を据えて、じっくり観察して欲しい。履物は、ゴム長靴が最適で、素足は危険である。
(1)植物 海側の砂泥地では、植物は付着性の珪藻などが殆んどであるが、暖かい地方にはヒルギなどいわゆるマングローブが見られることもあるし、また、淡水の多い所ではアシなどが生い茂り、多くの動物達に隠れ家を提供している所もある。一般的には、あまり植物の種類が豊富な所とはいえない。
(2)動物 付着性珪藻や泥中の有機物などを食べるゴカイやカイ、カニ、ハゼなどや、それを捕食するシギ、チドリなどの鳥が見られる。種々の条件により多種多様な干潟があり、種類数も個体数も豊富な所である。地域によっては、スコップで掘り返せばギボシムシのように珍しい動物を見ることもできる。水中から出て歩き跳びまわるムツゴロウやシオマネキなどは有明や諫早の干潟で有名であるが、トビハゼやコメツキガニなどは広く分布する。カモメ、カモ、シギ、チドリ、サギなど水鳥の餌場や休憩場所としても利用されている。衣服の汚れを気にしなければ、動物観察には面白い場所である。
3. 磯 非常に滑りやすく、転倒すると思わぬ大事故になることもある。スパイク付きやフェルト底の履物などが良いが、昔から藁草履・草鞋が良く使われてきた。ゴム底や鼻緒の抜けるビーチサンダルは絶対に利用しない。また、草履や草鞋をはいても、足袋や厚手の靴下をはくことを勧める。貝殻で切ったり、棘を刺したりするのを防げる。軍手も、切り傷や針棘から守ってくれる。
泳ぐわけではなくても、マスク型の水中眼鏡を用意すると良い。水中眼鏡で、ちょっとでも海の中を覗いて見て欲しい。たとえ50cmの水深でも、そこには水族館で見るようなパノラマが用意されている。漁師の使う箱めがねでもよいのだが、大きくて邪魔になることもある。
(1)植物 岩礁の表面にはアオサ、ヒトエグサなどの緑藻類、ヒジキ、ウミトラノオなどの褐藻類などが見られる。水中には更に多くの小型の海藻類、波の打ち寄せる磯の周縁部にはカジメ、アラメなどの大型の海藻、岩礁に囲まれた海底にはフクロノリやウミウチワなどの海藻、岩の下のほうには、石灰質を多く含んでごわごわしたオオシコロなどの珊瑚藻の仲間も見られる。
(2)動物 海藻が多く、岩礁の構造が変化に富む磯は、海岸動物の宝庫である。波が届かず飛沫だけが時々かかる岩の上から、岩の隙間から岩の下、岩礁と岩礁の間の水路、岩礁の凹みで引き潮に取り残された潮溜り(タイドプール)、波に叩かれる周縁部などいたる所を餌場として、隠れ家として非常に多種多様な動物達が利用している。
海水に直接触れることはあまりないと思われるような高い所にも、フナムシ、アラレタマキビなどが這い上がっている。
潮の引いた岩の上には、タマキビ、イシダタミ、フジツボなどが、岩の割れ目にひしめき合ってアマガイやイシダタミ、砂粒をつけてカモフラージュしたヨロイイソギンチャクなども見つけることができる。オオヘビガイやヤッコカンザシのように岩の表面に石灰質の曲がりくねった巣を造って潜りこんでいるものもいる。貝殻を8枚も持ったヒザラガイの仲間もこの辺りに多い。岩から絶対離れないと言っているように、しっかりはりついたカサガイの仲間も多い。何処からかパチンパチンと音が聞こえてきたら探してみて欲しい。テッポウエビが、はさみの先で音を出しているのだ。
適当な岩をそっと引き起こしてみよう。小さなカニやヤドカリ達が右往左往している。引き起こした岩には、ぺらぺらの動物が岩の表面を滑るようにして逃げてゆく。ツノヒラムシなどの仲間だ。カニのような形で平べたく、よく見るとひげが長く、脚が4本半(片側)のカニダマシなども張り付いていることがある。観察したら岩はそっと元のとおりに戻しておこう。干からびたら可哀想だ。
大きな岩と岩との間には黄色いカメノテが押しつぶされたように挟まっている。まるで貝のような殻を持つカメノテやフジツボがカニやエビの親戚だとは驚きだ。
海藻が付着しているような水中には、多くの貝類が見られる。内分泌撹乱物質(環境ホルモン)で有名になったイボニシも、波に洗われるこの辺りに見られる。大きな岩の下を覗いてみると、橙色や紫色のイソカイメンの仲間や、美しい斑点模様のある寒天が岩に貼りついたイタボヤ、泥色の筒の先からなんともいえない美しい花(?)を開くケヤリムシ、ミニチュアのサンゴのようなイソバナ、ヒトデ、ナマコ、ウニなども見つかるだろう。真っ白な小さなシダのように見えるシロガヤは触れると刺される。嫌われ者のナメクジのような体形を、美しい色で飾るウミウシがいるかもしれない。近年、いろいろなウミウシ達がダイバー達のターゲットにもなっている。
少し深みを覗いてみよう。大型の海藻の林の間をメジナやフグの仲間、運がよければヨウジウオや南から来たチョウチョウウオなどに出くわすかもしれない。岩の下にはうかつに手を入れないで欲しい。サザエやアワビがいるかもしれないが、ウツボに噛みつかれて大怪我をする確立の方が高い。なお、サザエやアワビはどこの海岸でも、地元の漁業権に触れるので見るだけにすること。
そして磯での観察で、最も力を注いで欲しいのが、潮溜まりの観察である。潮溜まりは、磯に棲む動物達の集約のような場所である。潮が引いていくために、近くから皆が避難してきているのだろうか。日差しが強く、水温が温泉のようにかなり高くなり、生物にとっては非常に過酷な環境になるが、次の満ち潮をひたすら待っているのだと思う。愛情を持って、丁寧に観察しよう。アゴハゼや何とも表現の仕様のないグロテスクなアメフラシなども見られるかもしれない。初夏の磯で、黄色や橙色のラーメンの玉みたいな海そうめんを見たら、アメフラシの卵だ。アメフラシは、雌雄同体なのに交尾する。数個体が並んで交尾することもある。
4. 断崖 波が強く、崖崩れや落石など危険なところが多い。しかし、このような環境でも、それを好む動物が分布している。波の穏やかな時を選んで、危険のない場所で観察できれば、垂直分布(帯状分布)のわかりやすい場所でもある。
(1)植物 陸上には、いわゆる海浜植物が分布している。イソギク、ハマカンゾウ、ハマナデシコ、ラセイタソウなどの草とともにトベラやハマゴウなどの低木が見られ、岩の隙間に根を張って日本画の世界をかもし出すマツは、日本中の海岸のどこにでも見ることができる景色だ。
(2)動物 雨の直接かからない砂岩の剥がれかかった薄片を、そっと剥いで見よう。岩と同色の小さな虫が、両手の鋏を大きく広げて張り付いている。イソカニムシである。海岸に出かけると、どうしても海側に気を取られがちであるが、これを観察できたら立派である。
海に目を転じる。波の強い場所には、固着性の動物が分布する。岩に一度張り付いたら離れられないフジツボやイガイは、それぞれが好む高さで水平方向に帯状の分布をしている。船やウミガメ、クジラなどに付着して、その推進力を著しくそぐのはこの連中であり、付着を防ぐために開発された船底に塗る塗料が、いわゆる環境ホルモンになったのである。空気が良く溶け込むので、カニやカイの仲間も多く見られる。
V. 観察法とまとめ
1. 観察法
・採集、観察の場所全体の地形を観察し、頭に入れ、移動経路のイメージをもつ。
・動物はいきなり捕らえず、まず行動を観察する。一度ちじこまったらなかなか伸びてくれないものもある。
・数少ない動物は、その場で皆で観察する。
・採集するときは、傷つけず、殺さず、最少個体数に抑える。
・原則として引き潮を追いかけるように観察しながら進む。
・干潮時、最大どこまで露出したか、また帰路を確認しておく。
・上げ潮になったら、できるだけ早く引き上げ、海の中に取り残されないようにするとともに、露出している場所の全体像を観察する。
・安全な場所に集合し、海水を張った大型の白いバットに、採集物を一つずつ入れて、全員で観察し、メモをとる。その場でメモを取らないと、知識も海に返すことになる。
・標本にするもの以外の生物は、海に返す。
2. ちょっと遊んでみよう
(1)アラレタマキビ
コップに海水を汲んで、アラレタマキビ(タマキビでもよい)を10個体ほど入れて、その行動を観察しみよう。
(2)アメフラシ
もし、アメフラシをみつけたら、浅い潮溜まりの中に置いて、背中の襞の間を指で探って見よう。中はどうなっているか。何が起きるか。
(3)カニ
潮溜まりの中に、カニの死骸が沢山落ちていないか。カニにとってそんなに悪い環境なのだろうか。そっと拾って、丁寧に観察しなさい。特に眼や甲羅の後部と腹側の継ぎ目を上にちょっと引っ張ってみる。
(4)カサガイ
マツバガイ、ヨメガカサなどの大きめのカサガイを見つけたら、素手で獲る工夫をしてみよう。
(5)二枚貝の貝殻
打ち上げられている二枚貝の貝殻を見てみよう。きれいな丸い穴が開いているものがいくつもある。この穴はどうしてできたのだろう。
(6)褐藻類と緑藻類
日本の海は、海藻の種類も量も非常に豊富である。北に行くに連れて種類数は減少し、コンブなどの大型のものが多くなる。南に行くにつれて普通の海藻は見られなくなり、植物プランクトンや石灰藻類と呼ばれるものばかりになっていく傾向がある。観察できた褐藻類の数と緑藻類の数を調べ、次の式で計算して、その数値を表の数値と比べてみなさい。どのようなことがいえるか。
| (観察できた緑藻の種類数) ÷ (観察できた褐藻の種類数) = ? |
| 三陸 |
常陸 |
房総 |
南伊豆 |
紀伊 |
伊豆大島 |
神津島 |
八丈島 |
鹿児島 |
| 0.4 |
0.5 |
0.6 |
0.6 |
0.6 |
0.7 |
0.9 |
1.5 |
0.9 |
|
3. まとめ
(1)磯で観察した生物
次の図のように、磯を模式化した図を描いて、満潮線と干潮線とを目印にして、観察できた生物を記入しなさい。
| (拡大画面:28KB) |
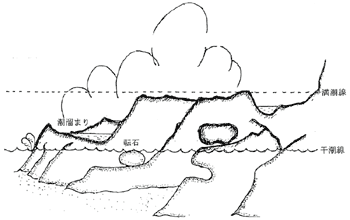 |
(2)動物分類
観察した動物を、次の分類段階「門」ごとに分けて表にして整理しなさい。
原生動物門、海綿動物門、腔腸動物門、扁形動物門、苔虫動物門、紐形動物門、星口動物門、環形動物門、軟体動物門、節足動物門、毛顎動物門、棘皮動物門、原索動物門、脊椎動物門
(3)植物分類
観察した植物を、次の分類段階「門」ごとに分けて表にして整理しなさい。
褐藻植物門、紅藻植物門、緑藻植物門、種子植物門
|