|
海の生きものをみに行こう
(講師 栃本忠良)
【講師紹介】
栃本忠良
昭和12年生
東京教育大学 理学部(動物学専攻)昭和37年卒業
東京教育大学 大学院(理学研究科)昭和42年修了 理学博士
東京都立高等学校(日野、府中、富士森、石神井)教員 平成10年退職
北里大学 水産学部教授 平成10年より現在に至る
(研究分野)
*軟体動物腹足類(前鰓目)の精子二型現象
*教育問題
*動物園と教育
海の生きものをみに行こう
I. はじめに
私達の地球には、数えきれないほど沢山の種類の生物が生息している。そして私達の周囲にも、緑の植物に囲まれた多くの虫達、多くの鳥達の世界がある。しかし、地球の2/3は海。青い空、澄んだ空気、そして美しい景色の海。 海! そこには、陸上とは比較にならないほど多くの種類の生物が生活を営んでいる。海は、生命の誕生した場所である。私達のずっとずっと昔の祖先達は、どこかで海から、あるいは川をさかのぼって陸上にはい上がり、陸上に生活圏を広げた。
海岸にはいろいろなタイプがあるが、それぞれの場所には、それぞれの環境に合った生物が集まって、ひしめき合うようにして棲息している。海には、あまり広い範囲を探さなくても、最も下等な原生動物から脊椎動物まで、全ての動物分類学上のグループ(門)のメンバーを見つけることができる。動物が多いということは、その餌となる植物が豊富だということである。それらの生物の多くが、干潮時には私達の手の届くほどの場所で生活している。
彼等の生活ぶりをちょっと覗かせてもらおう。初めての人には皆同じように見え、奇怪な姿をしていても、皆名前をもっている。名前を覚えるのが目的ではないが、気味悪がらずに名前を呼んであげよう。きっと親しみが湧いてくると思う。
II. 海ってどんな所
1. 海水濃度 地球上の水圏には淡水の湖沼や川と、塩水の海とがある。
川や多くの湖沼の水は淡水(真水)と言われているが、実際には、それぞれの場所ごとに水に触れている土壌や土砂から溶け出してくる特徴的な物質を含んでいる。サケが、広い海から生まれ故郷の川を探し当てて帰ってくるのは、この物質が目印だと言われている。一つひとつの川の水に、どんな味の違いがあるのだろうか。
海の水にも、川の水と同じように海底や海岸から溶け出した物質、そして川から流れてきた物質が含まれている。川と違って大量の水分の蒸発を繰り返してきたので、溶けていた物質の濃度がどんどん高くなった。特に多い塩分(塩化ナトリウム)のために、我々には、塩辛く感じられる。海水に溶けている元素の種類構成は、地球上の動物の体液(血液)に含まれている元素の種類構成に非常によく似ている。その濃度は、私達陸上の脊椎動物の体液(塩分濃度0.6〜0.9%)より少し高く、エビや貝のような海産無脊椎動物の体液濃度と同じである。海域によっても深さによっても多少違っていて(塩分濃度3.4〜3.6%程度)、一般的には、中緯度付近が最も濃く、また海面表層水が濃いようである。
海洋表面水の塩分の緯度による分布
(海洋の事典から)
大洋の中央部における水温と塩分量の鉛直分布
(海洋の事典より)
2. 海水の動き 海水の動きには幾つかの理由がある。
風によって吹き寄せられたり、川の水が流れ込んだり、太陽や月の引力で引っ張られたり、地球の自転による遠心力がかかったり、水温の違いにより低温水と高温水が重なったりなどにより、海の場所により水位の高低を生じる。そして海水は、川のように高い所から低い所に向かって移動する。それらの結果が、波、うねり、潮流や海流、潮の干満などとして現れる。
海水の動きは海岸にいろいろな影響を及ぼして、そこに様々な環境を造り出す。
(1)運搬 海は、いろいろな物をいろいろな所に運ぶ。海の荒れた翌日など、海岸には海藻や魚をはじめ、普段目にすることの稀な海底棲の動物、遠い地方からの漂流物が、ゴミなどに混じって打ち上げられている。その中には、オキナエビス、アオイガイ(蛸舟)、椰子の実などを見つけて感動したりすることもある。八丈島の海岸には、近くの他の島や伊豆半島にいない沖縄の方の海岸動物が何故いるのだろうか。生き物ばかりではなく、時には砂を運び、海岸に積み上げることもする。砂浜の砂はその例である。また、土砂を持ち去り、岩だけを残して磯をつくることもある。
(2)撹拌 海水の成分は、厳密にいえば場所によって異なる。しかし、多くの海産動植物は他の海に行っても生きてゆける。これは、海水の動きにより、海全体がかき回され、概ね同じ成分の海水になっているからである。また、撹拌によって海水中に溶け込んだ空気は、動植物の生存には欠かせないものである。
(3)侵食 海水の動きは、風雨とともに海岸を浸食する。繰り返えし打ち寄せる波や洗うように流れる潮流は、海岸を削り、海底を深く削り、土砂を運び去り、陸地を分断して島を造り、湾を造り、岬を造る。
III. 海岸
上で述べたように、海水の動きにより、次に述べるようないろいろな海岸地形ができた。海岸には浜、干潟、磯、断崖絶壁などがある。
| (拡大画面:43KB) |
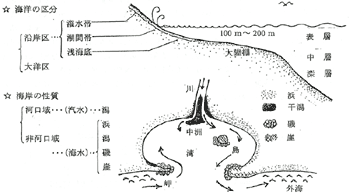 |
1. 海岸のタイプ
(1)浜 川が山から岩を削って生じた砂が、海まで運ばれる。その砂が波によって打ち上げられ堆積した海岸や、岩がほとんど無い海岸である。細かな砂粒の砂浜、小砂利の砂利浜、石ころが主体の石ころ浜(ゴロ浜)などがある。また、貝殻や珊瑚が砕けた砂浜、原生動物の星砂の殼が堆積した砂浜などもある。砂粒の性質により、真っ白な海岸、黄色みを帯びた海岸、真っ黒な海岸、踏むと音のする泣き砂の海岸などの特徴も見られる。湾の内部の河口周辺部に発達することが多く、一般的には遠浅になっている所が多い。しかし、外海に面した砂浜には強い波が打ち寄せ、急に深みを生じていたり、流れの速い潮流がすぐそばまできていることも多いので油断できない。
(2)干潟 湾の中の河口に泥と砂が混じって堆積して遠浅となり、波に洗われることが無く、引き潮時には広く陸地化する場所で、満ち潮時には海面下に没する。規模の大小はともかくとして、殆んどの河口付近に見られる。河口の中洲や河口の両岸に発達するため、時間によって汽水、海水、真水に洗われる。泥の多い所では、底なし沼のように足を取られる。砂泥には有機物が含まれ、川を流れ下ってきたゴミなども多く見かけられ怪我に注意を要する。規模の大きい干潟などには汐入の潟湖が見られることもある。
(3)磯 海岸から突き出た所や、島の周囲に展開する岩礁帯である。波が打ち寄せ、岩礁の上、隙間、岩の下など地形的にも非常に変化に富み、着生の海藻が生い茂り、多種多様な動物が豊富に棲息している。潮が引いた後の窪みには、潮溜まり(タイドプール)という水溜りができて、いろいろな動物達が取り残され、隠れている。したがって、干潮時は、海岸生物の観察には非常に適した場所だと言える。しかし、岩の上は海藻などで滑りやすく、転倒のおそれがあり、潮が満ちてくる時には、急激な大波に襲われたり、海の中に取り残されたりするので危険な場所でもあり、注意を必要とする。
(4)断崖 一般的には波が荒く、風化した崖の崩壊や落石の危険があり、生物の観察には不向きな場所である。
| (拡大画面:36KB) |
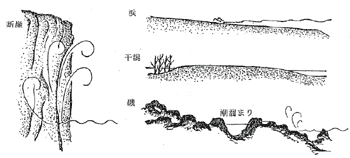 |
2. 潮の干満
潮汐による海面の昇降は、1日2回が普通である。月と太陽の引力と地球の自転による遠心力により、海水が引っ張られるために、海面が昇降する。太陽・月・地球が一直線上に並んだ時(満月と新月の時)、潮の干満の差(潮差)が最大となり(大潮)、太陽・地球・月が直角に並んだ時、潮の干満の差は最初(小潮)となる。ただし、実際には大潮は満月や新月より1〜2日遅れる。特に潮差が大きくなるのは、3〜5月(昼間)と12〜1月(夜間)である。例えば、潮差は太平洋岸で1.2〜2.0m、日本海岸で0.1〜0.3m、九州西海岸で2〜5m、瀬戸内海中央部3〜3.8mにもなる。毎日の干満の時刻は、次のようにまとめたものが、その年の理科年表に掲載されている。また、釣道具店でも調べられる。
(1)潮汐表例
東京芝浦 潮汐 xxxx年 中央標準時
| 日 |
5月 |
6月 |
7月 |
| 次 |
満潮 |
干潮 |
満潮 |
干潮 |
満潮 |
干潮 |
| |
h m |
h m |
h m |
h m |
h m |
h m |
h m |
h m |
h m |
h m |
h m |
h m |
| 1 |
6 25 |
20 46 |
1 13 |
13 37 |
7 19 |
22 8 |
2 27 |
14 46 |
8 3 |
21 47 |
2 51 |
14 53 |
| 2 |
6 52 |
21 48 |
1 49 |
14 19 |
8 10 |
23 3 |
3 26 |
15 37 |
9 3 |
22 25 |
3 47 |
15 33 |
| 3 |
7 24 |
23 9 |
2 33 |
15 11 |
9 26 |
− − |
4 52 |
16 43 |
10 20 |
23 8 |
5 2 |
16 26 |
| 4 |
8 7 |
− − |
3 47 |
16 27 |
0 1 |
11 16 |
6 27 |
18 1 |
11 54 |
23 55 |
6 22 |
17 44 |
| 5 |
0 47 |
9 32 |
6 3 |
18 2 |
0 54 |
13 7 |
7 32 |
19 12 |
− − |
13 38 |
7 23 |
19 6 |
| 6 |
1 53 |
12 25 |
7 38 |
19 20 |
1 38 |
14 24 |
8 18 |
20 9 |
0 47 |
14 59 |
8 11 |
20 12 |
| 7 |
2 31 |
14 5 |
8 26 |
20 17 |
2 15 |
15 18 |
8 55 |
20 57 |
1 40 |
15 53 |
8 53 |
21 6 |
| 8 |
3 0 |
14 59 |
9 2 |
21 2 |
2 47 |
16 2 |
9 29 |
21 39 |
2 29 |
16 36 |
9 34 |
21 54 |
| 9 |
3 24 |
15 40 |
9 34 |
21 40 |
3 17 |
16 42 |
10 3 |
22 17 |
3 15 |
17 15 |
10 15 |
22 37 |
| 10 |
3 46 |
16 17 |
10 4 |
22 15 |
3 48 |
17 20 |
10 37 |
22 54 |
3 58 |
17 54 |
10 57 |
23 20 |
| 11 |
4 8 |
16 52 |
10 34 |
22 47 |
4 19 |
17 59 |
11 12 |
23 31 |
4 40 |
18 33 |
11 40 |
− − |
| 12 |
4 30 |
17 27 |
11 3 |
23 18 |
4 51 |
18 40 |
11 50 |
− − |
5 22 |
19 11 |
0 1 |
12 23 |
| 13 |
4 53 |
18 3 |
11 33 |
23 49 |
5 25 |
19 22 |
0 8 |
12 30 |
6 5 |
19 50 |
0 42 |
13 6 |
| 14 |
5 17 |
18 41 |
− − |
12 5 |
6 2 |
20 8 |
0 47 |
13 12 |
6 52 |
20 27 |
1 23 |
13 48 |
| 15 |
5 42 |
19 23 |
0 19 |
12 39 |
6 43 |
20 56 |
1 29 |
13 57 |
7 44 |
21 4 |
2 7 |
14 30 |
| 16 |
6 10 |
20 9 |
0 51 |
13 16 |
7 32 |
21 45 |
2 17 |
14 47 |
8 46 |
21 40 |
2 57 |
15 14 |
| 17 |
6 40 |
21 5 |
1 27 |
13 59 |
8 40 |
22 36 |
3 18 |
15 43 |
10 2 |
22 18 |
3 57 |
16 3 |
| 18 |
7 16 |
22 12 |
2 10 |
14 53 |
10 12 |
23 26 |
4 38 |
16 48 |
11 35 |
23 0 |
5 14 |
17 6 |
| 19 |
8 10 |
23 29 |
3 17 |
16 4 |
11 57 |
− − |
6 8 |
18 0 |
13 31 |
23 51 |
6 36 |
18 27 |
| 20 |
10 1 |
− − |
5 20 |
17 29 |
0 15 |
13 36 |
7 18 |
19 10 |
− − |
15 10 |
7 44 |
19 46 |
| 21 |
0 41 |
12 19 |
7 6 |
18 48 |
1 4 |
14 55 |
8 12 |
20 13 |
0 56 |
16 10 |
8 40 |
20 53 |
| 22 |
1 35 |
13 54 |
8 2 |
19 53 |
1 52 |
15 58 |
8 59 |
21 9 |
2 7 |
16 54 |
9 31 |
21 49 |
| 23 |
2 16 |
15 0 |
8 45 |
20 48 |
2 39 |
16 50 |
9 44 |
22 0 |
3 8 |
17 30 |
10 17 |
22 37 |
| 24 |
2 52 |
15 55 |
9 25 |
21 37 |
3 22 |
17 35 |
10 27 |
22 46 |
3 57 |
18 2 |
11 0 |
23 18 |
| 25 |
3 25 |
16 46 |
10 5 |
22 21 |
4 4 |
18 16 |
11 10 |
23 30 |
4 38 |
18 32 |
11 39 |
23 56 |
| 26 |
3 57 |
17 33 |
10 44 |
23 4 |
4 43 |
18 55 |
11 51 |
− − |
5 16 |
19 0 |
− − |
12 15 |
| 27 |
4 29 |
18 20 |
11 24 |
23 44 |
5 20 |
19 30 |
0 10 |
12 30 |
5 52 |
19 26 |
0 31 |
12 47 |
| 28 |
5 0 |
19 4 |
− − |
12 3 |
5 57 |
20 4 |
0 49 |
13 7 |
6 28 |
19 51 |
1 4 |
13 18 |
| 29 |
5 32 |
19 49 |
0 23 |
12 42 |
6 35 |
20 37 |
1 27 |
13 42 |
7 6 |
20 16 |
1 38 |
13 46 |
| 30 |
6 5 |
20 33 |
1 1 |
13 22 |
7 16 |
21 11 |
2 6 |
14 17 |
7 48 |
20 43 |
2 14 |
14 13 |
| 31 |
6 39 |
21 19 |
1 42 |
14 2 |
|
|
|
|
8 37 |
21 12 |
2 55 |
14 41 |
|
(2)地形と潮の干満
潮の干満と海岸との関係を考えると、海岸は次の図のようにまとめることができる。
灌水帯は、波のしぶきや荒れた大波をかぶるところである。したがって、干潮時と満潮時、大潮と小潮などでしぶきをかぶる場所は異なるが、普通は、大潮や小潮に限らず満潮時にも海水中に没することはほとんどない。
干潮時の海水面から満潮時の海水面までの間を潮間帯とよび、生物観察(いわゆる磯採集)の最も適した場所となる。観察は、引いてゆく潮を追いながら行なうのがよい。引き潮はゆっくりに感じるが、上げ潮(満ち潮)は意外に早い。観察に夢中になっていると、波に取り囲まれて進退に窮することがある。また、引き潮時は波が小さくなるが、上げ潮時は波が大きく荒くなることも知っておこう。
|