|
4. 中海北東部における干拓堤防と魚類の分布の影響
中海北東部はかつては、境水道を通って外海水が直接流入していたが、現在は森山堤防によって水の流れは中浦水門を経由して中海に入り、本庄工区には大海崎堤防の開削部を迂回して水が入ってくる。
したがって、堤防が構築される前までは境水道と現在の本庄工区は一続きの水域であったが、現在は中海の中でもっとも外海と離れた位置関係にある。
このような分断された水域において、棲息魚類の種構成がどのようであるかを調べた。この場合、移動が少なく採集しやすいことを考慮すると、水際近くの浅場に生息する底棲性の魚類の比較がよいと判断した。
1999年と2000年の両年に本庄工区と北部小水路および中浦水門付近の3箇所の底棲棲の魚類の生息状況を比較した。
(1)3地点の生息状況
図−9は、調査期間を通じて採集された魚種と採集頻度を示している。
図−9 中海北東部3水域における生息魚種の比較
|
(拡大画面:135KB)
|
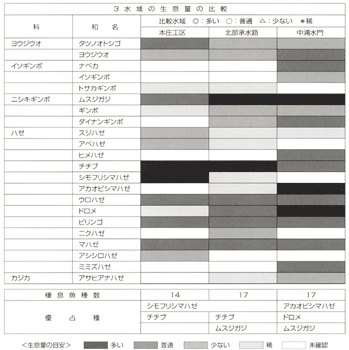 |
採集された魚種は22種であり、そのうちハゼ科が13種と6割弱を占めている。他は、ヨウジウオ科2種、ギンポ類6種、カジカ科1種であり共に、移動の少ない底棲棲の魚類である。そのうち、本庄工区は14種、北部承水路は17種、中浦水門付近は17種であった。3地点で共に採集された種は、タツノオトシゴ、ヨウジウオ、ムスジガジ、ギンポ、スジハゼ、チチブ、ウロハゼ、ドロメ、ビリンゴ、マハゼの10種で約半数であった。これらの種は多様な環境に適応している種といえる。中でも、ウロハゼ、ビリンゴ、マハゼは特にその傾向が強い。逆にドロメは、本庄工区・北部承水路・中浦水門付近の順に棲息密度が濃くなっていく。スジハゼは、本庄工区の方が多くなっている。
次に、偏った分布を示すものに、ナベカ、イソギンポ、ダイナンギンポなどのギンポ類、ヒメハゼ、アカオビシマハゼ、ミミズハゼ、アサヒアナハゼが見られた。それらは本庄工区内では採集されず、北部承水路と中浦水門付近では採集されており、いずれも後者の方が多かった。そのことは、これらの種が境水道から美保湾の浅場にかけても多く見られることから、中浦水門付近が海洋性的な性質の強い環境であることと、本庄工区が内湾性的な環境であることが伺える。
上と逆に分布の偏りを持つ種に、アベハゼとシモフリシマハゼがいる。
次に、上の中から、極近縁な2種のシマハゼ類類を取り上げてみる。
(2)シマハゼ類の分布
本水域には、図−9に示すように極近縁な2種のシマハゼが生息し、分布域に重なりがない。それらは、シモフリシマハゼとアカオビシマハゼであり、前者が宍道湖全域から中海の北東部を除くほぼ全域で、後者は中浦水道近辺から境水道、美浦湾にかけて分布している。つまり、前者が内湾的な水域であるのに対して後者は海洋的な色合いの強い水域とに生息域を分けている。
図−10 中海北東部3水域におけるシマハゼ2種の生息分布
|
(拡大画面:37KB)
|
 |
図−10は2種のシマハゼ類の月ごとの採集状況を示している。これより、本庄工区と中浦水門付近は対象的であることが分かる、前者は周年を通じてシモフリシマハゼのみが採集され、後者はアカオビシマハゼである。両者は、季節的に移動したりして交じり合うことはない。つまり、両者は、分布範囲を明確に分けているといえる。
北部承水路は、両種ともに少数しか採集されていないが、10月には両種が共に採集された。以上のことから、本庄工区が内湾的で、中浦水門付近が海洋的な特徴を持つ水域であるといえる。また、北部承水路は中間的な特徴を持っている。
かつては、一続きであった上の3地点は堤防などの人工構築物によって現在は大きく異なった環境となっていることが、2種のシマハゼの分布状態から伺うことができる。
|