|
3. 本水域における産卵と稚幼魚の出現
(1)魚類の産卵
2002年3月から同年9月までに、漁獲された魚類の中で生殖腺の熟した個体が高い割合で現れるものを調べた。それらは、生殖腺が成熟から完熟にいたるものを含むが、中に卵または精子がこぼれ出る個体を含むことを条件とした。つまり、このような個体群は本水域において産卵する種と判断したことによる。
図−4 宍道湖・中海水域における熟卵巣及び熟精巣保有魚の出現
図−4は上の条件に合う期間を種ごとに表している。時期的に早いものから3月中旬からサヨリの生殖巣が熟してきて5月下旬まで続く。次いで、4月上旬より、ウミタナゴ・コノシロと続くが、海産魚の前者が中海北部を中心に分布し、2週間程度と短期間であるのに対して、後者は水域全体で高密度に生息し期間も2ヶ月とやや長い。上記の3種から遅れて4月下旬から5月にかけて、サッパ、シモフリシマハゼ、カタクチイワシ、ダツなどの汽水性の魚類とコイ・ワタカなどの淡水魚の生殖腺が熟してくる。共に1〜2ヶ月間続く。5月中旬から下旬にかけて、アシシロハゼ、ヨウジウオ、タツノオトシゴ、クサフグ、ウロハゼと続き、6月になると、トウゴロウイワシとヒイラギと続く。
以上のように、4月から6月にかけて、多くの魚類の生殖腺が熟してきて、完熟卵を有することからこれらの魚は本水域において産卵する種として挙げられる。
図−5 コノシロの卵巣重量の変化(単位:g)
図−6 サッパ生殖腺重量の変化(単位:g)
(2)稚幼魚の出現
稚幼魚の出現は、図−7に示す。
図−7 宍道湖・中海における稚幼魚の出現状況
|
(拡大画面:85KB)
|
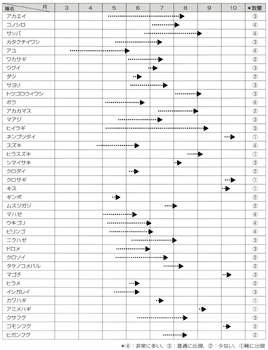 |
時期的に早いものから挙げると、3月の中旬からアユが出現する、このころは、まだ体色がほとんど現れないシラスアユである。4月に入って全長が6cmを超えるほどに成長する個体から次第に腹部から体色が出てくる。最近、本水域においてこの時期の稚幼アユは増加している。次いで、4月下旬よりスズキの当歳魚が大群で美保湾から中海に入り、そのまま宍道湖に遡上する群れもある。5月に入ると、種類が増えてくる。主なものは、ボラ、ヒイラギ、マハゼで、少し後になって、ウキゴリ、ビリンゴ、カタクチイワシ、アカエイ、マアジ、ドロメ、クロソイ、イシガレイなどが続く。6月になると、ワカサギ、サヨリ、ダツ、クロダイ、ヒラメなどの稚幼魚が見られるようになる。7月以降は、シマイサキ、カワハギ、ヒガンフグ、ネンブツダイ、クロサギなどの海産魚の幼魚が中海に入ってくることが多くなる。
|
図−8
|
宍道湖・中海において熟生殖腺と稚幼魚が共に確認された種と期間
|
|
(拡大画面:49KB)
|
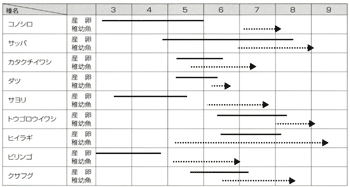 |
|