|
第4節 歌の旋律と三味線の手
《嵯峨の春》の歌の旋律に付けられた三味線の「手」には、大きく分けて、次の4種のような「使い方」がみられた。
歌の旋律に付けられた三味線の手
ア. 歌の旋律につかず離れずに奏される手 |
譜14 |
イ. 歌の旋律が平板な部分に対して動きを持たせる手 |
譜15 |
ウ. 「段落コトバ」につく装飾的な手 |
譜16 |
エ. 平板旋律や歌の定型旋律を装飾する三味線の定型旋律の手 |
譜17〜23 |
(拡大画面:42KB) |
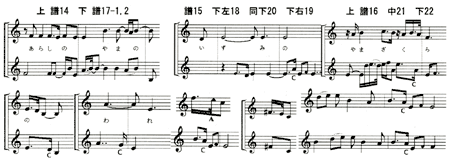 |
《嵯峨の春》は、これらの三味線の手によってみてみると、ア「歌の旋律につかず離れずに奏される手」を中心に、旋律が平板な部分に対しては、イ「動きを持たせる手」を使い、「段落コトバ」では、ウ「装飾的な手」も用いられていたが、歌の旋律を豊かに表現するための、エ「定型旋律の手」も使われていた。この定型旋律は、特定の音形やリズムで、一部には、「ウチ」「スクイ」などの三味線の奏法が含まれて、作られている。その使われ方は、種々の歌の旋律に独立している場合と、歌の定型旋律に対応している場合がある。
ここでは、歌の定型旋律に対応する三味線の定型旋律について詳しく述べる。次に、三味線の定型旋律の種類を、M1,N1〜2,O1〜2、P1〜2で示した。
三味線の定型旋律の種類の分類
M1:譜17−1、 |
2のような定型旋律 |
O1:譜20のような定型旋律 |
N1:譜18−1、 |
2のような定型旋律 |
O2: O1のヴァリアンテ
|
N2:譜19 |
N1のヴァリアンテ |
P1:譜21のような定型旋律 |
|
|
P2:譜22 P1のヴァリアンテ |
以上の分類によって、歌の定型旋律と三味線の定型旋律の関係をみてみると、それぞれのリズムや音形には変化があり、また、対応の仕方には前後への多少のずれもあるが、歌の定型旋律と三味線の定型旋律の対応には、習慣的な対応の仕方がみられた。表3は、その対応を一覧にまとめたものである。
表3 歌と三味線との定型旋律対応一覧
| |
歌の定型旋律 |
三味線の定型旋律 |
| 定型 |
音列 |
定型 |
音列 |
| (1) |
E1 |
(e-d-b)(a-g-e) |
M1 |
(e-d-b)(a-g-e) |
| (2) |
E2 |
(e-h)(a-e) |
M1 |
(e-d-b)(a-g-e) |
| (3) |
F1 |
(f#-e-c)(e-d-b♭) |
N1 |
(f#-e-c)(e-d-b♭) |
| (4) |
F1 |
(f#-e-c) |
N2 |
(f#-c) |
| (5) |
G1 |
(b-a-f-e) |
O1 |
(b-a-e-f-e) |
| (6) |
G2 |
(b-a-f) |
O2 |
(b-a-e-f) |
| (7) |
H1 |
(b-e-a-b-f-e) |
P1 |
(d-e-b-a-b-a-f-e) |
| (8) |
H2 |
(b-e-a-b-f) |
P2 |
(d-e-b-a-b-a-e-f-f) |
|
譜23
譜24
表3にみるように、段落コトバや段落感のある箇所で使われる、歌の定型旋律E1やE2には、三味線は、M1のような段落感のある進行をする定型旋律が対応している。F1「f#-e-c」や「e-d-b♭」のような増4度の進行には、やはり増4度進行のN1やN2が対応する。このc音やb♭音で終わる旋律形の対応は不安定で、後に続く旋律のある部分で使用される。
以上の対応は、歌と三味線の、ほとんど同型の旋律が対応している例であるが、GにO(譜23)、HにP(譜24)の対応は、使用される音は同じであるが、音列が異なる対応である。なお、先に見た、後に続く旋律のあるFにNの対応は、G2にO2、H2にP2のような、f音で終わるものの対応にも見られる。
このようにみてくると、三味線の定型旋律は、歌の種々の旋律に独立して用いられる場合もあるが、歌の定型旋律に対応して用いられる場合が比較的多く、数種ある歌の定型旋律に、固有の三味線の定型旋律が対応している。その上、GにO、HにPのような音列の異なる定型旋律の対応(ここでは「定型対応」と呼ぶ)が慣用になっていることも明らかである。
この「定型対応」については、《嵯峨の春》では登場回数が少なく、はっきりしたことがいえないが、定型旋律の対応や「定型対応」には、二つの対応のさせ方が考えられるであろう。すなわち、一つは、歌の旋律に定型旋律が歌われるところでは、それに、合わせる三味線の定型旋律が奏されるという考え方であり、もう一つは、三味線の定型旋律が先行して、歌の定型旋律がそれに乗って歌われるという考え方である。
《嵯峨の春》の三味線の手は、定型旋律を用いたり、平板な旋律に動きを持たせたりして、作品らしさを表現しながらも、歌の旋律につかず離れずの手を中心に用い、歌の旋律を邪魔せずに、引き立てる手付がされているといえるであろう。
(梁島章子)
註
1. 『新日本古典文学大系56』岩波書店 1997pp.195−196
2. 『庶民文化資料集成5』三一書房 1973p.479
3. 前掲書 pp.195−196
4. 東京都小河内鹿島踊の《こきりこ》、小林公江 採集採譜 1975年
5. 観世左近『観世流謡曲百番集』檜書店、1966 p.1138
6. 茂山家狂言《花折》NHK放映 1994年1月2日
7. 前掲、歌い出しの実音「一点ト音」。
8. 前掲、歌い出しの実音「へ音」。
9. 久保田敏子「嵯峨の春」『日本音楽大事典』平凡杜、1989 p.872
|