|
3. 環境修復策の効果予測
3.1 修復策検討ケース
貧酸素水の形成に関わる環境修復策として、以下に示した3ケースの対策条件を検討した。
・ケース1:環境イニシアティブ検討案複合
・ケース2:浅場造成
・ケース3:ケース1+ケース2
1)ケース1
まず、環境イニシアティブで実施された対策ありの検討ケースを複合したものをケース1とした。計算条件としては、以下のように設定した(図3.1)。
(1)中浦水門の位置に潜堤設置
中浦水門の位置に−3mの潜堤を設置したと仮定し、水深をかさ上げした。
(2)本庄工区堤防の開削
大海崎堤と森山堤の一部を開削したと仮定し、計算メッシュを変更した。大海崎堤については、澪筋部分を200m開削した。森山堤については、澪筋部分を200m開削し、本庄工区側の水深と勾配を付ける形で、10mまで堀削した。
(3)米子湾浚渫後窪地の埋め戻し
中海の浚渫窪地などの深く掘られた地形を埋め戻したと仮定し、中浦水門から米子湾に至る水深を6〜8m程度の水深にならした。さらに、水深を変更したメッシュは覆砂を行った場所と判断し、底泥からの栄養塩溶出および酸素消費を0とした。
2)ケース2
次に、中海南西部に浅場造成を施した検討をケース2とした。計算条件としては、図3.2に示した海域について、比較的浅場で貝類資源が豊富な海域と同様な水深および貝類資源量の条件に設定した。それにより、浅場造成に伴う貝類の効果を見込んだ。
3)ケース3
最後に、ケース1とケース2を複合した検討をケース3とした。
以上の条件以外は、現況解析と同じ条件設定で流動および水質シミュレーションを実施し、環境変化を予測した。
図3.1 修復策ケース1の検討策
(拡大画面:47KB) |
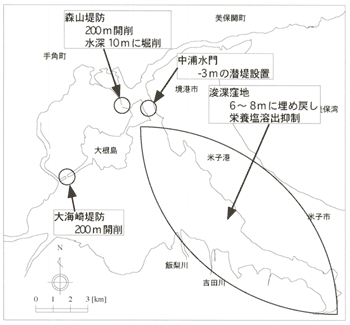 |
図3.2 修復策ケース2の検討策
(拡大画面:30KB) |
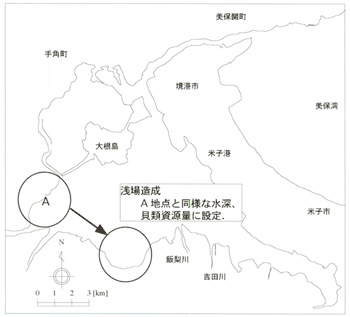
|
3.2 環境修復後の計算結果
1)流動の変化
ここでは中海の流動、特に底層の流れに着目して、環境修復後の流動変化について検討した。各検討ケースにおける底層(計算の海底直上層)の流速ベクトルを、観測日の中から各季節を代表して5月7日、8月5日、11月4日および2月1日を選び、 図3.3に示した。 現況では、各日とも概ね美保湾から境水道〜中浦水門を通り中海に流入し、大橋川と米子湾方面に分離する流れを示している。しかし、ケース1で本庄工区の2つの堤防を開削し、中浦水門に潜堤を設けたことによって、境水道〜森山堤を通り本庄工区に流入し、大海崎堤から中海に流入する進路に変更している。大海崎堤から進入した水は、大橋川に向かう流れと中海に拡がる流れに分離するが、米子湾方面にはそれほど拡がっていない様子が伺える。これらのことと、中浦水門を通る流量が減るため、現況で海水の影響を強く受けている中浦水門から中海中央部および米子湾付近にかけての水域では、高塩分水の影響が少なくなると考えられる。
ケース2の流れをみると、浅場を造成した水域で流れが若干変化しているのが認められたが、その他の水域では大きな変化はなかった。またケース3では、ケース1と2が複合した流れ場を形成している様子が伺える。
2)塩分の変化
ここでは、中海の底層塩分に着目して、環境修復後の塩分変化について検討した。まず、中海のSt.3、St.4、St.12、St.13および本庄工区のSt.25(観測地点の位置は 図2.7参照)における、各ケースの底層での塩分変動を 図3.4に示した。また、各検討ケースにおける底層の塩分変化(検討ケース―現況)を、各月の観測日の中から各季節を代表して5月7日、8月5日、11月4日および2月1日を選び、 図3.5に示した。 これによると、現況とケース2およびケース1とケース3は大きな差はなく、浅場造成による効果は当該海域周辺に限定していることがわかった。ケース1の効果によると、本庄工区では森山堤から高塩分水が流入してくるため上昇し、中海では中浦水門に設けた潜堤の影響で高塩分水が流入し難くなったため低下する傾向がみられた。変化の規模は、中浦水門に近いSt.13が最も大きく、大橋川に近づくにつれ小さくなる傾向にあった。本庄工区においては、現況では年間を通して余り動きの少ない塩分変動であったが、森山堤を開削することによって美保湾の潮位変動の影響を強く受け、日々の塩分変動が激しくなることもわかった。
ケース1における底層の塩分変化域は、季節によって規模は変わるが、分布の傾向は概ね本庄工区で5〜15psu程度上昇し、中浦水門南部で10psu程度、中海全域で5psu程度低下する傾向にあった。ケース2における底層の塩分変化域は、浅場造成した周辺海域で最大10psu程度の減少がみられたが、その範囲は限られていた。
3)DOの変化
ここでは、中海の底層DOに着目して、環境修復後のDO変化について検討した。まず、中海のSt.3、St.4、St.12、St.13および本庄工区のSt.25(観測地点の位置は 図2.7参照)における、各ケースの底層でのDO変動を 図3.6に示した。また、各検討ケースにおける底層のDO変化(検討ケース―現況)を、各月の観測日の中から各季節を代表して5月7日、8月5日、11月4日および2月1日を選び、 図3.7に示した。 これによると塩分同様、現況とケース2およびケース1とケース3は大きな差はなく、浅場造成による効果は当該海域周辺に限定していることがわかった。浅場造成を仮定した海域に近いSt.3では、現況とケース2の違いが明らかで、浅場造成による効果が現れていた。ケース1の効果によると、本庄工区と中海のほぼ全域でDOが増加し、中浦水門南部では減少する傾向がみられた。本庄工区においては、8月頃までは増加の傾向にあったが、9月以降は減少していた。これは、現況では本庄工区が閉鎖系の海域であったのに対し、堤防を開削したことにより中海の貧酸素水が9月以降には流入してきたためであると考えられた。
ケース1における底層のDO変化域は、季節によって規模は変わるが、分布の傾向は概ね本庄工区で8月までは1〜3mg/L程度増加し、9月以降は1〜2mg/L程度減少、中浦水門南部で1〜2mg/L程度減少、中海全域で1〜3mg/L程度増加する傾向にあった。酸素消費を抑制した米子湾では、冬季で1〜3mg/L程度の増加が確認されたが、夏季では顕著なDOの増加はみられなかった。ケース2における底層のDO変化域は、浅場造成した周辺海域で最大3mg/L程度の増加がみられたが、その範囲は限られていた。
最後に、シミュレーション結果から中海における貧酸素水塊(2.8mg/L以下の分布)の出現状況を可視化し、現況とケース3についてVTR(CD−ROM)に収録した。
|