|
源流から柳瀬川合流点までの流量調査結果
調査日時:14年3月2日(土) 10:00〜16:00
水温11℃ 気温19℃ 天気薄曇り
・源流部釣り池から流出2.7リットル/秒
・上流端看板下 4.6リットル/秒 セリが生えていた
・中村橋(市役所前) 6.27リットル コンクリートの横木の下で測定
・空堀橋(武蔵村山調整池)新河道が出来上がっている。脇に流れなし
・中砂橋 測定不能 僅かに流水あり
・神明橋 測定不能 流水なし
・上砂橋(東大和警察脇) 測定不能 流水なし
・中砂の川橋(芝中団地) 測定不能 流水なし
・山王橋 測定不能 流水なし
・砂の川橋(八幡通り奈良橋6丁目バス停) 橋下流入水あり 63.73リットル/秒
・庚申橋下 工場排水の流入 54.1リットル/秒
・高木橋 奈良橋川と合流 奈良橋川の流量は計測不能、5リットル前後と推定
・清水大橋 工事中
・西武多摩湖線架橋下 工事の濁りあり
・浄水場前 流れあり 測定せず
・第二天王橋 僅かに流れあり、測定せず
・石橋 測定不能 チョロチョロの流水
・野行前橋 1〜2リットル/秒 殆ど測定不能
・秋津南橋 測定不能
・大沼田橋 測定不能 流水なし
・野塩橋上流 落差工 流水なし 測定不能 釣り人あり
・三郷橋下 工事中・魚道の設置 工事中のため 測定できず。 流水あり
・柳瀬川合流点直前 (伏流水か湧水がある) 10.2リットル/秒
空堀川の流路図
| (拡大画面:43KB) |
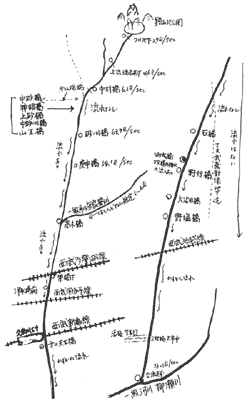 |
調査のまとめ(3月2日の調査結果をもとに)
空堀川の流量は、東大和市の八幡通り 砂の川橋直下右岸から流入する工場排水と、同地 庚申橋下右岸から流入する工場排水の二つの排水によって維持されております。この他の流入水は東大和地内 高木で合流する奈良橋川がありますが、冬季は流入する水量は少なく、殆ど空堀川の維持流量に貢献することなく、空堀川の流量は上記の二地点からの工場排水で維持されているといえます。
この日(3月2日)は土曜日であり、A工場の排水量は少ない日であることが予想(平日の60%程度)されます。この流量では東村山市内で西武新宿線架線より下流は地下に浸透してしまい流量を測定することは不可能でした。
柳瀬川との合流点前では流水が復活し、細い流れではありますが、10リットル/秒程度の流れがありました。この流れは野塩橋下(清瀬市)の伏流水と湧水であると思われます。
それにしても、雨が降らない限り川に水が無いということは深刻な事態です。
○流れの現状
3月2日、初めて空堀川の全川にわたって流量の調査を行ってみて、改めて強い危機感を覚えました。このままでは改修工事が終わっても水の無い川になってしまうことが明らかだからです。原因のすべては人が関わっているものです。
当会では一昨年空堀川に流入する水の調査を行って、数年のうちに深刻な水不足になるだろうと訴えてきました。
今回の調査では、水不足の事態が予想を超えて早まっていることが分かりました。
源流から上流端までは一般河川ということで、管理は武蔵村山市にあり、殆どが三面コンクリート張りで流路には蓋をされ、水路は歩道として生活道路に使われています。覗いて見るとわずかな流れがありますが、これはコンクリートの裂け目からの湧水でした。
上流端の看板下からは厚いコンクリート護岸が整備され、湧水の湧き出しも完全に閉ざされ数年前あった自然は喪失しています。このあたりの水量は僅かですが年間を通して一定しているように見られました。昔は念仏塚橋で合流する久保ノ川があったようですが、現在は暗渠になっていて空堀川に流入する水はありません。
武蔵村山市内ではわずかですが、まだ生活雑排水の流入もあります。けれど流れを形成するまでにはいたっていません。流路に溜まった水は悪臭を放っています。武蔵村山市内では新河道も併設されており、共用した場合は、流量の全部が新河道に浸透してしまい水無しの河道になることは明らかです。
東大和市内でも生活雑排水の下水道への接続が進んでいますが、生活雑排水以外の水がないため悪臭が鼻をつきます。河道は八幡通りの砂の川橋まで殆ど水がなく、ようやくこの橋下からの工場排水によって流れが復活しています。この流れはここから少し下流の庚申橋下の工場排水と合わさって高木橋上で唯一の枝川である奈良橋川と合流し、東村山市内に流れてきます。奈良橋川はこの時期は殆ど流量がなく前記2か所の排水によってかろうじて中流部の流れを維持していることが分かりました。
東大和市と東村山市との市境にある調節池が供用された場合、相当量の水が地表から失われることはハッキリしています。
東村山市内の西部新宿線久米川駅から下流では地下に浸透し、流れは消滅しています。東村山と清瀬の市境の大沼田橋・所沢街道の野塩橋の落差工には流れ落ちる水は一滴もありません。完全に涸れ川になっています。
清瀬市内三郷橋下からは伏流した水と湧き水によって細い流れが柳瀬川の合流点にそそいでいる現状です。
流量の測定も河道に水が無く、梅雨時を除いて測定することが困難な状況でした。
しかし、水無川であっても流量の測定する意味は大きなものがありました。どこで水が浸透しているのか、全川を測定したことによって各所のおよその流量が分かったことです。
まだ改修していない河道
改修して広くなった河道
雨水の地下浸透と地表面の被覆状況
| 不浸透率 |
: |
山間部を除く地表面積に対するコンクリート等により地表面を被覆された面積の割合 |
| 雨水浸透率 |
: |
降水量に対する雨水の地下浸透の割合 資料 東京都環境局 |
合流点における流量の経年変化
| (拡大画面:18KB) |
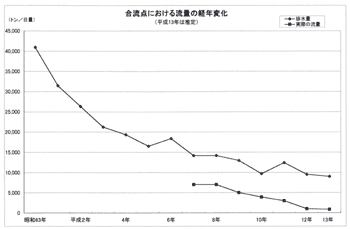 |
|