|
随想
YME2002使節員報告*
−ヨーロッパを訪問して−
清水悦郎**
1. はじめに
本年度、日本マリンエンジニアリング学会の学会活性化事業の一つである、平成14年度YME事業(研究動向調査)の使節員に選んで頂き、海外の研究所等を訪問する機会が得られました。私が選ばれました研究動向調査の使節員は、海外の研究所等を訪問し最新の技術動向を調査してくることとともに、IMarEST本部を訪問し交流をもつことが目的です。本報告では、訪問先の選定から実際に訪問してきての感想について述べさせて頂きます。
2.訪問先の選定
IMarEST本部への訪問は今回派遣されるYMEメンバーが別々に訪問することは先方にも迷惑となるため、YMEメンバー間で連絡を取り、IMarEST本部への訪問日程を先に決定しました。
派遣先選定に関しましては、私自身が制御理論の応用という観点から船舶やロボットなどの制御に関する研究を行っていることもあり、船舶の制御や海洋構造物、Underwater Robotなどの研究を行っている海外の研究所を訪問しようと決めました。その結果、平成14年11月26日より12月9日まで下記の行程でヨーロッパを訪問させて頂きました。
・11月27日〜29日
Norwegian University of Science and Technology(Trondheim, Norway)
・12月2日、3日
IMarEST本部(London, UK)
・12月6日
University of Newcastle upon Tyne
(Newcastle, UK)
以降ではそれぞれの訪問先の印象について述べさせて頂きます。
3. Norwegian University of Science and Technology
私は、今回初めてノルウェーに行ったのですが、まず、日照時間が短く、朝9時過ぎから明るくなり、午後4時には暗くなってしまうことにびっくりしました。
さて、Norwegian University of Science and Technology(NTNU)はノルウェーで唯一の工科系大学です。NTNUは、Thor I. Fossen教授の研究室を訪問させて頂こうと思い選択しました。しかし私自身はFossen教授とは全く面識がなかったため、東京商船大学の大津皓平教授に紹介して頂きました。大津教授はFossen教授と同様に操船制御に関する研究などされており、Fossen教授の研究室と相互に学生の受入を行うなど非常に親しくされており、私からのお願いも快く引き受けてくださいました。ちょうど私が訪問させて頂いた頃には大津研究室より田丸人意氏が留学していたこともあり、田丸氏にFossen教授との連絡のサポートをして頂き、私がNTNUに滞在中は田丸氏の部屋を共同で使わせて頂きました。
さて、ご存じの方もいらっしゃるかと思いますがFossen教授はDept. of Marine Cyberneticsに所属しており、
・船舶のモデリング、制御
・海洋構造物などの制御
・非線形制御理論
などの研究をされており、これらの研究に関する本も数冊執筆されています1,2,3)。特に船舶の制御に関して有名であり、訪問先に選定したのも船舶の制御に関して、ディスカッションを行いたいためでした。
初対面にもかかわらずFossen教授は暖かく迎え入れてくれ、研究の打ち合わせ等でお忙しいにもかかわらず、ご自身の行っている研究に関して説明してくださいました。その際に私自身が、非ホロノミック系に対する制御理論の応用として船舶の制御を考えているという話をすると、同じDept.に所属するOlav Egeland教授を紹介してくださいました。Egeland教授は
・非線形制御理論
・非ホロノミック系の制御
・Underwater Vehicleの制御
・Underactuated manipulatorの制御
に関する研究をされており、特に非ホロノミック系の制御に関する研究で有名なOle Jakob Sordalenの博士論文の指導教官でした。Fossen教授はEgeland教授を紹介してくださるだけでなく、Sordalenの博士論文もくださいました4)。他にもDept. of Marine Technologyに所属し、
・Underwater Robotの制御
・船舶の制御
・海洋構造物の制御
に関する研究をされているAsgeir J. Sorensen教授も紹介してくださり、Dept. of Marine TechnologyにあるMarine Cybernetics Laboratory(MC Lab.)という実験施設を見学する手配もしてくださっていました。MC Lab.は企業と大学が共同で維持している実験設備であるため、写真撮影は許可されませんでしたが、波を発生させることの出来る非常に大きな実験水槽(260m×10. 5m×5. 5〜10m)、回流水槽などを用いて海洋構造物の姿勢制御などの実験をしているところを見学することが出来ました。
NTNUでは海洋工学に関するCOEプロジェクトを行っていることもあり、マリンエンジニアリングに関する研究に対するパワーを感じました。スタッフに恵まれていることもあり、私自身もNTNUで落ち着いて研究を行ってみたいと強く思いました。Fossen教授にその話をすると、“部屋は用意できるから来てくれ”ということも言ってくださいました。今回面会した教授陣と今後も連絡を取り合っていこうという約束をして、NTNUの訪問は終わりました。
Fig.1 Fossen教授(右)と一緒に
| (拡大画面:480KB) |
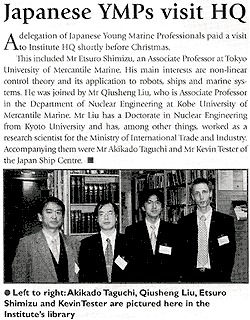 |
Fig.2 IMarEST訪問を伝える記事
4. IMarEST
NTNUのあるノルウェーからイギリスに移動して、LondonにあるIMarEST本部を訪問致しました。ノルウェーと比較するとLondonは暖かくちょっとほっとしました。しかし、雨の降る回数の多さにはびっくりしました。
IMarEST本部は、当初は他の調査研究分野で派遣されているYME使節員とそろって訪問する予定でしたが、仕事の関係上、都合が悪くなった方もいたため、結局、神戸商船大学の劉秋生助教授と二人で訪問させて頂きました。IMarEST訪問に関しましては、Japan Ship Centre(JETRO)の松村純一氏他、Fig.2に一緒に掲載されております田口晶大氏、Kevin Tester氏にお忙しい中、サポートして頂きました。
初日はIMarEST本部内を見学させて頂き、Director GeneralであるKeith Read氏を初め、John Butchers氏、Ed Hansom氏、Graham Hockley氏、David Long氏他と面会し、IMarEST本部の業務内容の説明の他、図書室等を見学させて頂きました。マリンエンジニアリングに関する書籍は世界中から集めているそうで、蔵書数の多さにびっくりしました。余談ですが日本マリンエンジニアリング学会誌もちゃんと保管されていました。
二日目は、IMarEST本部のMarie Barford女史がアレンジしてくださったマリンエンジニアリング関係企業
・JP KENNY Ltd.(Paul Jukes氏)
・Lloyd's Register of Shipping(Neville Harrison氏)
・Denton Europe Ltd. (Richard J. Palmer氏)
・Shell Shipping Technology(STASCO)(Alex Brigden氏、Michael G. Osborne氏)
を訪問し、海底ケーブルの敷設作業や海上輸送、船舶の運航管理等を行っているとの企業概要の説明を受け、業務内容に対する質問を受けつけて頂きました。日頃でも企業を訪問することが少ないにも関わらず、海外の企業の訪問は初めてであったために、いろいろと失礼な点もあったのではないかと思いますが、皆さん丁寧に説明してくださり、大変勉強になりました。
5. University of Newcastle upon Tyne
YME派遣の最後の訪問先として、England北部のNewcastleにあるUniversity of Newcastle upon TyneのTony Roskilly教授の研究室を訪問させて頂きました。
Newcastleに関してはLloyd's RegisterのHarrison氏、STASCOのBrigden氏から、この後Newcastleに行くという話をしたところ、“寒いところだから気をつけて”と言われていたので寒さを覚悟していたのですが、ノルウェーと比較するとまだ暖かかったので少しほっとしました。ちなみにHarrison氏、Brigden氏ともにRoskilly教授の教え子だそうです。
Roskilly教授はISME2000の際に特別講演を行われたので、ご存じの方も多いのではないかと思います。私もISME2000の際に名刺交換はさせて頂いたのですが、ほとんど、話が出来なかったため、訪問に際しては、YMEの生みの親であり、YMEのコーディネータである青木雄二郎前会長に紹介して頂きました。約束の時間にRoskilly教授を訪ね挨拶をしますと、私のことも顔を覚えていてくださいました。Roskilly教授は
・エンジンシステムの制御
・船舶の制御
・Underwater Robotの制御
などマリンエンジニアリング全般の制御に関して研究されています。Roskilly教授は非常にお忙しいようで、電話もよくかかってきているにも関わらず、自ら、これまでの研究内容、私の訪問後に導入予定のエンジン制御を研究するための実験設備等に関して説明してくださり、さらに私自身がロボットの研究を行っているとお話ししたところ、ロボットの研究を行っている研究室も案内してくださり、その研究室の方々も紹介してくださいました。また、Roskilly教授といろいろと話している際に、Newcastleに来る前にNTNUのFossen教授やEgeland教授に会ってきたと話をするとRoskilly教授もFossen教授やEgeland教授をよく知っているとおっしゃっていました。皆さん、マリンエンジニアリングの分野に関わっていることは確かですが、制御に用いている手法が異なるため、あまりご存じないのではないかと思っていたのですが、Roskilly教授の顔の広さにびっくりすると同時に、研究者間の交流が研究を進めていく上で重要なのだと改めて感じました。
Roskilly教授とは研究だけの話ではなく、Roskilly教授の可愛いお嬢さん(ブロンドに青い瞳だそうです)の話にもなり、“時間があれば紹介したのだけれど”と言ってくださったので、“今度は私も家族を連れてNewcastleをゆっくり訪問しにきますので、そのときにはお願いします。”と約束して別れました。
Fig.3 Roskilly教授(左)と一緒に
6. おわりに
このたびYME使節員として、ヨーロッパの大学ならびに企業を訪問させて頂いたのですが、私のつたない英語にもかかわらず、皆さん、やさしく説明してくださり、私の話している内容も理解しようとしてくださりました。この場を借りて皆さんのお気持ちに感謝するとともに、相手の親切心に甘えてばかりいられないと感じ、より英語を勉強しなければならないと痛感致しました。また、今回の訪問先で大変よくして頂いたのは私を訪問先に紹介してくださった方々のこれまでのお付き合いがあったからこそだと思います。私を紹介してくださったことに感謝するとともに、皆さんの築き上げてきたものを壊さず、私も他の方々に継承できるようにしたいと思っております。
訪問させて頂いて感じたのは、ヨーロッパでは日本と比較してマリンエンジニアリングという分野が確固たる地位を築いているということでした。日頃から日本は船舶がなければ成り立たない国であるにもかかわらず、マリンエンジニアリングの認知度が低く感じていましたが、今回、訪問させて頂いてより強く感じるようになりました。今後、今回の経験を生かしてマリンエンジニアリングの認知度アップに貢献できるよう努力しようと思っております。マリンエンジニアリングに対する認知度が上がれば学会の活性化にも繋がるのではないかと思います。
また、研究者同士のコミュニケーションも重要だと感じました。一つの分野、国にとらわれず、広くディスカッションを行っていくことが研究を進めていく上で重要だと感じました。今回、得られた人脈を生かしていくことはもちろんですが、今後は国内外の他の研究を行っている人とも積極的に交流を持ち、横断的な研究を行うまでに発展させることが出来ればよいなあと思っております。もし、私の研究内容、訪問した先等に興味を持った方がいらっしゃいましたら、遠慮なく、ご連絡頂ければと思います。とりあえず雑談のようなところからでも交流が始められればよいのではないかと思います。
最後に、今回のような形での研究室訪問の機会はなかなか得られないものでしたので、このような貴重な経験をさせて頂いた日本マリンエンジニアリング学会並びに日本財団の関係各位に深く感謝の意を表します。
参考文献
1)Fossen, T.I., Guidance and Control of Ocean Vehicles, John Wiley & Sons Ltd., (1993)
2)Nijmeijer, H. and Fossen, T.I. (eds. ), New Directions in Nonlinear Observer Design, Springer-Verlag. (1999)
3)Fossen, T.I., Marine Control Systems: Guidance, Navigation and Control of Ships, Rigs and Underwater Vehicles, Marine Cybernetics, (2002)
4)Sordalen, O.J., Feedback Control of Nonholonomic Mobile Robots, ITK-report 93-5-w, (1993)
*原稿受付 15年3月31日
**正会員 東京商船大学(江東区越中島2−1−6)
|