|
表2 キューイング例
| (1)いつ |
4、3、2、1(カウントダウン)、サンハイ! |
| (2)どこで/どちらへ |
その場で、前へ、右手の方へ、こちらへ |
| (3)何を |
膝を曲げましょう、かかとを前へ、手を前にパンチ! |
| (4)いつまで |
あと4回!もう一度左右に! |
| (5)どのように |
腰を反らせないように!お腹に力を入れて! |
| (6)かけ声 |
ソレー!ハー! |
| (7)動機づけ |
そうそう!大丈夫! |
| その他の言葉がけ |
もう一度繰り返しますか?これが最後! |
|
表3 注意する動作
| 動作 |
注意点 |
| 背すじの伸展 |
背骨の曲がっている人に対して「背すじを伸ばす」という説明は避ける |
| 膝の屈伸 |
膝屈伸時の膝と足先の向きをそろえる 屈角度が90度以上にならない |
| 膝、肘の伸展 |
過伸展させない |
| 腰の伸展 |
反らせすぎない |
| 上肢の挙上、回旋 |
痛みのある人は腕を肩の高さ以上に挙げない |
|
c. 指導方法
指導の際には、わかりやすいキューイング*と余裕のある動作展開を行い、参加者の動き具合を見ながら臨機応変に運動強度を調節することを心掛ける。
指導者は参加者全員がよく見える位置にいることを確認し、参加者と向かい合って鏡となるように動いたり、背を向けて参加者と同じように動いたりしながら指導する。複数の指導者がいる場合は一人が鏡になりキューイングを出し、他の指導者は参加者の間に入り同じ動作をするとよい。
キューイングは、(1)いつ(タイミング)、(2)どこで/どちらへ(場所/方向)、(3)何を(動作の名前)、(4)いつまで(回数)、(5)どのように(動作の注意点)を動作に先立ち簡潔かつ明確に伝える(表2)。次の動作に移るタイミングより前(2×8から1×8カウント前)に余裕をもって行うようにする。そのほかに、(6)かけ声、(7)動機づけとなる言葉がけをして積極的なコミュニケーションを図る。さらに、声のトーンや話すスピードを変えて工夫をするとよいが、早口は避けてはっきりと指示する。進む方向や回数は、顔の向き、手指のジェスチャーも入れて示すとわかりやすい。また、次の動作に移る前に余裕がほしいときは「足をとめて膝の屈伸をしましょう」とキューを出し、両足をそろえた屈伸動作を入れて一休みすると無理なく次の動作に入ることができる。
各動作を指導する手順は、1)下肢の動作を練習してできるようになったら上肢の動作を加えていく、2)ゆっくりのテンポで練習してできるようになったら本来目標とする倍の速いテンポにすることである。1)の例として、まず一種類の足の動作を行い慣れてきたら手の動作を加える、手足を合わせてできるようになったら次の足と手の動作を同様に練習し、できるようになったら二種類の動作を連続して行ってみる。または、初めに二種類の足の動作を連続してできるようにして最後に手の動作をつけてみてもよい。2)に関しては、速いテンポに変えたときにできない人がいた場合に備え、ゆっくりのテンポでもできるカウントでパターンを作っておき臨機応変に対応する。
d. 注意点
からだの使い方(筋肉、関節の使い方)によっては傷害を誘発させる場合があるため、参加者の姿勢・動作には注意を向けることが大切である(表3)。
*動作の内容ときっかけを合図すること
4. 例(表4)
(1)フォークダンス・パターン(運動強度・弱)
二重円をつくり、二人組で向き合い両手をつなぎ、相手を変えながらパターンを繰り返す。運動強度は低く、人と一緒に動いて楽しむことを主な目的とする。
(2)サルサダンス・パターン(運動強度・中)
二人組で向き合い、手または腕を組む。動作は重心移動が中心である。
前後のチャチャチャ:まず二人とも両足をそろえて立つ。初めに前に踏み出す人は、右足を1歩前へ出す(1)→左足はその場で足踏みをする(2)→右足を戻して左足にそろえて立つ(3・4)→左足を1歩後ろへ出す(5)→右足はその場で足踏みをする(6)→左足を戻して右足にそろえて立つ(7・8)、初めに後ろへ踏み出す人は上記の5〜8を先に行ったあと1〜4を行う。
クロス歩行:進行方向側の足を1歩横へ開く(1・2)→反対の足を交差する(3・4)→進行方向側の足をさらに1歩横へ開く(5・6)→反対の足をそろえて立つ(7・8)。
左右のチャチャチャ:進行方向側の足を1歩横へ出す(1)→反対の足はその場で足踏みをする(2)右足を戻して左足にそろえて立つ(3・4)→反対側も同様に行う(5・6・7・8)。
* 括弧内はカウント数
* 余裕があればチャ(1)・チャ(2)・チャチャチャ(3・4)のように3・4拍目でそろえて立つ代わりにその場で足踏みを加えることもできる。
例)右・左・右左右、左・右・左右左、・・・
(3)エアロビクス・パターン(運動強度・強)
高い強度で全身を持続的に動かすことを目的とする。動作の組み合わせしだいで強度を弱くして持続させることも可能である。例)上肢の動作のアレンジ
(4)椅子に座って行うパターン(運動強度・弱)
椅子に座り下肢への負担を軽減することにより膝・腰に痛みのある参加者も行えることを目的とする。例は、釣りバカ日誌のテーマ音楽に振り付けたものである。
表 4例
| *最上段の1〜4のあと次段の1に続く |
| *上:上肢の動作下:下肢の動作 |
| (1)フォークダンスパターン(運動強度・弱) |
| |
1(8カウント) |
2(8カウント) |
3(8カウント) |
4(8カウント) |
| |
右のかかとを前へ2回 |
左のかかとを前へ2回 |
円の中心に4歩進んで膝の屈伸1回 |
円の外側に4歩戻って膝の屈伸1回 |
| |
その場で太腿たたき2回、相手と手拍子2回を2セット |
相手と同じ側の手を交互に8回合わせる 右・左・右・・・左 1・2・3・・・8 |
片手をつなぎその場で一周回る |
右隣に移動 相手を変えて繰り返し |
|
| (2)サルサダンスパターン(運動強度・中) |
| |
1(8カウント) |
2(8カウント) |
3(8カウント) |
4(8カウント) |
| |
前後どちらかのチャチャチャ 1回 |
〃
1回 |
〃
1回 |
〃1回 |
| |
進行方向にクロス歩行 1回 |
左右どちらかのチャチャチャ 1回 |
〃
1回 |
|
| (3)エアロビクス・パターン(運動強度・強) |
| |
|
1(8カウント) |
2(8カウント) |
3(8カウント) |
4(8カウント) |
| A |
上 |
|
|
屈伸と同時に手拍子 |
〃 |
| 下 |
前へ歩く
8歩 |
その場で歩く
8歩 |
足をとめて膝の屈伸
2回 |
続けて
〃
あと
2回 |
| B |
上 |
両腕を前にパンチ
2回 |
〃 |
両腕を前にパンチ
4回 |
〃 |
| 下 |
かかとを交互に前へ(右・左)
2回 |
続けて
〃
2回 |
倍のテンポで
(右・左・右・左)
4回 |
続けて
〃
4回 |
| A' |
上 |
後ろへ歩く 8歩 |
|
屈伸と同時に手拍子 |
〃 |
| 下 |
|
その場で歩く 8歩 |
足をとめて膝の屈伸 2回 |
続けて
〃
あと 2回 |
| C |
上 |
足と同時に両腕を横に開閉屈伸時に手拍子 |
〃 |
〃 |
〃 |
| 下 |
右へ2歩右へ1歩出し開脚で膝の屈伸1回右足を戻して立つ |
左へ2歩左へ1歩出し開脚で膝の屈伸1回左足を戻して立つ |
もう一度右へ
〃 |
もう度左へ
〃 |
| D |
上 |
足と同じように腕を開閉 |
〃 |
左手から同様に |
|
| 下 |
その場で足を開いて閉じる開(右左)、閉(右左) 2回 |
続けて
〃
あと2回 |
左足から
〃
開(左右)、閉(左右) 2回 |
続けて
〃
あと2回 |
|
| (拡大画像:652KB) |
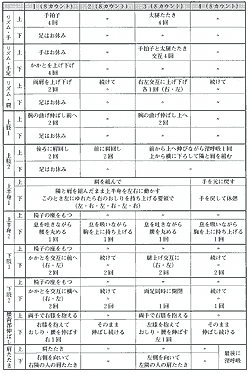 |
●引用文献
1) Whipple RH: Improving balance in older adults: Identifying the significant training stimuli. Gait Disorders of Aging Falls and Therapeutic Strategies (Masdeu JC et al eds). 355-379. Llppincott-Raven, New York, 1997
2)上野勝則, 武藤芳照, 黒柳律雄, 太田美穂:高齢者の運動の適応と禁忌, 身体教育医学研究2:35−37, 2001
3)黒柳律雄:健康診断, 身体機能測定―整形外科的診察, 武藤芳照, 黒柳律雄, 上野勝則, 太田美穂編, 転倒予防教室―転倒予防への医学的対応―, 41−43, 日本医事新報社, 東京, 1999
●参考文献
1)2001年度日本船舶振興会(日本財団)補助事業「ケアポートを核とした元気むらづくり事業」(事業組織:社会福祉法人みまき福祉会, 身体教育医学研究所)
2)平成11年度三菱財団社会福祉助成「高齢者の転倒予防のための屋内及び温水プールでの運動遊びの開発」(代表研究者:武藤芳照)
3)上岡洋晴・他:高齢者の転倒・転落事故に関する事例研究.東京大学大学院身体教育医学研究科紀要38・441−449, 1999
4) Greenspan SL et al: Fall direction, bone mineral density, and function; Risk factors for hip fracture in frail nursing home elderly. Am J Med 104:539-545, 1998
|