|
●資料
高齢者の転倒予防のための運動プログラム(2)
―リズム運動―
Exercise Program for Fall Prevention in the Elderly
―Rhythmic Exercises―
| 高橋 美絵a |
山田 美穂b |
| Mie TAKAHASHIa |
Miho YAMADAb |
a 東京大学大学院身体教育学講座武藤研究室
b 東京厚生年金病院健康管理センター
a Laboratory of Prof. Mutoh, Department of Physical and Health Education, The Graduate School of Education, The University of Tokyo
b Health Center, Tokyo Koseinenkin Hospital
Abstract
This paper, from an exercise instructor's standpoint, introduces: 1) risk management, 2) composition and teaching techniques, and 3) four examples of rhythmic exercises practiced in the Fall-Prevention Program for the elderly at Tokyo Koseinenkin Hospital. Here we define the purpose of rhythmic exercises as: to enjoy the whole body moving rhythmically in harmony with music in order to activate all the major muscle groups in concert. In addition, it is supposedly effective as balance training in consequence of weight shifting, such as forward, backward, side, up and down movements. It is important for these goals to apply safe, effective and enjoyable programs according to the physical conditions, physical abilities, personal favors and characteristics of participants.
For risk management, physician and orthopedist offer thorough medical examination and consultation prior to exercise. Exercise instructors plan the contents and exercise strength of program with regard to doctor's evaluation and recommendation. Doctors and nurses attend exercise sessions.
Composition techniques explain how to outline the program. Important factors are: time duration, exercise strength, movement patterns, music and flow of program. Teaching techniques refer to cueing and movement development.
Four examples, each differing in exercise strength, include three standing exercises: folkdance, salsa dance and aerobic versions, and one seated exercise.
| Key Words: |
Elderly, Fall Prevention, Exercise, Rhythmic Exercises |
| |
高齢者、転倒予防、運動、リズム運動 |
1. はじめに
本報告では高齢者の転倒予防を目的とした運動プログラムの一例として、東京厚生年金病院・転倒予防教室におけるリズム運動の構成とその指導方法を運動指導者の立場から解説する。リズム運動は「音楽に合わせて、楽しくリズミカルに全身運動を行う」ことで「自然に全身の筋肉を活動させる」ことを目的としている。指導者は、これらの目的を達成するために参加者の身体状況、運動能力、その他参加者の趣味や特徴を把握し「安全で楽しく効果のある」運動プログラムを構成・指導する。また参加者は、初めは音楽に合わせて動くことが苦手な場合も少なくないが、慣れてくるにしたがってリズムにのって動く楽しさを覚え、持続して運動する充足感を感じている。
2. 期待される効果
一般的に、大きな筋群を持続的に動かす有酸素運動は、筋量増加と体脂肪の減少、筋力・全身持久力の向上の効果がある。また本教室のプログラムでは、体温、筋温、心拍数を上昇させからだを温める効果、関節部(特に肩関節、股関節、膝関節)の運動により関節可動域を広げ動きを滑らかにする効果、下肢と上肢を組み合わせて動くことにより神経・筋の協応性を高める効果、前後左右の重心移動・上下の振幅動作によるバランス訓練効果、骨への刺激により骨そしょう症の進行速度を遅延させる効果を目指している。
Whipple1)の報告によると、転倒予防のための効果的なバランス訓練は、(1)自己の体重不可が十分にかかる、(2)水平方向への速い移動と合わせて身体の各セグメントの相互作用がある、(3)垂直方向への振幅を伴うトレーニングであるとされ、リズム運動はその要素を全て含めることができる。つまり、前方、側方、後方への転倒を防ぐバランス訓練の効果が期待できる。
3. 方法
指導者は、参加者全員が一緒に楽しみながら、できるだけ持続して動くことを目標とする。そのためには、安全への配慮及び参加者が動きやすい構成と指導上の工夫が大切である。
a. リスク管理
音楽や人の動きに合わせて動く緊張感と興奮の中で運動を持続すると、心拍数や血圧の過度な上昇、発汗による脱水、下肢の疲労、筋肉と関節の痛みが生じるおそれがある。特に高齢者にとって運動の効果とリスクは表裏一体であり、過度な運動がそのまま重篤な傷害や疾患につながる可能性が高いため、適度な運動であるかを常に配慮しなければならない。そこで本教室では、事前に参加者に対して「運動ができるか」、「どのレベルの運動なら安全で長続きできるのか」の二点を主眼に内科医と整形外科医の診察を行い、診察所見と病歴から評価をしている2)。運動が可能と判定した場合、指導者は事前と運動当日の診察記録から注意事項を確認し、運動内容と強度を設定する3)。運動中は、顔色と動き具合に目を配り、参加者一人一人にこまめに言葉がけをして心身状態の確認をする。本教室では、医師、看護婦も運動の様子を観察している。また運動前後には水分補給を積極的に促す。
b. 構成方法
構成する際、あらかじめプログラムをいくつかパターン化しておくとよい。例えば、立位で行うもの、座位で行うもの、上肢と下肢の動作を組み合わせて反復するエアロビクス風のもの、ジャンケンを取り入れたゲーム性のあるもの、人と組んで動くダンス風のものなど運動強度と趣向の異なるものを複数用意しておく。
実際に構成する手順として、まず参加者に適した運動時間、強度を設定する。本教室では、10分前後持続して運動することを目標に強度を設定している。次に、設定強度に即したパターンを決め動作の組み合わせを検討する。音楽は、いくつかのパターンに合わせて事前に用意しておくと便利である。最後に指導の流れを作り上げる。表1に構成する際の枠組みを示す。パターンの具体例は4. 例に示す。
表1 構成の枠組み
| (拡大画像:514KB) |
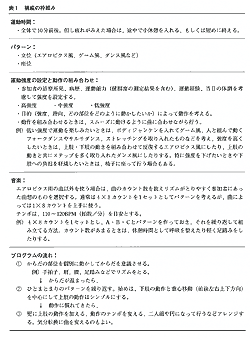 |
|